
商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回は、「建築」と「仕掛け」を融合させた場づくりを通じて、賑わいやコミュニティづくりを目指している株式会社リライトの籾山真人さんと、これからの商業施設について語り合います。これからの時代、いかにして地域や人を巻き込みながら持続可能性を保つのか、商業施設はどのような役割を果たすべきかについて対談しました。今回はその前編です。
メディア運営と拠点開発を通じた地域コミュニティづくり
村井:籾山さんは、メディア運営を通じた地域コミュニティづくりなど、独創的な取り組みをされています。その一例として、東京都立川市で携わった取り組み(以降「立川プロジェクト」)について教えていただけますか。
籾山:立川プロジェクトは、2009年から2014年まで僕を含めた複数のメンバーが、課外活動的に行った取り組みです(※1)。かつての活気が失われつつあったJR立川駅北側の商店街(※2)を舞台に、地元コミュニティFMを活用した「メディア運営」と、空き物件を活用した「コミュニティ活動の拠点づくり」を行いました。エリア内外でさまざまなソーシャルグッドな取り組みをされている方にゲストとしてラジオ番組に出演してもらったこと、さらにラジオを通じて生まれたコミュニティの受け皿となるカフェやシェアアトリエをつくったことなどを通して、地元でのつながりが加速度的に広がっていきました。
(※1)リライトは籾山さんが2008年に起業。「立川プロジェクト」をきっかけに、別々の組織で活動していた立ち上げメンバーが協業するケースが増え、その後徐々にリライトに参画していくことになった。
(※2)1977年まで立川駅北側至近には米軍基地があり、プロジェクトが展開された商店街は、基地の門前に位置する歓楽街として賑わった。

「立川プロジェクト」では、2009年10月から約3年半、FMたちかわでラジオ番組「東京ウェッサイ」を毎週放送。「東京の西側をステージにユニークな活動をする人たちを紹介するラジオ番組」をコンセプトに、各回さまざまなゲストを招いてその取り組みなどを紹介した
※写真提供:リライト
村井:私たちは順番としてまず商業施設などの場ありきで情報誌などのメディアを作成することが多いですが、籾山さんたちはまずラジオというメディアから始められたことが興味深いと思いました。
籾山:コミュニティラジオというメディアを使ったおかげで、「まちづくり」活動を始めたばかりの若者たちが、会ってみたいと思った人をゲストに呼ぶ口実ができました。さらに、放送後にゲストを交えた交流会をカフェで行っていたので、ゲストに興味を持った地元の若手たちが、放送後に自然とカフェに集まってくるようになりました。メディアの運営だけでなく、そこにリアルな場もあったことで、いろんな人たちが交流できるサロンのような場が生まれたのです。
地域のイノベーター・アーリーアダプターを集め、アクションを促す
松本:コミュニティについて言うと、これまでの識者の方との対談では、セミパブリックな縁側のようなコミュニティや、販売員と顧客が友達のようになれるコミュニティ、働く人を巻き込んだ商業施設全体のコミュニティ化といったアイデアが出てきました。籾山さんが生み出していくコミュニティの特徴は、地域の人たちが深く関わることがポイントだと思うのですが、いかがでしょうか。
籾山:僕は、マーケティング分野でいう「イノベーター理論」(※3)が地域コミュニティづくりにおいても援用できると考えています。つまり、既に自身で地域活性に取り組んでいるような層をイノベーター、まだ活動するには及んでいないものの地域に関心のある層をアーリーアダプターとすれば、まずそのような人たちにピンポイントで関わってもらいたいし、巻き込んでいきたい。どうすれば、その層を地域から見つけ出せるのか、さらにその層に主体性を持って関わってもらえるのかということを考えています。
(※3)新しい商品やサービスなどが市場に普及する際、消費者を5つの層に分類する考え方。普及していく順に、イノベーター(革新者)、アーリーアダプター(初期採用者)、アーリーマジョリティ(前期追随者)、レイトマジョリティ(後期追随者)、ラガード(遅滞者)と呼ぶ。
松本:具体的にはどんなことをするのでしょうか。
籾山:例えば、リライトが関わったJR中央線の「ののわプロジェクト」(※4)では、地域で既にソーシャルグッドな活動を行っている“イノベーター”をトークイベントのゲストに呼ぶことで、お客さんとして地域住民の中でも情報感度が高く地域活性に関心のある“アーリーアダプター”をピンポイントに拾い上げることができました。加えて、フィールドワークや食をテーマにしたイベントなどを定期的に実施することで、今度はアーリーアダプター同士の横のつながりをつくります。ちなみに、このイノベーター理論の考え方は、そのまま立川プロジェクトにも当てはめることができます。ラジオのゲストがイノベーターで、交流会に来てくれる人がアーリーアダプターという感じでしょうか。
(※4)2010年にJR中央線三鷹〜立川間の高架化工事が完了したことにより、高架下空間の活用、中長期的な沿線価値向上を目指して、「中央ラインモール構想」がスタート。リライトでは、その一環として「ののわプロジェクト」を立ち上げ、周辺の隠れた名所やお店を紹介するエリアマガジン『ののわ』の企画・制作を行った。また、このエリアマガジンと連動する形で「ののわWEBサイト」「地域連携イベント(トーク/フィールドワーク/試食)」も同時に展開。
村井:なるほど。今後テレワークが普及して、自由に好きな地域に住めるようになると、同じ嗜好性を持った人たちが集まってくる可能性があります。そうすれば、横のつながりもつくりやすくなりそうですね。しかし一般的に、コミュニティができると、新しい人が参加しにくい内輪の雰囲気ができてしまうことがありますね。
籾山:そうですね。イノベーターやアーリーアダプターだけではなく、コミュニティの裾野をもっと広げていく工夫も大事だと思います。例えば、「ののわプロジェクト」では、「地域ライターネットワーク」という活動も行いました。WEB版の「ののわ」では、地域住民にライターになってもらい、企画から取材、記事化までを行う仕組みをつくったのです。地元に愛着を持った地域ライターさん自身のつながりを通じて、バズった記事が出てくるケースもありました。こうした取り組みを通じて、次第にコミュニティの裾野を広げることができたのではないかと思います。
地域の小規模事業者のコミュニティを束ねるイベント
松本:2012年から5年間、ルミネ立川の屋上庭園で「あおぞらガーデン」というイベントを企画されましたね。
籾山:この取り組みは、駅ビルの屋上という遊休スペースを活用するとともに、地域コミュニティとの連携を通じて、これからの郊外型駅ビルの在り方を考えるという大きな課題設定がありました。
そこで、地元のお店や地元の作家さんなど、小規模な出店者さんを中心としたマルシェイベントを行うことにしたのです。出店者さんのSNSと館内ポスターぐらいしか告知はしなかったのですが、初年度は毎日1000人以上の来場者がありました。特筆すべきは、その約8割がこのイベントを目指して足を運んでくれた「目的来場」だったこと。さらに、ルミネがなかなか取り込めていなかったファミリー層に来場してもらうことができました。
「地域を巻き込んだ賑わいイベント」としてだけでなく、「郊外型駅ビルにおける新しい販促手法」を示せたことで、「あおぞらガーデン」は5年間継続し、我々にとっても大きな学びになりました。

2012年、リライトが企画運営を行い、ルミネ立川の30周年イベントとして、屋上庭園を使った「あおぞらガーデン」を開催。ブックカフェやマルシェ、参加型のものづくりワークショップなどが行われた。イベントは好評で、2016年まで継続された
※写真提供:リライト
籾山:このイベントの成功については、出店してくれた地元のお店の方々が既にコミュニティを持っていたことで、我々が告知をほぼしなくても集客できたところが大きいです。元々その人たちが持っているコミュニティを束ねることで、そこでしかつくれないコミュニティづくりを実現できました。出店者さんが持つコミュニティを生かすことで、ルミネ立川に対するエンゲージメントを高めることにつながった気がします。消費者同士の新たなコミュニティ形成に貢献できたかは分かりませんが、少なくとも、潜在的なファンを増やすことができたのではないでしょうか。
村井:一般の消費者ではなく地域の小規模事業者に注目したのが興味深いです。こういった人たちであれば、都心に勤める会社員よりも地域のネットワークが強く、SNSや口コミによる地元集客が可能になるのですね。
松本:地域の小規模事業者の方だからこそ、その地域に関わる覚悟と熱量を持っているという点も、うまくいった秘訣でしょうか。商業施設と地域との関係性も、もっとさまざまなつくり方ができるのかもしれませんね。
前編では、籾山さんが手掛けてきたユニークな取り組みを中心に、地域のコミュニティづくりに対する考え方を伺い、そのポイントを話し合いました。後編では、これからの商業施設がどのような役割を果たすべきかを、引き続き籾山さんと考えていきます。
<後編に続く>
構成・文 松葉紀子

籾山真人(もみやままさと)
1976年、東京都生まれ。博士(工学)。2000年東京工業大学社会工学科卒業、2002年同大学院修了。2002年アクセンチュア株式会社入社。経営コンサルティング業務に従事。マネージャーとしてクライアント企業の新規事業立上げ、マーケティング戦略の立案などに携わる。2008年株式会社リライトを設立、同代表取締役就任。コミュニティバリューに着目し、賑わい創出に向けた仕掛けづくりに強みを持ち、さまざまな商業施設及び公共施設のプロデュースを行う。大規模商業施設や商業デベロッパー等をメインクライアントに、商業施設の企画や、周辺コミュニティを巻き込んだエリアマネジメントなどを手掛ける。2015年JCDインターナショナルデザインアワード金賞受賞(コミュニティステーション東小金井)、2016年グッドデザイン賞ベスト100及び特別賞[地域づくり]受賞(コミュニティステーション東小金井)、2019年グッドデザイン賞受賞(クマガヤプレイス)、グッドデザイン・ベスト100(コトニアガーデン新川崎)。









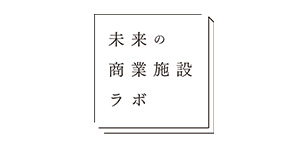








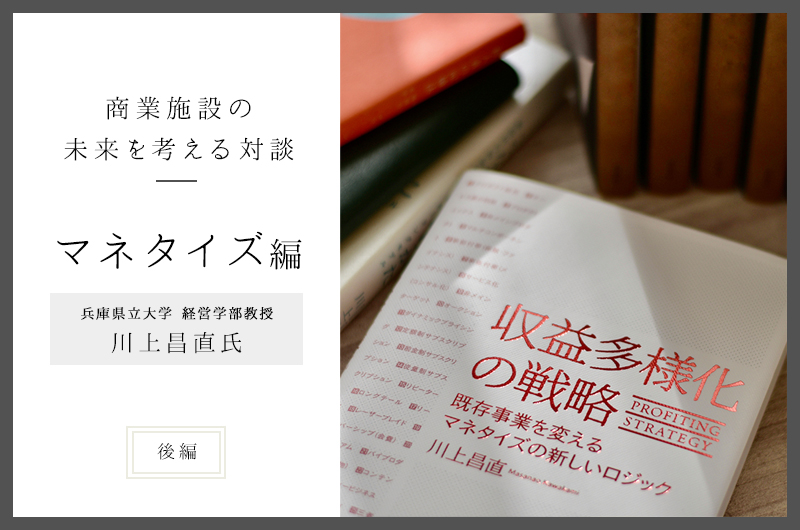



































村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー
2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。