
電動キックボードなどのマイクロモビリティが活況です。法律や制度、インフラの整備など、課題はありますが、今後、ますます普及していくでしょう。都市の大動脈である鉄道に加え、毛細血管のような役割を果たすマイクロモビリティがあることで、どのような社会・都市像になり、どのような消費が生まれるのでしょうか。
特に電動キックボードなど近距離移動に適した低速のマイクロモビリティに注目し、これまでの取材(EKISUMER VOL.52)やヒアリングをもとに、今後の消費のあり方を考えてみました。
ゆっくり短距離をマイペースに移動することで生まれる心理
まず、消費者はマイクロモビリティをどのように捉えているのでしょうか。電動キックボードのシェアサービス「LUUP」のユーザー(女性20代前半)にヒアリングしてみました。

- 乗ってみたら楽しかった。自分で漕がずに風を切って走れるので、スマートで気持ちが良い
- 電車やバスと違い、発車時刻や他の乗客に左右されることなくマイペースで動けるので、心に余裕が持てる
- 電動キックボードだと景色を見ながら、あえて遠回りして、ナビも入れずに自分の感覚でなんとなく目的地に向かう
- 自分の肌で感じて街を知る。ちょっと素敵なレストランを見つけたので今度行ってみようと思った
また、時速5kmの自動走行モビリティ「iino」の利用者からは、「普段見ている景色なのに、こんな所に緑があったことに初めて気付いた」とか、「乗ると不思議とボーッとして、急いでいたはずなのに『まあいいか』という気分になった」などの声が挙がったといいます。(PICK UP 駅消費研究センター VOL.47)
ここで注目したいポイントは、マイクロモビリティの持つ①移動自体の楽しさ、②マイペースに動ける自由度の高さという2点です。この2点に着目すると、どのような機会が考えらえるでしょう。
①目的地までの体験価値を高める
目的地までの道中の体験価値を高めるサービスとしてマイクロモビリティは活用できるのではないでしょうか。たとえば、リゾートでのホテルの送迎バスは味気ないものもありますが、駅からホテルまでの間の街並みや自然豊かな道などをマイクロモビリティで周遊することで、観光の気持ちを高める……。そんな演出をするような送迎サービスも考えられるかもしれません。
②街の魅力の再発見と消費喚起
マイクロモビリティで移動をすることによって、景色を見たり、あえて遠回りしたり……。マイクロモビリティの利用は、街の魅力の再発見と消費喚起にもつながっています。レジャーや観光に来た人だけでなく、通勤・通学している人や居住者も街の中で行ったことがない場所はあるでしょう。マイクロモビリティという移動手段を提供することで、改めて商圏の顧客の発掘・創出につなげることができるかもしれません。
マイクロモビリティとコミュニケーション
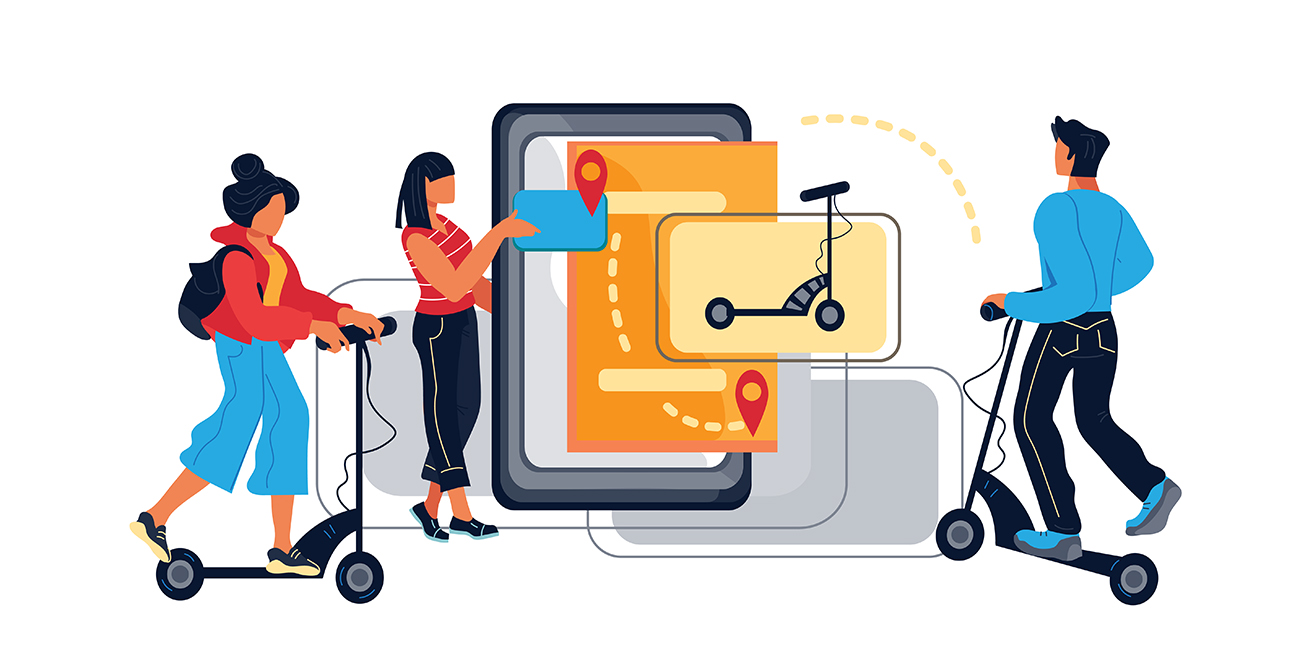
マイクロモビリティがあり街を自由に動けるようになると、情報提供はますます大事になると考えられます。マイクロモビリティで巡りたくなるようなルート情報が、ある種、「移動体験型の広告」となるのではないでしょうか。たとえば、住宅販売をする際に、駅から物件まで直行させるのではなく、あえて街のあちこちをマイクロモビリティで巡ってもらい、街の魅力を見つけてから物件を見てもらうことで、住宅の評価も上げられるかもしれません。駅から離れたショップでも、気持ちの良い海岸沿いを通るルートから店舗に行けば、気分が良くなって財布の紐を緩めて買い物をしてくれる……。そんなことも考えられるのではないでしょうか。
私たちは、長年、駅消費研究をしてきましたが、駅ビル・エキナカの発展は、駅という立地の利便性だけでなく、移動中という特有のシーンでの消費心理を捉えたからこその発展だと思っています。私たちは、オンからオフへといった「キモチスイッチ」、日常で小さな発見をしたい「未知との出合い」、会社や家での役割から解放されたい「個への回帰」といった移動中のインサイトを見出してきました。そうした移動中のインサイトをうまく捉えることで、駅で非計画購買を誘発させてきたのだと思います。今後、マイクロモビリティの普及に伴って、さらにミクロな移動インサイトが発生するのではないかと予想しています。そうしたミクロな移動インサイトを丁寧に捉え、サービスを設計していくことが、ビジネス成功のカギとなるのではないでしょうか。














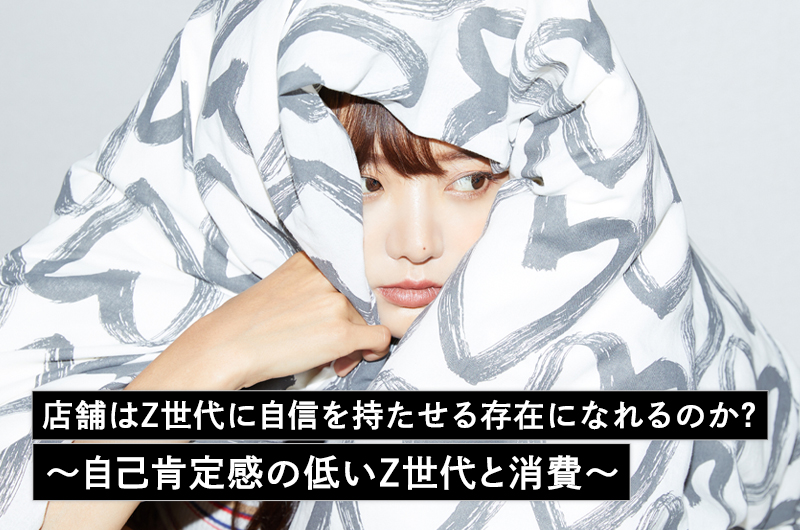

































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。