
商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。本連載では、当ラボメンバーによる、識者へのインタビューをお届けしています。今回のゲストは、昨年、働く場所や住む場所を自由に選べるようになった時代を考える著書『リビング・シフト 面白法人カヤックが考える未来』を刊行された、面白法人カヤックCEOの柳澤大輔さんです。東京から地域への移住が注目される中での、より良い地域づくりやそこで商業施設の果たすべき役割などについて、お話を伺いました。今回はその後編です。
<前編はこちら>
地域の特長を生かし、個性を打ち出す商業施設へ
松本:「リビング・シフト」が起きている今、商業施設が地域のためにできることがあるとすれば、どんなことでしょうか。
柳澤:その地域に出店する企業は、地域の特長を生かしながら、地域に貢献していくことが欠かせません。街ごとの特長を打ち出し、そこで得られた利益は街にしっかりと返していく。つまり地域内で良いものを循環させていくような商業施設になればいいと思います。
大手企業が出店する場合でも、地元のためにカスタマイズすることが大事です。経済合理性から考えると、似たような商業施設やお店をどの地域にもつくってしまいがちですが、それでは中央集権型で地域に利益が還元されませんし、同じような商業施設では魅力的ではなくなっていくと思います。地域と共存するためには、地元のカラーを色濃く打ち出しているような、ポリシーのあるテナントを集めるとか。それぞれの街がそうやって個性を出していければ、さまざまな違った魅力を持った街が増え、面白くなるのではないでしょうか。
松本:未来の商業施設ラボでは、商業施設がもっと、生活者の暮らしを支えるような機能を提供できればよいのではないかと考えています。カヤックでは、地元鎌倉で働く人を応援する「まちの社員食堂」を運営されていますが、商業施設にどのような機能があると良いと思いますか?
柳澤:やっぱり、コミュニティをどう活性化させるかが大事だと思うので、僕らが考えるとすれば、商業施設に「まちの社員食堂」のようなものをつくると思います。
「まちの社員食堂」は、ただ地元企業の人たちが食べに来るだけでなく、人と人がつながるハブのような場所にしようと決めているので、働く人同士や出店してくれる地元レストランの人同士などを、徹底的につなぐことを意識しています。LINEでは、メニューを配信するだけでなく、「今、こういう人が来ています」という情報を配信することもあり、その情報を見て食堂にやってくる人もいます。やりようによっては、人と人をつなぐことにしっかり踏み込むこともできるわけです。

鎌倉で働く人のためにつくられた「まちの社員食堂」は、JR鎌倉駅から徒歩約2分の場所にあり、面白法人カヤックをはじめ、鎌倉に拠点を持つ企業・団体21社が出資する共用の社員食堂。鎌倉にある55のお店が週替わりで健康的なメニューを提供。地域コラボイベントや交流イベントなども不定期に開催されている
働く人も巻き込み、商業施設全体をコミュニティに
松本:商業施設が人と人をつなげ、地域のコミュニティをつくり、さらに深めるためにできることは何かありますか。
柳澤:商業施設のお客さんたちをつなぐだけでなく、店舗スタッフを含めて、商業施設の中で働く人たちを起点としたアイデアもあると思うんですよね。あるコミュニティに所属しているというロイヤルティを感じるためには、ある程度の「“おらが街”感」が必要です。その点、商業施設で働いている人たちにはそこで働いているという所属感があるので、つながりを意識させやすいと思います。
そのとき大事なのは、人と人が楽しくつながっていくことに注力すること。とにかく楽しいという方向に施設側、運営側が音頭をとって進めていくと、働いている人だけでなく、やがてそこを訪れるお客さんも楽しい気持ちになるはず。そうしたことを徹底的に行う商業施設があると面白いのではないでしょうか。
例えば、働いている人同士が日常的に交流できる機会があったり、皆が心から楽しいと思えるイベントがあったり、お得な福利厚生などとは違う形で、働く人に投資していくようなイメージです。こういった取り組みを通して、働く人も巻き込んで商業施設全体がコミュニティ化していけば面白いと思います。
松本:今後、テクノロジーの発展でバックヤード業務が軽減されると、店舗スタッフはお客さまと接する時間が増える可能性があります。店舗スタッフが楽しい気持ちで働いていたら、お客さまもその輪の中に入りたくなるかもしれません。そもそも店舗スタッフも、アルバイトをしている地域のお客さまかもしれませんし……。
柳澤:そうですね。さらに言えば、働いている人たちには、単に自分のお店に立つだけじゃなくて運営にも関わってもらった方がいいと思います。例えば、店舗スタッフが、商業施設全体で取り組む企画を出したり、その地域のためになるプロジェクトを立ち上げたり。自分がそこを運営しているという意識を持てるように工夫する。そうして、関わりをどんどん増やしていくような設計を突き詰めるといいのではないでしょうか。
「まちのテーマパーク化」に貢献する商業施設
松本:ご著書の中では、「まちのテーマパーク化」という話をされていました。街ごとに突出したコンテンツを伸ばして、そのコンテンツが好きでたまらない人たちばかりが集まったら、日本中に多様性のある面白い街が増えると。
そうやって、何か好きなものが共通している人たちが集まるような街が生まれてくるとすると、そこで商業施設が果たせる役割は、何かあるでしょうか。
柳澤:地元企業とコラボレーションするとか、どんなことでもいいのですが、ハード面もソフト面も街ごとでカスタマイズして、ご当地のカラーを出していくことが欠かせないでしょうね。
松本:例えば、茨城県土浦市にある駅ビルの「プレイアトレ土浦」は、日本最大級のサイクリングリゾートとして全館を自転車に特化した施設にしており、土浦市の「テーマパーク化」に貢献したといえる事例だと思います。(未来の商業施設ラボ VOL.9参照)
柳澤:そうやって街自体が素敵になれば、土浦のように自転車好きが集まったり、移住してきたり二拠点居住を始めたりする人も出てきます。突出した魅力であれば、インバウンドも増えるでしょうね。
たとえ突出したテーマがなくても、何かを見つけて、そこから広げていくしかないと思います。商業施設の運営側が、自ら行政に働きかけ、住民をも巻き込んでいく。そうやって街を盛り上げていくのは本来楽しいことですし、やっている段階でワクワクしてくることなので、実際、そういう取り組みにチャレンジしたいという人はいると思います。
松本:商業施設が働く人のコミュニティとなったり、地域の個性を生かして「まちのテーマパーク化」に貢献したりすれば、そこにしかない新たな体験を提供できるようになるかもしれませんね。そうした世界を実現できるように、私たちも目指していきたいと思います。
次回以降も、未来の暮らしに関して、さまざまな識者の方へのインタビューをお届けします。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。
<完>
構成・文 松葉紀子

柳澤大輔(やなさわだいすけ)
面白法人カヤック 代表取締役CEO。1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社を置き、ゲームアプリや広告制作などのコンテンツを数多く発信。SDGsの自分ごと化や関係人口創出に貢献するコミュニティ通貨サービス「まちのコイン」は全国8地域で展開中(2021年5月31日時点)。さまざまなWeb広告賞で審査員をつとめる他、ユニークな人事制度やワークスタイルなど新しい会社のスタイルに挑戦中。著書に『鎌倉資本主義』(プレジデント社)、『リビング・シフト 面白法人カヤックが考える未来』(KADOKAWA)ほか。まちづくりに興味のある人が集うオンラインサロン主宰。金沢大学 非常勤講師、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授。「まち・ひと・しごと創生会議」有識者委員。








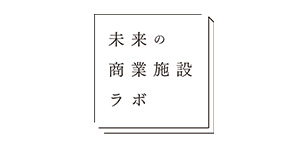


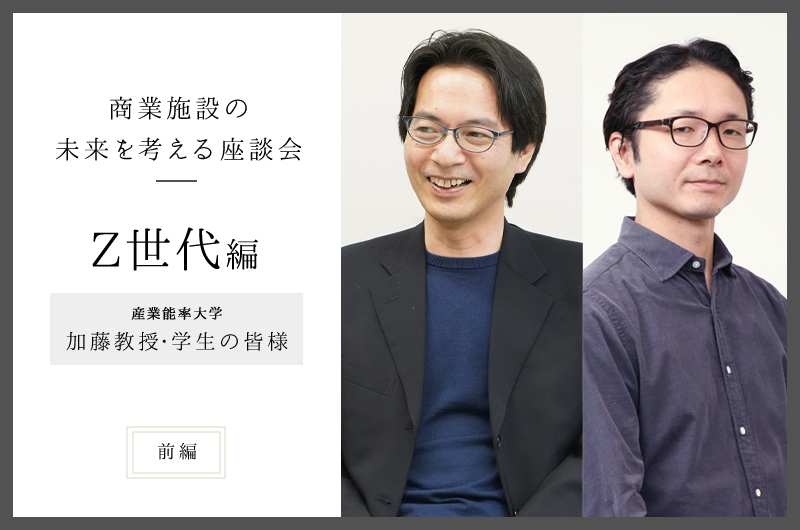


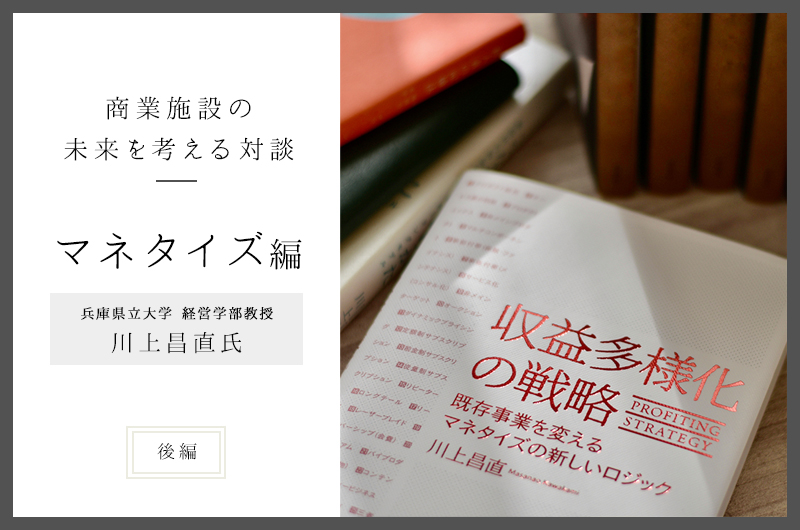



































村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー
2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。