
商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える「未来の商業施設ラボ」。「未来の商業施設ラボ」が考える新たなフレームワークをご紹介した前回に続き(VOL1参照)、今回は「未来の商業施設ラボ」にアドバイザーとして参画をいただいている産業能率大学の加藤肇教授と共に、この発想の背景や意義について話し合います。

加藤 肇(かとう はじめ)氏
産業能率大学 経営学部 教授
エキナカ・駅ビルなど移動の動線上に位置する商業施設特有の消費に注目。その固有性を行動と心理の両面から解き明かすと同時に、攻略法である移動者マーケティングを考案。現在は人口減少下での鉄道沿線の活性化をマーケティングの視点から考察している。元株式会社ジェイアール東日本企画 駅消費研究センター長。
「モノを売る場」の既成概念を脱し、新たな価値を考える
村井:「未来の商業施設ラボ」では、商業施設の「買い物の場」に代わる、新たな存在価値を考えるところからスタートしました。商業施設を取り巻く環境への危機感が背景にありますが、加藤先生はどのようにお考えでしょうか。
加藤:人口減少やモノ離れ、コト志向、オーバーストア、EC定着など、様々な変化があり、まさに過渡期と言えますが、中でもコロナ禍で加速した動きとして、テナント側のオムニチャネル化に注目しています。
テナントが消費者に自社ECで直接販売し、実店舗はメディアとして機能させる動きですが、テナントはもう既に実店舗の役割や意味を変えてきています。商業施設だけが今までと同じように、モノを売る場という定義に固執していたら、どう考えてもうまく行かないし、時代に取り残されてしまいます。
さらにコロナ禍でオンライン接客も活発になりました。「買わないと申し訳ない」とプレッシャーを感じることが少ない、自宅のワードローブの服と合わせられる、などの評価もあり、ECの進化は加速しています。

村井:接客はリアルの強みでしたが、お株を奪われてしまう可能性もありますね。商業施設の強みであった品揃えも今ではECの方が優れていて、商業施設の「買い物の場」としての価値がますます厳しくなりそうです。
加藤:もう変わらざるを得ない。そういう局面が目の前に来ていると感じます。「モノを売る場」という既成概念から脱却して、新しい次の価値をつくっていく。日本を代表する企業・メーカーのトヨタ自動車でさえ、モビリティカンパニーとして自ら価値転換を進めています。商業施設にもそういった改革の姿勢が求められると思います。
地域と一体化し、地域の価値を向上させる
村井:「未来の商業施設ラボ」では、商業施設が提供する新たな価値を「生活の質の向上」ととらえ、「家や街の機能の代替で、クオリティ・オブ・ライフを向上させる」という新たなフレームワークを考えました。商業施設のフードホールが「家」のダイニングキッチンの機能を代替したり、商業施設の芝生広場やオープンカフェが「街」の公園の機能を代替したり、様々な生活シーンでの利用を想定したものです。

加藤:このフレームワークのポイントは、商業施設が生活のあらゆる時間に寄り添い、生活の質の向上を目指すものですが、基本的なスタンスとして「地域との共生」が大切です。
人口減少や高齢化によって、地域経済の減速が懸念される中、商業施設の責任の範囲は地域全体にまで及ぶでしょう。
商業施設が地域の生活の質を向上させ、さらに地域との連携・一体化を志向することで、地域自体の価値を向上させることが理想です。その結果、行政や市民にとっては地域が活性化し、裏を返せば、商業施設にとっては商圏が活性化して、結果的に売上として戻ってくるといった、新しいウィンウィンの構造をつくるべきだと思います。
村井:今や商業施設と地域は運命共同体のようなもので、地域を持続可能にするために、商業施設がどうあるべきかを考える必要があるかもしれません。具体的にはどういったアプローチが考えられるでしょうか。
加藤:まず商業施設が地域の公共機能を支援することが考えられます。地域の機能の中でサービスが低下しているものをサポートする。街にある公園を民間のノウハウで活性化したり、図書館のサポートをしたりすることもあるでしょう。
商業施設が地域の窓口やコンシェルジュのようになることも必要かもしれません。例えば、商業施設は最初の相談だけ受け付けて、さらに手厚いサービスを求められたときは、地域の専門施設を紹介するなど、循環する仕組みを設けるわけです。商業施設のテナントと地域の個人商店が連携してサービスを提供するなど、新しい試みが考えられます。

村井:地域のコンシェルジュということだと、商業施設のアテンダントやスタッフなどの、人に求められる役割も変わっていくのでしょうか。
加藤:地域のことをよくわかっていて、地域の人脈も豊富な人、地域をよりよくしたいと思っている、地域を愛しているような人が良いですね。商業施設はそういった人材を採用し、地域と商業施設を繋いでくれるパイプ役として育成することが求められるかもしれません。地域や商圏、そこに関わる人は、リアルにしかない価値なので大切にしたいですね。
村井:商業施設が地域と一体化して、地域住民の様々な生活の時間に寄り添い、暮らし全体を豊かにすることができれば、その地域に住みたい人も増えるかもしれません。地域の価値が向上すれば活性化していきますよね。
商業施設を中核とした新たな地域像
村井:商業施設と地域の一体化について話をしてきましたが、コロナ禍を契機としたライフスタイルの変化で、地域の役割も大きく変化していくと感じます。加藤先生はどのような点に注目されていますか。

加藤:コロナ禍を契機としたテレワークの普及によって、郊外などの生活圏と都心などの生産圏を行き来する通勤スタイルが減少しました。自分が住む地域で、寝るだけでなく働くことになり、地域で過ごす時間も大幅に増加しています。これまで分離していた、生活圏と生産圏が統合され、地域の生活圏に一本化されたわけです。コロナ禍をきっかけに、都心と郊外の関係が、大きく変わろうとしているのではないでしょうか。
そうしたときに、商業施設をコアとした新たなコンパクトシティのような地域像が思い浮かびます。商業施設がその地域の中心市街地のような役割を担い、働くことも含めた暮らしの多くがそこで営まれるようなイメージです。このように地域で暮らしを完結できれば、環境への負荷も軽減できます。こうした循環型の地域社会がどんどん増えていくことで、SDGsへの貢献にも繋がっていきます。
村井:商業施設にも社会課題の解決が求められる中、地域に加えて環境にも貢献していけたら理想的な展開ですね。本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
VOL1、2を通して、未来の商業施設の理想像を考えてきましたが、今後のひとつの方向性を示すことができたのではないでしょうか。では実際に、未来の商業施設はどのようなものになるべきか。生活者の未来の暮らしそのものを広く俯瞰した上で、より具体的に考えていく必要があります。次回より、未来の暮らしに関する、様々な識者の方へのインタビューを始めます。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待下さい。








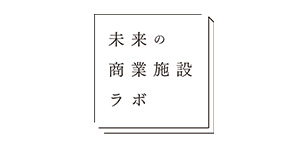







































村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー
2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。