
商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回は、当ラボメンバーによる、商業施設運営者へのインタビューをお届けします。ゲストは、グッドデザイン賞2020も受賞したPLAYatre TSUCHIURA(プレイアトレ土浦)の前店長・藤本沢子さんです。駅ビルでモノを売ることをやめ、日本最大級のサイクリングリゾートへとコンバージョンをはかった、その背景や想いとは。また地域に貢献する商業施設の在り方などについて伺いました。今回は、その前編です。
お客さまがいない・モノが売れない・テナントさんが出店してくれない、という三重苦
松本:2020年3月にグランドオープンし、グッドデザイン賞2020も受賞したPLAYatre TSUCHIURA(プレイアトレ土浦)ですが、サイクリングに特化しているという、これまでにないような駅ビルですね。
藤本:そうですね。延床面積は約1万7千㎡ですが、この広さがまるごとサイクリストのための施設ということで、世界でもあまり例が無いと思います。
サイクリングステーションやサイクルショップ、サイクルカフェなどサイクリストの拠点となる施設のほか、サイクリングホテル、レストランゾーンやマーケットゾーンで構成されています。
もちろんサイクリストだけではなく、観光の方、ビジネスの方、駅をご利用の方、地元の方々に便利に使っていただけるような施設になっていますが、特徴としては、サイクリングをテーマにしているので、モノを売るよりもコトを売る、体験を売る施設です。

B1・1Fの「BIKE BASE/りんりんスクエア土浦」(左上)は、サイクリスト向けのサービスが全て揃った国内最大級のサイクリング拠点。2・3Fの「STATION LOBBY」(右上)は、2フロア約400坪で展開するエリア最大級のレストランゾーン。2Fの「BOOK&TABLE」(左下)は、地元茨城のフードショップとブックストアを組み合わせた新感覚のマーケットゾーン。3・4・5Fの「CYCLING HOTEL」(右下)は”居酒屋以上、旅未満”。「ハマる輪泊」が合言葉のルーズなホテル「星野リゾート BEB5土浦」となっている。
松本:駅ビルでモノを売らずに、コトを売るというのは、なかなか無い発想ですね。なぜそのような考えに至ったのでしょうか。
藤本:端的に言ってしまうと、モノを売ることが限界を迎えていたということです。プレイアトレ土浦は、土浦駅ビルをコンバージョンして誕生しました。元の土浦駅ビルは1983年に開業したのですが、当時はバブル経済の波に乗っていましたし、土浦が郊外ベッドタウン、商業地として栄えていたので、地方の駅ビルとしては名門と言われるほどでした。しかしその後、モータリゼーションの進展、都心回帰、バブル崩壊という流れを受けて、駅前が衰退し、年々売上が落ちてしまったんです。運営者を変えたり、リニューアルをしたりなどをしましたが、なかなかうまくいきませんでした。
私は2015年にそうした土浦駅ビル再生のために着任したのですけれど、当時の土浦の駅前というのは、空ビルだらけで人よりも鳥の方が多いんじゃないかというような状況でした(笑)。
松本:人よりも鳥の方が多い状況ですか(笑)。そのようなマーケットにもかかわらず、撤退せずに継続されたのは、どのような理由があったのですか。
藤本:お客さまがいない・モノが売れない・テナントさんが出店してくれない、という三重苦の状態では、ショッピングセンターの運営自体が成り立たないんですね。その3つが無い中で、どうやって駅ビルを存続させていくのかということをまずは考えました。
やはり駅ビルというのは公共インフラとしての側面もありますし、地域社会との結びつきも強いので、安易に撤退はできません。さらに、土浦の駅ビルは駅舎と完全な一体型ということもあり、撤退も減築もできないという状態で、既存のビルを残したまま存続させなくてはいけないという高いハードルがありました。

「日本一のサイクリングロード」を足掛かりにした新たな試み
松本:プレイアトレ土浦は官民一体となった地方創生の新たな試みとお聞きしています。
藤本:はい。当時、土浦市でも駅前をなんとかしないといけないという想いがあって、中心市街地活性化事業を国と進めていたんですね。ただその内容はハード=ハコモノが中心でした。
土浦市がハードを中心に進めていくのであれば、駅ビルとしては、地域の付加価値を高めるなど、ソフト面で新しい価値を生み出すことができれば、相乗効果が生まれるのではないかという考えがありました。
松本:その中でも、サイクリングに特化した施設をつくろうとされたキッカケはなんだったのでしょうか。
藤本:当時、茨城県が旗を振って、サイクリングロードの整備事業の話を進めていました。既存の「霞ヶ浦自転車道」と「つくばりんりんロード」、この2つのサイクリングコースをまとめて1つに整備し、全長約180kmで日本最長、オールフラットで非常に走行環境も良く、筑波山や霞ヶ浦などの恵まれた自然環境もあり、完成すれば「日本一のサイクリングロード」になるというものでした。そこに着目して、行政を巻き込みながら駅ビルの再生プランをつくっていきました。
一般的な商業施設の場合、施設を維持するためには、毎年売上と収益を伸ばしていく必要が有り、人口や駅利用客の増加がその前提となります。当時の土浦駅前は、ゴーストタウン化が進んでおり、周辺・地域住民をターゲットとしたモノを売るビジネスモデルでは限界があるマーケットでしたので、消費を目的としない普遍的な集客施設を駅に設けることができたら、面白いことができるんじゃないかなと思ったのがキッカケです。そこでサイクリングに着目したんです。

つくば霞ヶ浦りんりんロードは、霞ヶ浦などの水郷地域や筑波山地域などの豊かな自然や風景、歴史的・文化的資産など、多様な地域資源を有する全長約180kmのサイクリングコース。茨城県と沿線の14市町村、企業、関係団体が一体となって、誰もが多様にサイクリングを楽しむことができる、日本一のサイクリングエリアの形成を目指している。
地域再生、価値創造を目指し、組織としてもチャレンジ
松本:非常によくわかりました。とはいえ、モノを売らない集客施設をつくるという決断はなかなか難しかったのではないでしょうか。
藤本:もう、逆転の発想だったんですね。モノが売れないのであれば、モノを売らなくていいじゃないと(笑)。
人が来ないのであれば地元の方をターゲットにするのではなくて、首都圏や全国から人が集まるような施設をつくればいい。
私たちがビジョンとして掲げているのは、地域再生と地域価値の創造という2点なんですね。そこを最終目標として、コト消費という新しいビジネスモデルだったり、地方創生型の駅ビルだったり、新しいビジネスモデルや次世代の駅ビルモデルが構築できれば良いと。そこで社会的な価値が生み出されていけば、結果的に売上はついてくると。なので、目先の売上は安易に追わないという覚悟を決めて臨んだコンバージョンでしたね。
松本:本当になかなかできない決断をされたのだと思います。それだけに、組織の中では、反対や疑問視するような声はありませんでしたか。
藤本:当時の社長に、サイクリングをテーマにしたモノを売らない駅ビルをつくりたいんだという話をしたときに、「駅ビルなのにモノを売らないというのはどういうことなんだ?!」とあきれられたということはありましたね(笑)。
ただ、一般的な駅ビルとして再生するのは難しいとわかっていたので、新しい自由な発想でのチャレンジが必要だったというのは大きかったと思います。そこで、一連のストーリーを説明して、このチャレンジに納得してもらったという感じです。
松本:そのときに設定された目標や指標などはありますか。
藤本:売上ではない指標、独自のKPIを設定していて、どれ程まちと駅に人を呼び込めたかというのは大切にしています。駅ビルを再生するには、まちを再生するというのが大前提ですので。
松本:施設のテーマやビジネスモデルももちろん新しいですが、そもそものビジョンやゴール設定もこれまでにないものを掲げられていますね。そのような決断はなかなかできるものではないと思いますが、これからの時代に非常に重要な考え方を教えていただいたように思います。
前編では、プレイアトレ土浦が開業した背景や想いなどについて、お話を伺いました。後編では、コロナ禍での動向や、地域との関係性、そして藤本さんの考えるこれからの商業施設の在り方についても伺います。








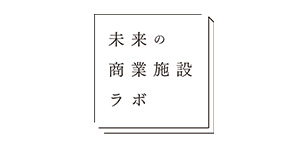





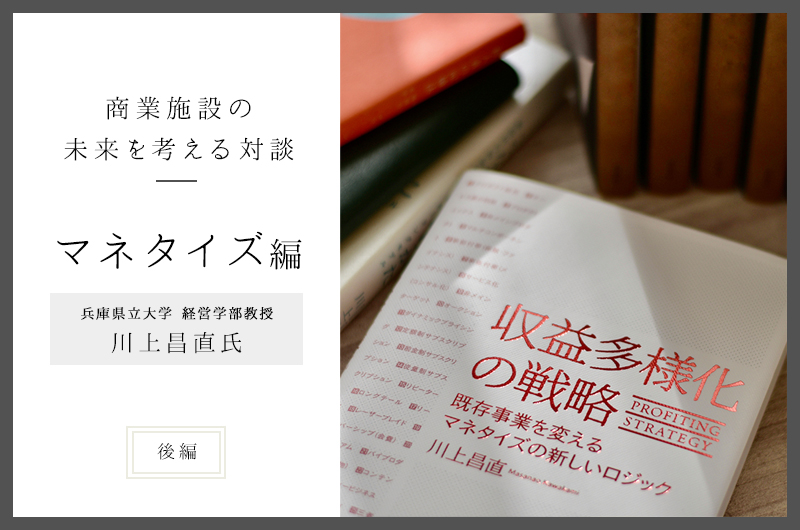



































村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー
2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。