
写真左から
株式会社PocketRD 代表取締役 プロデューサー 籾倉 宏哉 氏
JR東日本 国際事業本部ロサンゼルス事務所 Innovation Strategy Manager 森 伊織 氏
jekiデジタル本部 JR東日本グループ デジタル推進局 部長 藤原 久美子
jekiメディアマーケティングセンター センター長 直井 伸司
2024年1月にアメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級のテックイベント「CES®️ 2024」※1。コロナ収束後、本格的な再開を果たしたCESは、150か国以上から13.5万人を超える来場者を集め、最新技術や自社の描く未来を発出する場として賑わいを見せた。今回は、日本貿易振興機構(ジェトロ)が出展した「Japan(J-Startup)パビリオン」に参加したPocketRDの籾倉 宏哉氏と、現地で会場を視察したJR東日本ロサンゼルス事務所の森 伊織氏、jekiデジタル本部の藤原 久美子が、CESから見えたミライのテクノロジーのあり方について語った。
※1 CES®️は毎年1月に全米民生技術協会が主催し、ネバダ州ラスベガスで開催される電子機器の見本市。業界向けの見本市で一般には公開されていない。
・CES®️はConsumer Technology Associationの登録商標です
・CES® is a registered trademark of the Consumer Technology Association.
PocketRD、JR東日本、jekiが見たCES
直井:今回はCESの出展者として、あるいは訪問者として感じたことや、CESから見えた私たちの未来について語り合いたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。
籾倉:PocketRDの籾倉です。2017年に創業したアバターとブロックチェーンの企業です。もともとBtoCでのビジネス展開を意図して起業したのですが、JR東日本さんをはじめとするさまざまな企業を通じて、BtoBtoCでのサービスも提供していく予定です。

森:JR東日本のロサンゼルス(LA)事務所の森です。LA事務所の主なミッションは、訪日外国人旅行者拡大、新規シーズ・サービスの探索などです。将来的に米国での鉄道や公共交通事業とのシナジーを生み出せる事業も模索していますが、オープンイノベーションという大きなくくりのなかで、まずは当社グループの事業に資する「技術の芽」となるものを探しています。
藤原:jeki デジタル本部の藤原です。JR東日本グループのデジタル戦略やクリエイティブディレクションを担当しています。
存在感を発揮できていない日本企業、その背景は
直井:今回、籾倉さんは出展者としてCESに参加されましたが、感じたことはありましたか。

JETRO(日本貿易振興機構)が出展した「Japan(J-Startup)パビリオン」(写真提供:JETRO)
籾倉:大きく3つあります。まずは、日本企業が韓国企業に押され気味だったということです。CESの総出展社数は4,200社で、ベンチャー企業が集まるエリアには1,400社が出展しているのですが、そのうち600社が韓国でした。一方の日本はベンチャー企業が30社で、大企業を含めても60社です。ただこれは、日本は市場が大きく、海外進出が必須ではないという事情もあってのことです。韓国の人口は日本の半分くらいしかなく、市場テストをしてもすぐに飽和してしまうので、海外展開を前提に事業設計している企業も多いのです。「マーケティングで世界を対象に考えるか否か」という視点は発見でした。
2つ目は、日本企業のブースに日本人が集まりすぎているということです。海外でコミュニケーションを取ることに慣れていないのか、自国企業のブースで安堵の表情を浮かべる日本人を多く見かけました。
3つ目は、CESがもはや「家電見本市」ではなくなったということです。CESは、元は“Consumer Electronics Show”の略で、消費者向けエレクトロニクス製品の見本市だったわけですが、近年目立つのはAmazonやWalmartといった流通企業の台頭です。韓国のロッテはメタバースを大々的に押し出していたのが印象的でした。
森:「これが私たちの世界です」という将来像や世界観を描いた上で、「そのためにはこのサービスや製品が必要ですよね」と自社製品を展示したり、複数の企業でアライアンスやコンソーシアム組成を促す企業が多く見受けられました。当たり前すぎて忘れられがちですが、プラットフォーマーと呼ばれるAmazonやGoogleは、もともとそうした発信をしてきた企業です。自らの基盤の上にさまざまなコンテンツが乗ることでこそ真価が発揮されるので、その発展性と拡張性を打ち出す姿勢には学ぶべきことが多いと感じました。特に、基調講演に登壇したジーメンス(SIEMENS)は、「Industrial Metaverse(産業用メタバース)」という枠組みで、生成AIと共にデジタルとフィジカルの融合を掲げた基盤を構築し、自分たちの製品やパートナー企業と共に創り上げたい世界観を、大きなアライアンスという形でうまく示していたと感じました。

藤原:私は、ロレアルの基調講演に感動しました。化粧品をデジタルと組み合わせるという発想で、女性に限らずいつまでも美しくありたいと思う気持ちを、AIなどのテクノロジーによって実現しようとしている。そこには障がいのある方も含まれていて、DE&I ※2という点でも良かったです。
※2 DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)とは、Diversity(ダイバーシティ/多様性)・ Equity(エクイティ/公平性)・Inclusion(インクルージョン/包括性)の3つを合わせた言葉。
オープンイノベーションを推進するために求められることとは
籾倉:先ほど話に出たジーメンスは、今から約100年前に古河電気工業と合弁で会社を作り、それが私の古巣である富士通につながっていることからもわかるように、古くからオープンイノベーションに長けた会社です。今回のCESでは、ソニーが開発したXR HMDを活用し、XR環境下でデザインを制作するソフトウェアを紹介していました。そのソニーはホンダと自動車を開発して出展していますが、こうした姿勢は見習うべきでしょうね。JR東日本グループは、先進的なオープンイノベーションの事例も、社会的な取り組みもたくさんあるはずなのに、それをうまく発信できていないと感じます。
森:JR東日本では、モビリティ変革コンソーシアム(現・WaaS共創コンソーシアム)を中心に、CEATECなど国内の展示会で情報発信しています。一方、籾倉さんが仰る通り、CESのような世界中の異なる視点が集まる場で、自分たちの強みや、実現していきたい世界観を発信していくことで、新たなアライアンスの可能性を生み出したり、共感を得ることは、難しくも大事なことだと感じます。
「投資しないリスク」とどう向き合っていくのか
籾倉:アメリカでは、「投資しないリスク」という言葉をよく耳にします。何か芽を見つけたら、小さくても投資しておけば、花開き返ってくる可能性もある。投資しないのはむしろリスクなのではないか、という考え方です。日本だと、成功するかわからないものに投資することに否定的な雰囲気がありますが、別の視点を持つことも大事です。
財務諸表だけでなく、事業内容やそこで働く人たちなど、別の側面からも検討する。走りながらイノベーションに挑戦するのか、それとも失敗しないよう万難を排してからイノベーションに取り組むのかの違いでもありますが、JR東日本グループは次の段階へ進みつつあるのではないかと感じています。

森:海外生活が長いからこそ、共感する部分が多いです。失敗無しですべてを進めることはほぼ不可能です。大事なのは、失敗した理由を分析し、判断に至るまでのプロセスのどこで間違えたのかを把握し、分岐点まで戻ってスピードをもってやり直すという思考法に慣れることです。今は技術により思考プロセスが可視化しやすくなったので、多くの事例を共有・活用し、周囲が状況を理解できる環境を整えることで、リスクに対する意識も変わってくるのではないでしょうか。
籾倉:韓国の人に「失敗したらどうするんですか」と聞くと「成功するまでやります。やめなければ失敗じゃない」と言っていましたが、日本でも、事業の本質とリスクについて考え直す必要があると思います。
今、Web3.0の技術は、一部の投機家によりマネーゲーム的な使われ方をされることがあります。ただ、本質的にはそうではなくて、DID/VC※3をはじめ、自らが持つ能力や実績を証明するための技術であり、新しいビジネスを生み出せる手段です。目的意識を持ってビジネスを構築すれば、おのずと突破口は見えてくるはずです。
たとえば現在、メタバースプロジェクトが乱立していますが、十分なマーケティングもせず、持続可能性のない形で実現するケースが多いと感じます。結果、「過疎バース」となり、サービスを中止する例も散見されますが、成功するまで止めないことは大事だと思うし、地道に継続して取り組むことは日本人の得意とするところだと思うのです。
※3 Decentralized Identifier(DID/分散型ID)、Verifiable Credential(VC/検証可能なデジタル証明書)のこと。

PocketRD の出展ブース(写真提供:PocketRD)
森:JR東日本では以前より『「安全」の先にある「安心」をめざして』を謳っていました。入社直前の私の心に残った好きな言葉なのですが、英語では「安心」を直接的に表現できる単語がない。安心という言葉自体がやわらかい響きを持っていて、こういうところに日本の良さが表現されていて、それを支えているのは「信頼性」や「クオリティ」だと考えています。
たとえば、日本の鉄道は時間に正確だと世界中で評価されていますが、質の高いレベルのサービスを確実に遂行できる現場力の強さが売りだと思います。
最近、当社の建設工事部門が、自分たちの仕事をYouTubeで発信しているのですが、それが「土木広報大賞2023」の優秀部門賞を受賞しました。我々には気づかなかった「外部の目から見た魅力」を発信材料として、また事業共創に向けた新しい商材として再構築・再編集することが、今後のオープンイノベーションにつながっていくのではないでしょうか。

直井:CESを軸にいろいろお話をうかがってきましたが、最後にこれからの意気込みをいただけますか。
藤原:XRやメタバース、AIなどのテクノロジーを交通インフラと組み合わせることで、jekiとしてどのような価値を提供できるのか。事業領域としてはそこにデータマーケティングも加わってくるので、どんどんチャレンジしていきたいと思いました。
森:私は、JR東日本グループそのものがオープンイノベーション的な要素もあると思っています。当社グループはjekiをはじめ、各事業領域の専門性に特化した会社が90社以上ある。そこに社外の皆さんと世界観を共有し、外部の知見を付加していただくことで、自分たちだけでは創り上げることができないサービスや事業を「共創」し、国内のみならず海外のお客さまと社会に提供し続けることができるのではと感じました。
籾倉:IT系企業が集まっている渋谷が「日本のシリコンバレー」と言われるように、ベンチャー企業の多い恵比寿もビットバレー的に語られる場所ではあるので、jekiがJRグループの垣根を取り払い、自由にいろんな人が集まる場所を作るのもいいかもしれません。そもそも私がここに参加しているのもオープンイノベーションですし、この輪をもっと広げていきたいですね。
直井:皆さん今日はありがとうございました。

直井 伸司
jekiメディアマーケティングセンター センター長 兼 XR&データビジネス事業推進準備室 室長
1992年jeki入社。約17年間、人事部門にて、採用、教育、評価、制度など人事全般を担当。その後、JR局にて、「JR SKISKI」や「大人の休日俱楽部」のキャンペーンなどJR東日本関連の案件を、第一営業局にてJR東日本グループの商業施設を担当した後、2019年7月、メディアマーケティングセンターのセンター長、2023年4月、XR&データビジネス事業推進準備室の室長となり、現在に至る。

藤原 久美子
jeki デジタル本部 JR東日本グループデジタル推進局 部長
2023年jeki入社。プロモーション、デジタルマーケティングなど幅広い経験を元に、前職では幅広いクライアントのブランド戦略をはじめとしたクリエイティブディレクションに従事。多様な領域を掛け合わせる越境性を重視したブランド戦略やイノベーション創出、コンサルティングを行う。
現職では幅広い実績・経験を活かし、JRE MALLをはじめとしたデジタル領域でのブランドプロモーション・クリエイティブディレクション等を手がけている。

籾倉 宏哉
株式会社PocketRD 代表取締役 プロデューサー
同志社大学心理学部卒業後、富士通、リクルートにて事業企画・マーケティング・広告宣伝領域を歴任。経済産業省 起業家創造事業ドリームゲートCOOを経て2007年にネクスゲート社(現リトライブ社)を創業し独立。
来るブロックチェーンとアバター市場の到来を感じ2017年にPocket RD社をスピンアウト創業。2023年度決算で単年度黒字化を実現。創業来日本を代表する企業との資本、業務提携をはじめ、幅広くアライアンスを展開。最新鋭のアバター技術とブロックチェーンビジネスの構築力で、世界中のコミュニケーションとエンターテインメントの未来を切拓く。
ベンチャー/IT/広告業界に精通し、幅広い人脈を生かしたマーケティング力が強み。複数の企業を創業した実績をもつシリアルアントレプレナーでもあり、ネクスゲート時代には、ARI株式会社(投資、経営支援)、グリッジ株式会社(アーティスト支援)、NaS株式会社(人材紹介)、ネクストイノベーション株式会社(マーケティングコンサルティング)などを世に送り出している。

森 伊織
JR東日本 国際事業本部ロサンゼルス事務所 Innovation Strategy Manager
2007年JR東日本入社。高崎支社での車両メンテナンス現場業務を経て2012年より海外大学院留学。2014年に帰国後、技術企画部(現・イノベーション戦略本部)にて技術戦略策定や、モビリティ変革コンソーシアム(現・WaaS共創コンソーシアム)設立・運営に従事。
2019年より英国・ウェストミッドランズ鉄道に派遣。改善マネージャーとして、現地車両工場の現場業務改善をリード。2021年帰国後、2022年より現職。同年よりカリフォルニア州立大学イーストベイ校講師。
専門領域は人間工学およびバイオメカニクス、趣味はクラシック音楽全般。











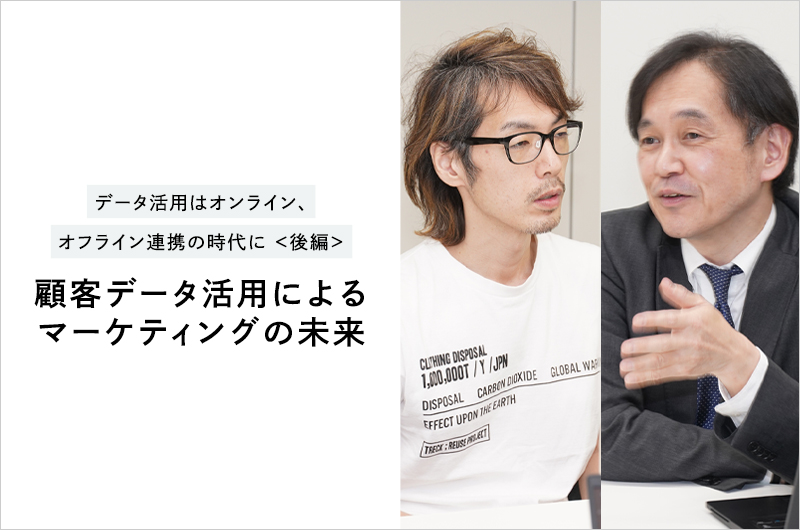
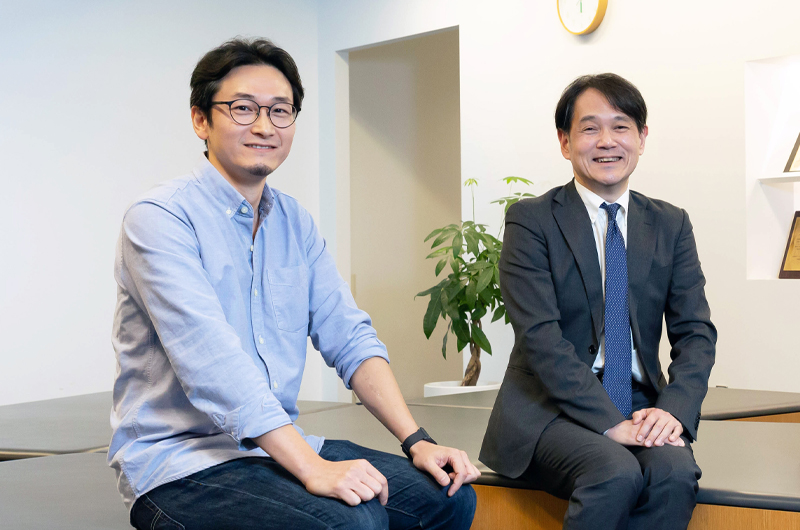





















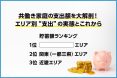












直井 伸司 jekiメディアマーケティングセンター センター長 兼 XR&データビジネス事業推進準備室 室長
1992年jeki入社。約17年間、人事部門にて、採用、教育、評価、制度など人事全般を担当。その後、JR局にて、「JR SKISKI」や「大人の休日俱楽部」のキャンペーンなどJR東日本関連の案件を、第一営業局にてJR東日本グループの商業施設を担当した後、2019年7月、メディアマーケティングセンターのセンター長、2023年4月、XR&データビジネス事業推進準備室の室長となり、現在に至る。