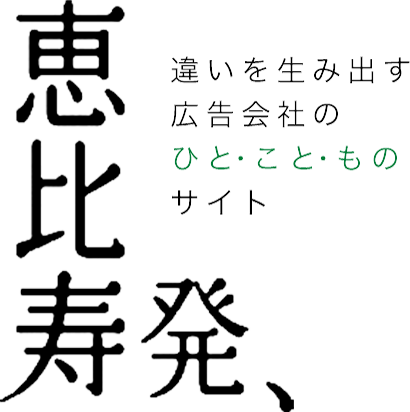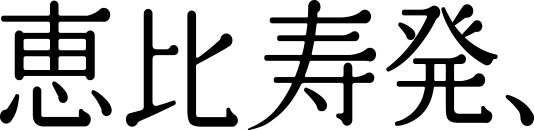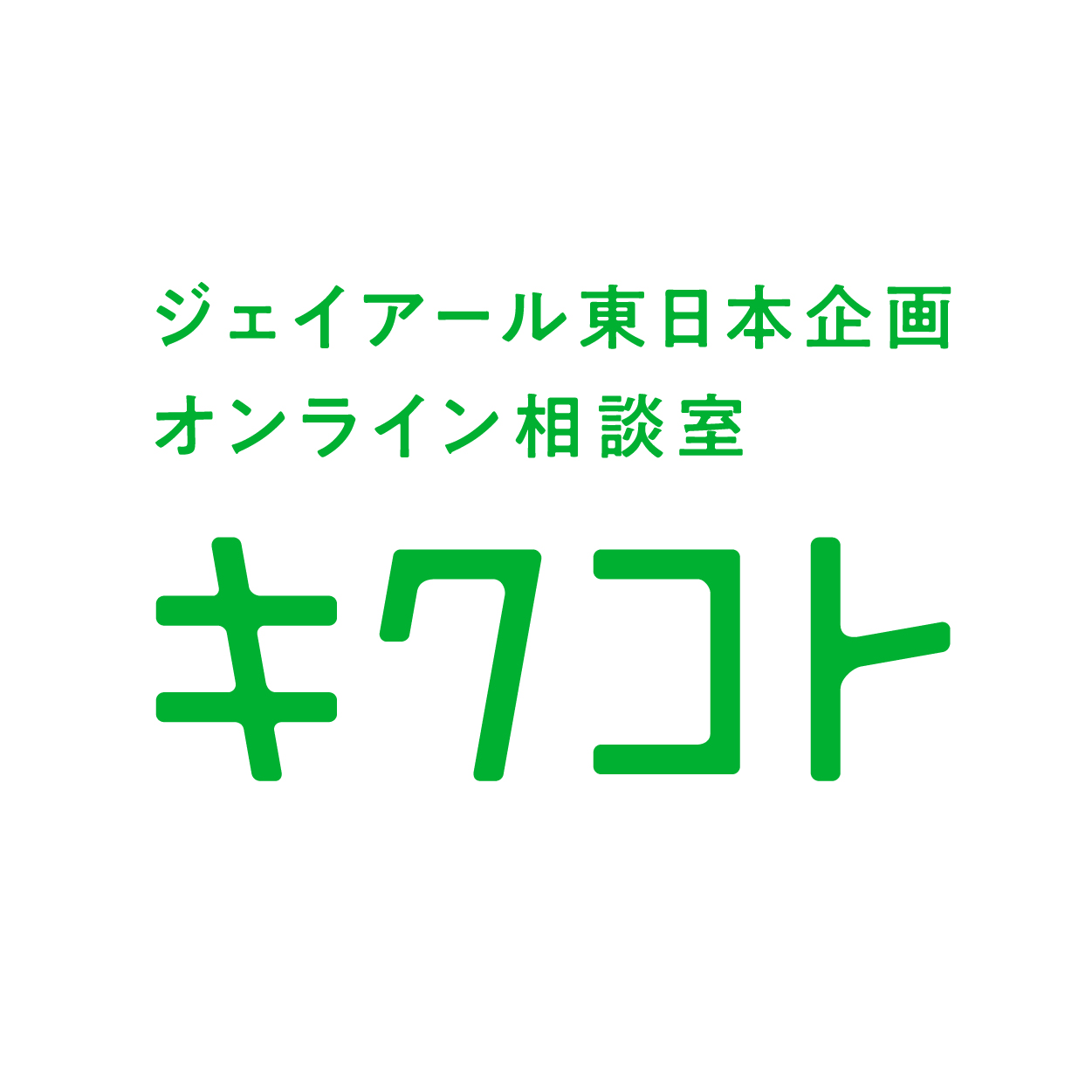(写真右より)
東宝株式会社 映像本部 映画企画部 映画企画室長 プロデューサー 山田 兼司 氏
jekiコンテンツビジネス局 コンテンツ第二部 部長代理 船越 拓
jekiコンテンツビジネス局 コンテンツ第二部 川鈴木 伊吹
9月に公開を迎える映画『百花』。菅田将暉さん、原田美枝子さんのダブルキャストをはじめとする豪華出演陣に加え、原作者である川村元気さんが自ら監督・脚本を手がけ、初の長編監督デビューを果たすことでも大きな話題となっています。今回は、本作品のプロデューサーである東宝株式会社の山田兼司氏と、製作委員会メンバーとしてタイアップ企画などを担当するjekiコンテンツビジネス局の船越拓、川鈴木伊吹が、製作の裏側や作品の見所を語り合いました。
個人的な経験を普遍的な物語として紡ぎ、映像化する
船越:『百花』は、監督である川村元気さんの個人的な経験をもとにした小説が原作になっています。映画化のきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

山田:川村さんとは同じ79年生まれで年も近く、私がテレビ朝日の映画プロデューサーだった頃に一緒に企画を開発したこともあり、旧知の間柄でした。ある時「実はこんな小説を書いていて、映画化するなら自分で監督をしたい」と相談されたんです。ただ、川村さんの実体験が反映された物語だというし、初の長編監督作品だし・・・最初は躊躇したんです。でも、ゲラを読ませてもらったら、個人的に共鳴することが多くて、シンプルに感動したんですよね。誰もが心打たれる普遍的なテーマで、静謐で素敵な物語だと思いました。

川村 元気
1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』などの映画を製作。2011年、優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。2012年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表し、同作は21ヶ国で出版された。2018年、初監督作品『どちらを』がカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に出品される。他著に小説『億男』『四月になれば彼女は』『百花』『神曲』、対話集『仕事。』『理系。』、翻訳を手がけた『ぼく モグラ キツネ 馬』など。
※写真/山野一真
船越:作品としての魅力を感じたということですね。映画化にあたり、どのようなアプローチを取られたのでしょうか。
山田:映画の企画としては、今回は特殊な始まり方だったかもしれません。通常は、興行としてのサイズ感やマーケティングからビジネスの“ガワ”として勝算を検証するところから手掛けることが多い気がします。でも、彼も百戦錬磨のプロデューサーであり、お互い〝分かっているもの同士”ということで、そういう話がメインではなかった。それよりも、作家としての川村さんが自身の経験を掘り下げて普遍的な物語とした小説があり、それを監督としての川村さんが映画として世の中に届けたいという。それをどうしたら実現できるかという、すごく純粋な思いから企画がスタートしました。幸い私もドラマ製作でいろいろな作家の方と伴走しながらオリジナルで物語を作る機会が多かったので、その経験が活きました。
川鈴木:川村さんと山田さんの信頼関係があったからこそですね。その後は、どのように作品づくりを進めていったのでしょうか。
山田:脚本家であり監督でもある平瀬謙太朗さんが初期から加わり、3人で頭を突き合わせていろいろな話をしてきました。小説と映画が似て非なるものということは、川村さんが一番わかっていて、作家の頭、監督の頭を自由に切り替えられる。「これじゃ映画にならないから」と結構ドラスティックに場面を切ったり、改変したりすることに躊躇がない(笑)。一方、平瀬さんは緻密な方で、整合性を取りながら丁寧に紡いでいくという印象でした。原作と見比べていただければ、映画ならではの設定や表現、その理由がわかると思います。
最高のクリエイティブを生み出す「チームビルディング」と「空気の醸成」
船越:川村さんの実体験がもとになった小説を映画という形にしていくには、とても繊細な作業が伴ったのではと思います。

山田:脚本や構成はもちろんのこと、「映像として映えるシーンはどうするか」、「記憶と音楽をどう組み合わせるか」といった映画ならではの細かい表現まで、コンセプトに忠実に模索した感じですね。スタッフやキャストといった才能をどうやって集め、どう配置するかも非常に重要でした。川村さんは試行錯誤することを躊躇わないし、どんどんチームに人が入って、加わった人の意見も取り入れて、最後には監督としてジャッジしていく。そして、撮り終わった後も、普通、初監督なら気負って足し算したくなるはずなのに、ばっさりカットするなど、恐ろしいくらい潔かったです。欲張らずに絞り込んだ結果、作品がすごく締まったし、完成度が高まったと思います。
川鈴木:『百花』は、菅田将暉さんと原田美枝子さんの共演でも話題となっています。キャストもそのようなアプローチで決めていかれたのですか。
山田:この人に演じてもらいたいという候補を出していきましたが、比較的早い段階から満場一致で「理想のキャスト」が出てきて、それが実現したというところですね。

船越:記憶を失っていく母と、その母を献身的に支えながらも、過去の出来事から心にわだかまりがある息子。そんな難しい役で、繊細で説得力があるお芝居ができる方はそういないというのもあって、主演がこの二人というのは納得感がありました。
山田:菅田さんとは、川村さんも仕事をしているし、私も自分の企画制作した連続ドラマで主演を演じてもらい戦友みたいになっていて、彼の凄みは誰よりも理解しているつもりでした。繊細な感情表現から、一瞬で場をさらっていく瞬発力は、この世代では群を抜いていると思います。ただ、この物語にどのくらい興味を持って、演じたいと思ってもらえるかが重要だったので、川村さんから直接本を渡して読んでもらい、共鳴して引き受けていただけたのは、理想的な決まり方だったと思っています。
原田さんの場合は、認知症になられたお母様についてドキュメンタリー映画を撮っていらして、それを拝見したのも非常に大きなことでした。大女優であり、キャストとして最もふさわしいと思われる方であるのは間違いないのですが、プライベートでのご経験において重なる部分があり、それもあってお引き受けいただけたのは運命的なものを感じました。そう、この仕事では、時々「この人と物語を作るのが必然ではないか」と感じるような出会いが度々あるんです。
川鈴木:佇まいも自然で、まるで〝アテガキ※“のようでした。
※演じる俳優をあらかじめイメージしたうえで書かれた脚本
山田:お芝居の直前まで脚本を書き直し続けていましたし、セリフも二人のイメージによってニュアンスを変えたりしたので、確かにアテガキに近かったかもしれませんね。
船越:こうして伺っていると、チームの雰囲気は抜群という感じが伝わってきますが、プロデューサーとして意識されていたことはありますか。
山田:最初に川村さんと握ったことは「ベストなチームをつくろう」ということです。カメラマンも、スタイリストも、最も信頼できて、この作品に合っている方にお願いしようと。そこにかなりの手間とエネルギーと情熱を注ぎ込みました。チームビルディングがかなった時点で、大部分は成功に近づいたと言えるかもしれません。その上で、いい作品を一緒に作り上げようという空気感を醸成することが大切ですね。具体的には、コミュニケーションに誤解を生じさせない、自由に発言して健全な試行錯誤ができるようにするなどでしょうか。
物語の裏側にある〝見えない思いや気持ち”を伝えたい
船越:山田さんは作品に共鳴しながら、原作者・監督である川村さんを、映画プロデューサーとして支えられたわけですが、もとはテレビ局で多くのドラマの製作に携われてこられました。映画プロデューサーになられたのは何かきっかけがあったのですか。

山田:実はテレビ局にはドキュメンタリーや報道の仕事がしたくて入社したんです。3年間ほどディレクターとして報道に携わっていたのですが、ある時から、私が伝えたいこと、表現したいことは、フィクションの方が向いているのではないかと感じるようになりました。たとえば、ある事件を取材しても”事実”しか報道できず、「なぜ起きたのか」という本質的なことは置き去りにされがちです。でもフィクションなら事実の裏側にある、理由や思いなどまで深掘りして描くことができる。
私自身も映画やドラマに心を動かされ、影響を受けてきたことを思い出し、映画・ドラマ部門に異動希望を出しました。そして、10年以上ドラマのプロデューサーとして様々な作品に関わるうち、映画は予算も規模も最大のエンターテインメントであり、人間を深く描ける方法として目指すべき最高峰だと思っていたところに、東宝に声をかけていただいた感じです。

川鈴木:川村さんを引き寄せたのも、山田さんの情熱による引力かもしれませんね。
山田:川村さんこそが〝狂った情熱の持ち主”だと思います。いや、違う次元までいっているというべきでしょうか(笑)。プロデューサーとして誰も真似ができない個性を発揮して、すばらしい成果も出しているし、小説も脚本も手掛ける。そんな彼がいよいよ初長編監督作品というところで、私がプロデュースすることになり、巻き込まれたのか巻き込んだのか、改めてそういう星の下にあるのかもと感じはしました。
記憶を失っていく母から息子が受け継ぐ「愛と赦し」
船越:改めて作品について聞かせてください。『百花』のテーマや最も描きたかったことなどを、川村監督とどのように共有されたのでしょうか。
山田:「記憶」がテーマであり、記憶を失っていく母親がいて、その母と向き合うことで思い出を蘇らせていく息子がいて、その行き違いが状況的には切ないわけですが、決してネガティブなことばかりではない。記憶を失っていく中でこそ、かけがえのない人との関係においては、一つの和解がありうるし、記憶を失うことで人生の美しさに気づくこともあるのではないかと思うんですね。観ていただければ、しみじみと親子や家族の関係を振り返る気持ちになると思います。
船越:親が老いていくということに切ないものを感じました。いろんなことを忘れて、最後には自分のこともわからなくなるのではないかという不安。まだ経験してはいないのですが…。
山田:確かに映画の中では母親はどんどん息子のことを忘れ、それと反比例して息子の方は母親のことをどんどん思い出していく。そのことに対して菅田さん演じる息子が苛立つ様子には、胸を打たれますよね。そしてある日、忘れていた大切なことを思い出す息子がいて、その思い出にこだわり続けていた母親は何もかも忘れてしまっていて…。その時、母親の記憶が息子へと手渡され、きっと母親が亡くなったあとも、その記憶は大切な思い出となって、息子の中で何度も色鮮やかに再現されるのだろうと想像できます。
ただ、親子って血がつながっているからこそ、関係がこじれてしまうと後々までしこりが残る。いざ和解するといっても、最後まで納得できない部分もあると思うんです。だから、神戸編と言われる映画内のあるパートをどう描くかは、すごい議論を重ねて作っていきました。親子の記憶にとって非常に繊細な内容でもありましたので。
船越:水に流すとかではなく、その苦い記憶も内包しつつ、すべてを受け入れるというか。そんな感じなのかもしれませんね。
山田:そう、人間は不完全なものだと理解していても、親の汚い部分や弱い部分を知りたくないというのも事実。でも、そんな部分も含めてあるがままに受け入れる。それが「大人になる」ということなのかもしれません。この親子の間に佇む妻である長澤まさみさんのお芝居がまたすばらしくて…そのあたりもぜひ、映画館でご覧いただければと思います。
映画の世界観をそのままに、タイアップCMも展開
船越:映画公開に向け、製作委員会メンバーも『百花』ならぬ「100の広報・宣伝企画」を考えています。活発に意見を出し合い、さらに川村さんが委員会に参加されることもあって大いに士気が上がっています。
山田:メンバーの皆さんがいろんなメニューを出してくださいましたが、特にタイアップCMは映画の作品性と企業の理念やコンセプトによる相乗効果で、より強くメッセージを感じ取っていただけるのではと思います。
川鈴木:jekiが提案させていただいた、太陽生命さんとのタイアップCMですね。認知症予防保険の訴求として「愛する人を守るために」というメッセージも、気持ちに寄り添うものになっています。
今回お話をうかがって、あらためて同世代の方にも劇場で観てほしいと感じました。ストーリーや、キャストさんの演技、映像の美しさなど・・・心惹かれるポイントはそれぞれかと思いますが、観れば、必ず家族に連絡したくなると思います。

船越:若い方ももちろんですが、ぜひ多くの方に映画館に足を運んでいただきたいですね。
山田:はい、すごく感動できる愛の物語だと思います。音楽も映像も丁寧にこだわり、映画館だからこそ最大限に味わえるものを目指して作りましたので、ぜひ足を運んでいただきたいですね。
船越:はい、jekiとしても盛り上げていきたいと思っております。本日は、ありがとうございました。
<了>

山田 兼司
東宝株式会社 映画企画部映画企画室長・プロデューサー
ドラマ「BORDER」(2014)「dele」(2018)などを手掛け、東京ドラマアワード優秀賞、ギャラクシー賞テレビ部門優秀賞などを受賞。
2019年より東宝に所属。主な映画作品は「相棒-劇場版Ⅱ」(2010)「岳」(2011)「百花」(2022)などがあり、現在は複数の映画作品をプロデュースしている。

船越 拓
コンテンツビジネス局 コンテンツプロデューサー
2004年jeki入社。営業局にてJR、およびJRグループのファッションビルを担当し、2017年より現職。コンテンツビジネス局に配属後、多くの映画やアニメ製作委員会に事業参画。

川鈴木 伊吹
コンテンツビジネス局 コンテンツプロデューサー
2020年入社。コンテンツビジネス局に配属後、映画・アニメへの事業参画・宣伝等に従事。コンテンツタイアップのサポート業務も取り組んでいる。