

ゲキダンイイノ合同会社
座長 嶋田 悠介さん
1983年生まれ。2009年、関西電力株式会社に新卒で入社。経営企画室で中期経営計画策定などに従事した後、若手を中心にした社内の新規事業創設部門を立ち上げ、自身も2016年から専属となる。2020年2月、ゲキダンイイノ合同会社設立。2020年10月、時速5kmの自動走行モビリティ「iino」のサービスを開始。
モビリティの製造・販売ではなく、移動体験全体をプロデュース
2022年2月には、神戸市や関西電力と共に神戸市三宮でtype-S712を使った実証実験を行ったそうですね。どのようなことを行ったのですか。
嶋田:街の回遊性向上や賑わいの創出に向けて、歩行者と共存できる新たなモビリティ活用を目指すという実験です。iinoの試乗体験はもちろんですが、iinoを含め電動キックボードなどの乗降場であり休憩もできる拠点として、「モビリティスポット」の設置も行いました。
これまで、こういった交通の結節点となる拠点は、たくさんの機能が統合された大きな拠点を目指すことが多かったと思います。しかしこの実験のモビリティスポットでは、いろいろな所を回遊してもらうため、機能を統合するのではなく、場所に応じて機能やデザインを分散させました。
さらに、単なるモビリティの提供ではなく、どの場所にモビリティスポットを置き、どんな移動体験をしてもらうかまでを考えました。iinoだけでなく他のマイクロモビリティも含めてどんな種類のモビリティを何台置いたらいいのか、どこで休んでもらうかなど、移動体験全体をプロデュースしたのです。
移動体験のプロデュースとは、例えばどのようなことですか。
嶋田:駅前のスポットには、たくさんの種類のモビリティを置きました。駅を降りてまずはどのモビリティにするか、街歩きの“相方”を選ぶという意味で、このスポットは「buddy(バディ)」と名付けました。
港まで600mという場所に設置したスポットでは、コーヒーを飲めるようなスタンドをつくって一息入れてもらえるようにしました。ここからは海へ向かいたい気持ちが高まってくると思うので、iinoのような速度の遅い乗り物から、少しスピード感のある電動キックボードに乗り換えてもらうような形にしました。このスポットのネーミングは、心のスイッチを入れるという意味で、開始の合図である「cue(キュー)」としました。そんなふうに、エリアに応じて移動体験を設計し、モビリティスポットも機能やデザインを変えていきます。

神戸三宮での実証実験風景。写真左のモビリティスポットは、駅前に設置されさまざまなモビリティに乗り換えることができる「buddy」。写真右は、iinoを含めたモビリティの乗降場であり、休憩や情報発信の機能も備える「cue」。
移動体験のプロデュースは、ゲキダンイイノという会社のビジネスの一つになっているのでしょうか。どのようなビジネスモデルですか。
嶋田:iinoの開発は行っていますが、メーカーとしてモビリティを大量に製造・販売するということはしません。神戸市のような自治体や、デベロッパー、大型商業施設の運営事業者などから、ウォーカブルシティの構築やエリアの賑わい活性、駅前開発といった依頼を受け、コンセプトづくりから参加して移動体験をプロデュースします。
コンセプトに基づいてそのエリアをどのように回遊させるべきかを考え、モビリティやスポットを配置し、最終的にiinoやその他のモビリティも含めてゲキダンイイノが運用していきます。その運用サービスフィーを自治体や事業者から支払ってもらうというのが、僕らの考えるビジネスモデルです。
モビリティの利用者がお金を払うのではなく、自治体や事業者がお金を払ってモビリティを走らせるということですか。
嶋田:移動に対する“運賃”という形で、利用者からお金をいただきたくはありません。運賃を支払った瞬間に、利用者はバスやタクシーと比較し始めて、「行きたい所になかなか着かない」とか、「変なルートを通る」など、不満が出てしまう可能性があるからです。
提供したいのはあくまでも、既存の移動とは違った、より良い移動体験です。ですから、場合によっては別の形で料金をいただくことは考えています。例えば、モビリティに乗っているときにしか楽しめないコンテンツを提供し、そのサービスに対する利用料をいただくなどです。
個性あるまちづくりが移動体験を豊かにする
移動体験をプロデュースするというのは、とても新しい発想ですね。街の回遊性を高め、賑わいを創出するという課題解決につなげるために重要なことは何ですか。
嶋田:単にそこを通っただけでは、賑わいは生まれません。重要なのは、走らせる場所そのものの魅力です。立ち寄りたくなる要素が必要ですから、街との連携は欠かせません。街と協議し、どのようなコンテンツをつくるか、いかに魅力を引き立てるかなどを考えていきたいと思います。場合によっては、街や施設の開発・設計の段階で計画する必要も出てきますから、できるだけ上流から関わることを目指しています。
移動体験をプロデュースする上で、iinoのようなモビリティにとって相性の良い街はどのような街ですか。
嶋田:都市の在り方などを論じたアメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブズが提唱した、都市の多様性を生み出す条件(※)が当てはまると思っています。一街区が短くて街路や角を頻繁に曲がるたびに景色に変化があるとか、新旧の建物が織り混ざっているなど、雑多で、いろいろな人がいて、人の営みがにじみ出ているような場所は、何度通っても少しずつ景色が変わるので面白く、iinoとはとても相性が良い。
逆に、一街区が長くて車中心につくられている街や、住宅街のように住むことに機能が特化された街はあまり向いていません。雑多な街の方が良いですね。
※ジェイン・ジェイコブズが提唱した、都市の多様性を生み出す条件……アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブズが1961年に刊行した『アメリカ大都市の死と生』の中で論じたもの。ジェイコブズは、都市の多様性を生み出す条件として、複数の機能があること、街区が短いこと、古さや条件の異なる建物が混在していることなどを挙げた。
やはり、街の魅力が移動体験の豊かさに反映されるということですね。
嶋田:僕らが最もやりたいのは、移動するときに今まで見過ごしていたものを改めて認識することで、いかにその場所を楽しむかです。ですから、街やストリートによって、ここはできるだけゆっくり走らせたいなど、走らせ方も変えたい。街によっては、モビリティのデザインさえもちょっとずつ変えたい。エリアの特性を生かした走り方、ものづくりができたらいいと思っています。
まさに、移動体験のオーダーメイドと言えますね。そのような観点から、駅や鉄道に対して期待することは何ですか。
嶋田:駅を含めた街の開発では、できるだけ高層の建物を建てたいなど、より収益性を高めたいという考えに引っ張られがちだと思いますが、収益性だけでなく移動体験に重きを置いた、コンセプトを尖らせた楽しめるまちづくりに期待しています。その際、「モビリティは最後に付加する要素」としてしまうと、街のコンセプトに合わなくなる可能性があります。だからぜひとも、計画時から、移動体験に重きを置いたまちづくりを検討してほしいと思います。
取材・文 初瀬川ひろみ
写真提供 ゲキダンイイノ合同会社
〈完〉
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.52掲載ののためのインタビュー内容を基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年6月)のものです。








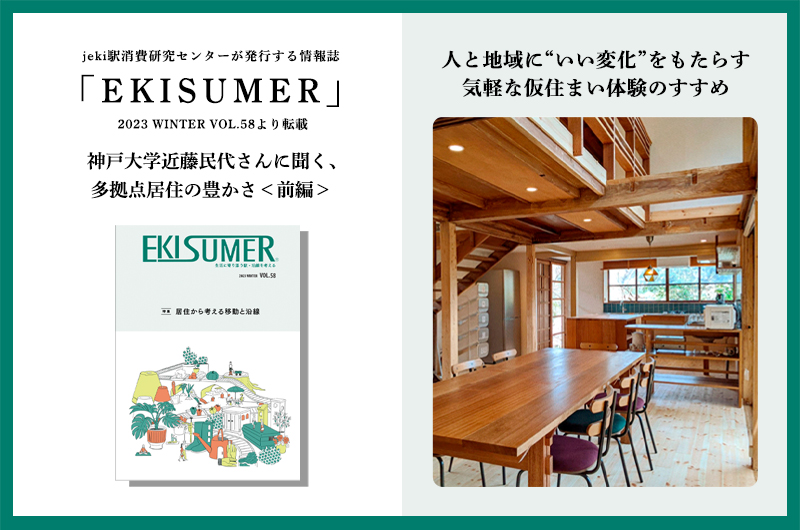

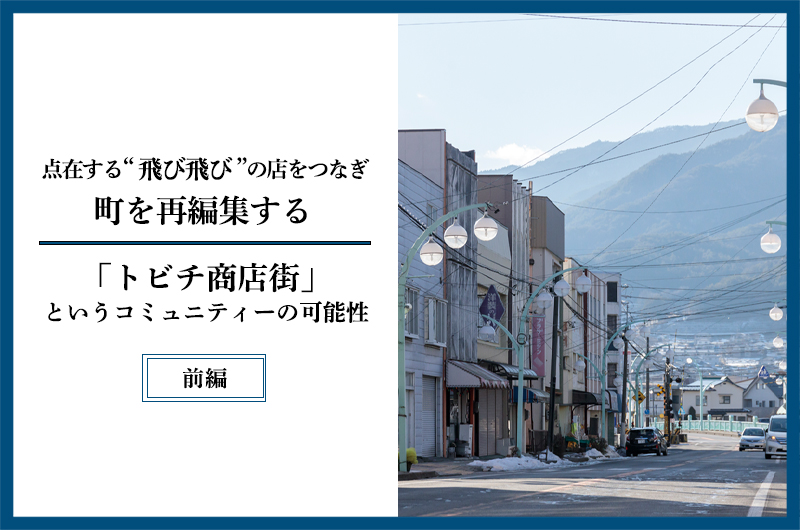

































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。