
近年、人口減少や厳しい財政状況、公共施設等の老朽化など、顕在化するさまざまな課題に、民間と協働して挑戦する自治体が増えています。公民が連携したからこそ、新たな地域活性につながるような取り組みが出始めている今、地域と共にある鉄道会社も、そうした事例から学ぶことは多いのではないでしょうか。建築設計を基軸としながら、リノベーション、公共空間の再生、地方都市の再生などを横断的に行うOpen A代表取締役の馬場正尊さんに、公民連携の可能性についてお話を聞きました。今回はその前編です。
※jeki駅消費研究センター発行「EKISUMER」はこちら

馬場 正尊(ばば・まさたか)
1968年佐賀県生まれ。Open A代表取締役、建築家、東北芸術工科大学教授。早稲田大学大学院建築学科修了後、博報堂入社。2003年、Open Aを設立。建築設計、都市計画まで幅広く手掛け、WEBサイト「東京R不動産」「公共R不動産」を共同運営する。近作に「佐賀城内エリアリノベーション」「泊まれる公園 INN THE PARK」など。近著に、『エリアリノベーション 変化の構造とローカライズ』『CREATIVE LOCAL エリアリノベーション海外編』(編著)、『公共R不動産のプロジェクトスタディ 公民連携のしくみとデザイン』『テンポラリーアーキテクチャー 仮設建築と社会実験』(共著)、(いずれも学芸出版社)など。
あまり使われていない公共空間を活用してもらうメディアづくり
建築設計を基軸にさまざまな活動をされていますが、中でも、全国の公共空間の情報を紹介しているWEBメディア「公共R不動産」について教えていただけますか。
馬場:公共R不動産は、低利用・未利用の公共空間を、民間企業や市民に使ってもらうためのマッチングサイトのようなものです。例えば、廃校やあまり使われていない公園、音楽ホールなどの情報を全国から集め、それを民間に利用してもらったり、公民連携で活用したりするような機会を増やそうと、2015年に開設しました。
それ以前から、東京の面白い物件を集めて新しい使い手を探す、不動産仲介のWEBサイト「東京R不動産」を運営していました。古い建物も一風変わった建物も、見方によっては、ユニークなこだわりのある建物だったりします。誰もが好むわけではないけれど、そういう隠れた魅力のある物件を欲している人もいる。それをつなぐ、新しいタイプの不動産メディアです。東京R不動産を運営していく中で、次に扱うべきは公共空間なのではないかという気づきがあり、それが公共R不動産へとつながりました。
公共空間を扱おうと思われたのには、何かきっかけがあったのでしょうか。
馬場:きっかけは幾つかあるのですが、一つはニューヨークで見た「ブライアント・パーク」(※)の風景です。オフィス街に囲まれたミッドタウンの真ん中にある公園には、芝生に寝転んでいる人もいれば仕事をしている人もいました。随分前だったのですが、園内で無線LANも使えて、とにかく多様な形で利用されていました。日本の公園では見たことがない風景でした。
※ブライアント・パーク……ニューヨーク市の中心部にある市立公園。1970年代には荒廃していたが、80年代から公民連携による再生のための取り組みが始まり、92年の大規模な改修を経て、市民や観光客に愛される憩いの場となった。芝生広場では無料Wi-Fi、可動式の椅子・テーブルが利用できるほか、ヨガや映画上映といったさまざまなイベントが行われている。
同じころ、池袋を中心に行われた舞台芸術祭に合わせ、池袋西口公園に期間限定のカフェなどを仮設でつくるという仕事をやっていました。ところが、たとえ仮設でも、公園に何かをつくろうとするとものすごく制約が多くて、大変だった。そのとき、こういう理由で公共空間はなかなか利用されないんだなと実感したんです。
少子化で多くの廃校が生まれている状況などもあり、総合的に見て日本の公共空間は制度疲労を起こしていると思いました。公共空間がどんどん余ってきているのにそれを活用するシステムがない。だったら、そのためのメディアがあればいいのではないかと思ったんです。で、僕はいつもそうなのですが「とりあえずつくってみるか」という感じで、公共R不動産を始めました。
公共R不動産をきっかけに、公共空間を民間で利活用する事例がたくさん生まれていますよね。
馬場:はい。公共R不動産は、大きなムーブメントのうちの一つのピースです。「公共空間にもっと民間が介入した方が楽しくなる」というメッセージ、それも具体例まで含めたメッセージを伝えるメディアになっていると思います。
良い公共空間は適切なルールと自由がバランスを保っている
理想的な公共空間とは、どのようなものだとお考えですか。
馬場:例えば公園にちょっと落ち葉がたまるとすぐに掃除してほしいと近隣住民から要望が出たりしますよね。だから行政側もまめに管理しなければと思わざるを得ない状況になっています。公共空間はみんなのものであったはずが、いつの間にか行政の所有物のように勘違いされてしまい、結果、活用の制限が進み、空間が硬直化して楽しくなくなるという負のスパイラルに陥ってしまいます。
理想の公共空間とは、適切なルールと適切な自由が、バランスを保っている空間だと思います。過度な行政の負担にもならず、適度に経済活動も行われているような、バランスを常に模索している状態が、良い公共空間と言えるのではないでしょうか。現状を見ると、もっと自由を担保するルールが必要だと思います。
理想的な使われ方をしている公共空間の例があれば教えてください。
馬場:東日本大震災直後の宮城県石巻市で、ハッとする風景を目にしました。夕方、がれきの中に残されたビルの外壁に白い布を張り、プロジェクターでアニメを流している。そこに街の人がたくさん集まって、子どもたちはアニメを楽しんでいるし、大人たちはビールを飲みながらそれを見守っている。私の大好きな映画『ニュー・シネマ・パラダイス』の1シーンのようでした。ものすごく大変な中でも、ハッピーな風景が広がっていました。いわば“超法規的状況”だったからそういう風景が生まれたのかもしれませんが、市民が、自分にできることを持ち寄って出来上がった、すごく良い風景だと思いました。
また、コロナ禍の南池袋公園を見ていると、家族連れも、一人の人も、カップルも、芝生の広場で適度に周りに気を使いながら、ちょうど良い距離感でくつろいでいました。大きな空間の中に、小さなプライベート空間が無数にあって、公共空間の中でも“自分の空間”だと思える領域が設定されている。そのようなテンポラリーな、小さなプライベート空間が調和しているような風景は、良い公共空間の在り方なのではないでしょうか。そういうことが許容され、そういうことが起きやすい空間・環境・ルールが存在している状況がいいと思います。
仮設建築や社会実験が都市の活性化の突破口に
近著の『テンポラリーアーキテクチャー 仮設建築と社会実験』の序文で、「都市は柔らかくしなやかな身体のようなものであるべき」と書かれていましたが、そうした考え方について、詳しく教えてください。
馬場:近代、特に戦後の日本は、人口も経済も成長する中で、国の“骨格”として、交通経路などのハードインフラをつくってきました。しかし、人口が減り始めている今は、これまでつくった都市空間をもっと上手に使わなければなりません。“つくる”フェーズから“使う”フェーズに変わってきているのです。
人間になぞらえると、骨格はしっかりできたので、これからはもっと筋肉や神経、血液を充実させていかなければならないということです。骨格の隙間を、さまざまな経済活動が筋肉のように埋めて、物流が血液のように隅々まで循環して物を動かし、進化する通信網やサービスは神経となる。これからは、そういう柔らかな部分を活性化させる必要があります。
そのために、一時的に設置する「仮設建築」や、本格導入前に期間や地域を限定して試行される「社会実験」が有効だと僕は捉えています。もちろん都市を安定させるための骨格は重要ですが、これからは流動的・可変的なところに意識や資本が注がれていく、そういう時代に突入したのだと思います。
恒久的に何かをつくるよりも、仮設建築や社会実験という形にすることによって、都市は活性化されていくということですか。
馬場:恒久的につくることに対して否定的な感覚は全くありません。最初からしっかりしたものをつくれるならば、それに越したことはないと思います。
ただ、今はそれだけの投資体力がなかったり、時代のスピードが速く、つくっている間に状況が変わってしまったりする可能性があります。間違った答えを出して取り返しがつかないことになるよりも、適切なタイミングと規模で、段階的に進めた方がいいですよね。物事の進め方のオプションが増えていて、そのうちの一つが、社会実験や仮設建築だというふうに考えてもらうといいかもしれません。そうした手法で、硬直して動かなくなってしまったものが少し前に進んだり、新しい突破口になったりして、本当につくるべき建築が見えてくる可能性があります。
公園や大通りを、市民のリビングルームにする試み
ご自身もさまざまな公民連携に携わっていらっしゃいますが、「nest marche(ネストマルシェ)」「IKEBUKURO LIVING LOOP(池袋リビングループ)」は、どのように実現されたものですか。
馬場:南池袋公園は2016年にリニューアルされ、芝生広場と居心地の良いカフェが人気の公園になりました。豊島区はさらに、その賑わいを池袋駅東口のグリーン大通りまで広げることを目指し、そのパートナーとして、僕を含めた公共R不動産のメンバーと地元有志が立ち上げた会社「nest(ネスト)」が参画しました。
コンセプトにしたのは、公園や通りをリビングルームのような感覚で使い、都市自体を市民のリビングルームにしようというもの。それを具現化するための社会実験として行ったのが、毎月開催するnest marcheと、年に1回規模を大きくして開催するIKEBUKURO LIVING LOOPです。
通りや公園に屋台やテントが立ち並ぶマルシェイベントですが、定期的に開催することで出店者も増え、地元のクリエイターなどが参加するケースが出てきたり、池袋に拠点を持つ大手企業が出店してくれたりするようにもなりました。一市民と企業市民がパラレルに並ぶ風景が形成されたのです。

左/南池袋公園は、2016年にリニューアル。かつては薄暗い印象のあった公園に、広々とした芝生広場を整備し、新設のカフェには、公募によって地元の人気店「ラシーヌ」を運営する事業者を選定。生まれ変わった公園が街の雰囲気をも変え、公民連携による新たな公共空間のモデルとして注目される事例となった 右/南池袋公園北側にあるグリーン大通りをメイン会場とするIKEBUKURO LIVING LOOP開催時の様子 (写真提供:株式会社nest)
とても良い状況が生まれていると思いますが、その要因は何でしょうか。
馬場:南池袋公園は本当に芝生が美しくて、風景として魅力的だったというのがポイントです。良いデザインと良いマネジメント、両方がそろっていることで今の状況が生まれていると思います。
その社会実験は現在も継続中なのでしょうか。また、その実験を経てどのような展開をしていくのでしょうか。
馬場:今も継続していますが、今後はイベントではなく、より日常化していきたいと考えています。そうするためには、どんなエリアマネジメント組織が必要で、どんなデザインが行われるべきなのか。また、行政と民間はどのように役割分担をしていくべきなのか。試行錯誤しながら、進めている段階です。
取材・文 初瀬川ひろみ
〈後編に続く〉
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.51掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年3月)のものです。








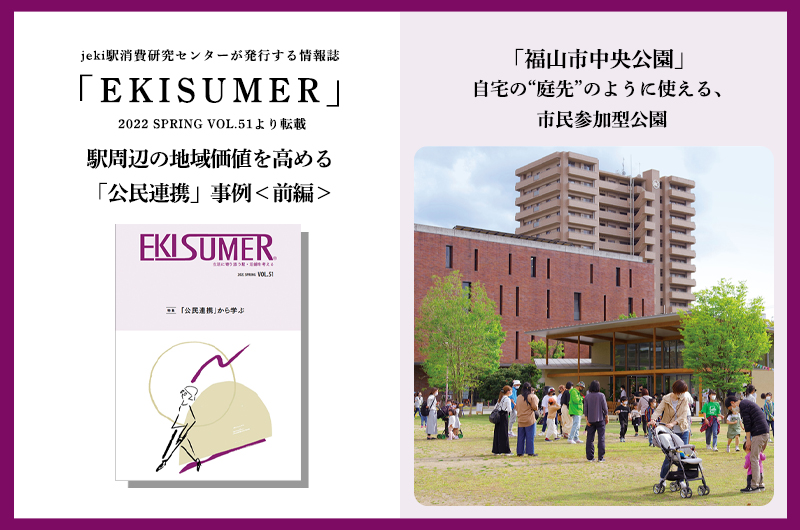
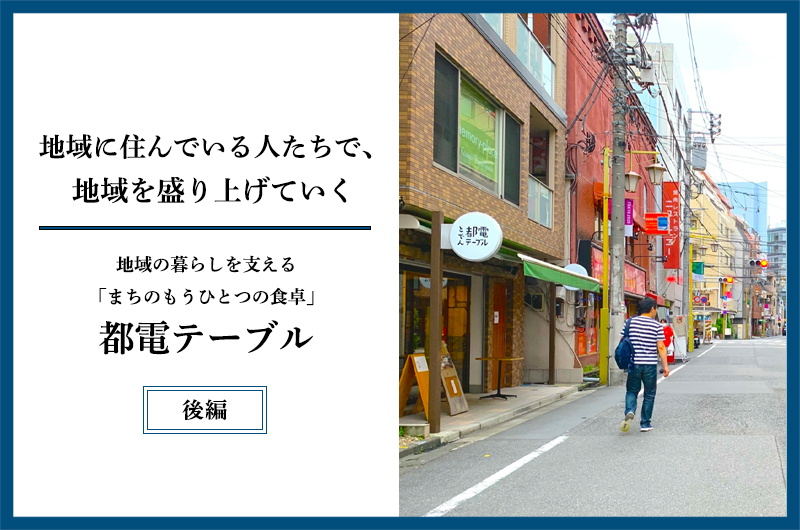


































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。