オムニチャネルにより顧客管理は進化した
EC隆盛の今、消費者はネットとリアルをどのように使っているのでしょうか。
奥谷 ネットとリアルを行き来しながら買い物をしています。何かを購入しようとする場合、今や大半の人は事前にネットで情報を検索するでしょう。そして、そのままネットで買う場合もあれば、店舗で買う場合もある。私が以前在籍していた良品計画では、ネットストアの売上の半分が家具でした。多くの人が店に行って、見て、触って、ソファならば座って、「じゃあ買おう」ということになります。ところが、お客さまはその場では買わずにネットで買ったりする。買い物におけるこうしたネットとリアルの融合は今後ますます進み、買い物行動はオムニチャネル化していくでしょう。
買い物行動がオムニチャネル化すると、どのようなことが起こるでしょうか。
奥谷 チャネルを行き来する顧客にとって、一つの店舗で選択から購入までを完結させる必要はなく、店舗はもはや顧客とのあらゆる接点のうちの一つに過ぎなくなる。そうなると、企業もオムニチャネル化しなければいけない。
オムニチャネルとは、単にチャネルを増やすことではありません。一人の顧客に複数のチャネルを用意するチャネル形態は、クロスチャネルからオムニチャネルへと進化しました。クロスチャネルの段階ではチャネルごとに顧客管理を行っているので、同じ顧客がオンライン店舗とオフライン店舗の両方で買い物をしていても企業側はそれを把握できない。それに対して、オムニチャネルの場合はチャネルを横断した顧客管理を行います。そうなれば、どちらで買い物をしても「個客」として認識し、統一した対応ができるようになる。
つまり、進化したのは顧客管理です。それまでは店舗を軸に顧客の管理を行っていたのに対して、オムニチャネルでは、顧客を軸にチャネルの管理を行うことになるのです。
買い物行動のプロセスである「顧客時間」に寄り添う
顧客を軸にしたときに、大切なことは何ですか。
奥谷 私は、買い物行動における「選択→購入→使用」のプロセスを「顧客時間」と呼んでいるのですが、その「顧客時間」に寄り添うことが大切です。購入だけを重視していても、顧客との関係を築くことはできないでしょう。そもそも、「きれいになりたいから化粧品を買う」とか「おしゃれをしたいから洋服を買う」など、購入は課題解決的であって、楽しみはむしろ買った商品を使うときが最も大きいとも思います。選択、購入、使用の各段階でどのような顧客接点をつくるかを考えるべきでしょう。
私が良品計画時代に開発を手掛けたMUJI passportは顧客時間を把握することが目的でした。注目したのはネットが持つ特徴です。例えば、顧客がどんなときに無印良品を検索しているか、ECサイトでどのように商品を選択、購入したのかが分かる。ECサイト内の口コミプラットフォームには商品のレビューも書かれている。ネットなら顧客時間の把握が簡単にできるのです。それをリアルの世界でもできないか、と考えて開発したのがMUJI passportです。多くの店がプラスチック製のカードで行っているポイントやマイルの付与をスマートフォンのアプリでできるようにしました。アプリを開いた履歴や購入履歴で、無印良品の利用頻度が分かります。アプリを通してリアルの店舗情報や店頭の在庫情報を確認できるようにしたことによって、顧客の選択段階もある程度把握できます。また、SNSや無印良品のクレジットカードとのID連携機能によって「誰が何を買ったのか」も把握できる。さらに、アプリはコミュニケーションが容易なことも大きなメリットです。来店が少ない顧客にはプッシュ通知でセール情報などを知らせ、それに対する反応も確認できます。これらによって、無印良品の顧客理解は大きく進みました。

今の時代は、そもそも消費者自身何が欲しいか認識していないようなところもあります。顧客時間に寄り添うことで、そうした潜在的な部分にもアプローチできそうですね。
奥谷 何が欲しいか分からないという顧客に対しては、リアル店舗の方がチャンスがあります。ネットの世界は能動性が求められる。何か検索ワードを打ち込まない限り何も出てこない。それに対して、リアル店舗には顧客接点がたくさんある。動く車を目の前で見たり、料理の匂いを嗅いだり、生地を触ったり。問題は、そこでどうやって精度の高い提案をするかです。これについてはネットの方が優れているかもしれません。どんな情報に触れて商品を選択し、どこの店舗でどんな商品を買い、それをどのように使ったのか。大切なのは、購買データではなく買い物行動のプロセスを可視化できる行動データなんです。それを基に、企業は顧客に対して提案を行っていかなければなりません。「お客さまは、こんなものが欲しかったのではないですか?」と。
提案がなければ、顧客とのつながりは生まれません。それが、他の人とは異なる自分だけに向けた提案であれば、つながりはより深まります。
これからは接客も顧客が選ぶ時代
オムニチャネル化が進む中で、リアル店舗はどうあるべきだとお考えですか。
奥谷 実際に売り場にいる店員は、顧客のことをどれくらい知っているでしょうか。マニュアル通りに「いらっしゃいませ」と言い、「Mサイズはありますか」と聞かれたら、そのサイズを持ってくるというだけでは意味がありません。「奥谷さん、これがいいですよ」などと名前で呼び掛けてくれる店員も限られています。購入履歴などからレコメンド情報を提供するのは、ネットでは当たり前にやっていることです。人の流動があり、空間としての魅力を持っているリアル店舗では、そんなことをしなくても買ってくれるかもしれない。しかし、それだけではよい関係性は築けません。どうやって顧客と、程よい距離感のコミュニケーションを取るか。そのために、もっとデジタルを使うべきではないでしょうか。デジタルで緩くつながり、「今日は接客してほしい」という人を特定していく。これからは、デジタルを活用した顧客理解抜きには先へ進めないと思います。
紳士服のコナカがやっている「ディファレンス(DIFFERENCE)」というオーダースーツのブランドは、オンラインとオフラインを組み合わせて新しい接客を実現しています。顧客は専用のアプリをダウンロードし、好みのデザインを事前に選択して店舗に来店予約を入れます。店に行くと、選択しておいたデザインに沿った生地が用意されていて、アプリの情報から既に顧客の要望を知っているスタッフが応対してくれる。実際に生地を見て手触りなどを確認し、プロのテーラーに採寸してもらって、購入・決済すれば最速2週間でスーツが届きます。そして、2着目以降は全てオンラインで選択から購入までを済ませることが可能になります。
ディファレンスでは、顧客が事前に「接客してほしい」ということをアプリで表明している。ここを利用している20代のある男性は、他の店に行くときはヘッドホンを着けて接客を拒否していると話していました。彼は洋服が好きなので、最近の流行など店員より自分の方がよく知っている。そのくらいの情報しか得られないのであれば、接客は要らない。ディファレンスでは事前に好みを伝えた上で依頼しているからこそ、1時間半もたっぷりと時間が掛かる接客を受けるのだと言います。これからは、接客もオプトイン(選択)の時代なのです。顧客が望んでいるときは声を掛けるが、不要なのであればしない。接客の要望をアプリなどで把握しながら、心地よいコミュニケーションを実現していくわけです。


取材・文 初瀬川ひろみ
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.38掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2018年10月)のものです。









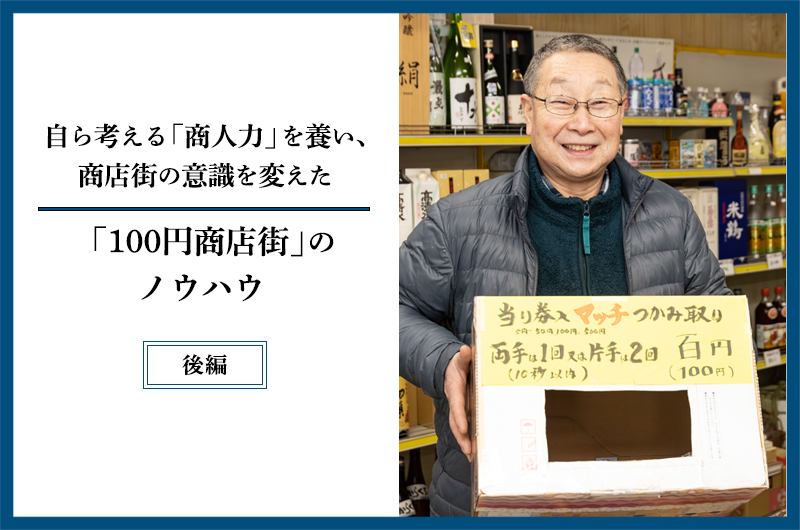

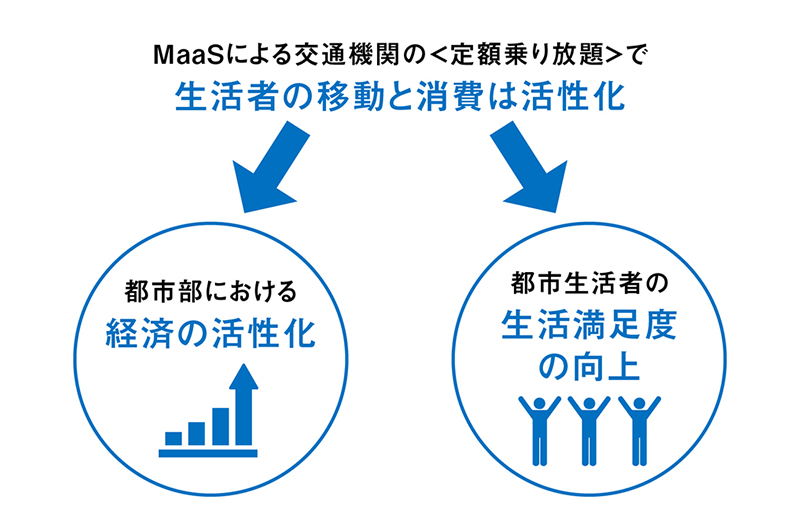

































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。