
新たなライフスタイルとして、流動的な住まい方を実践する人が少しずつ増えているなかで、その変化をいち早く捉え、生活にさまざまな豊かさをもたらす住宅やサービスが生まれています。沿線や地域を積極的に移動する居住者たちはいま、暮らしに何を求め、どんな価値を感じているのでしょうか。これからの住まい方と移動の可能性を広げていく先進的な3つの取り組みを、全3回で紹介します。

デュアルスクール とくしま
デュアルスクールとは、地方や都市など異なる地域の学校の行き来を容易にし、双方で教育を受けることができる多地域就学制度。地方でサテライトオフィスなどを運営し、地域振興事業を推進する株式会社あわえと徳島県が始めた取り組み。居住地とは異なる生活を通じて、地方と都市のそれぞれの良さや違いを知り、多様な価値観を持った子どもの育成を目指している。この仕組みを展開する目的で一般社団法人ミライの学校が設立され、他都市でも導入が進む。
都市と地方、2つの地域で学ぶ。学校の新しい形
多拠点居住者というと、単身者のイメージが強いかもしれません。それでは、子どものいる家族の多拠点居住には、どんな形があるのでしょうか。
2013年から地方へのサテライトオフィス誘致に取り組んできた株式会社あわえによれば、家族を伴って都市部と地方のサテライトオフィスを行き来する人もいるといいます。しかし、子どもが小学校へ上がる年齢になると、就学がハードルとなって続けられず、行き来をやめてしまうそうです。そこであわえと徳島県がつくったのが「デュアルスクール」という取り組みでした。デュアルスクールとは、都市と地方の2つの学校の行き来を可能にし、どちらでも教育を受けることができる新しい学校の形です。県の事業として、2016年にスタートさせました。

徳島県那賀町の滞在施設は、地域住民総出で改修した古民家。向かいにあるデザイン会社と、この施設を使うデュアルスクール利用者家族の間には、交流が生まれているという
日本の学校教育制度では、居住地によって通学する学校が決まり、2つの学校に籍を置くことは認められていません。デュアルスクールでは、希望する部活動がなかったり、いじめなどの理由で特例的に指定外の学校に通える「区域外就学制度」を、家族の短期地方居住に応用。住民票を異動させることなく、都市部の児童・生徒が徳島県の公立小中学校で学べるようにしました。1年間に複数回行き来することも可能で、受け入れ校での就学期間も出席日数として認められます。手続きも、それほど難しくありません。
「区域外就学願を提出すると、その後は双方の学校と教育委員会が手続きを進めてくれますから、親御さんとしては住民票を動かすより圧倒的に楽だと思います」と話すのは、あわえのコミュニティマネージャー、中野美優さん。「ただ送り出す側の学校の先生に対しては、なぜデュアルスクールを利用するのか、その理由を親御さんから丁寧に説明してもらっています」
中野さんは、受け入れの窓口として利用者から希望や生活イメージなどを丁寧にヒアリングし、地域につなぎます。短期間とはいえ全く知らない土地で生活しようとする利用者にとっては、不安を払拭してくれる大きな存在です。

デュアルスクールを実施している那賀町立相生小学校。地産の木材が豊富に使われているという。中野さんの母校でもある
デュアルスクールは子どもの感性と関係性を育む
あわえは、デュアルスクールの取り組みを徳島県だけでなく全国に広めるため、2021年に一般社団法人ミライの学校を設立。デュアルスクールを利用したい家族と地方を結ぶプラットフォームを提供するとともに、地方自治体に対し制度導入のコンサルティングも行っています。
ミライの学校の代表理事である高畑拓弥さんは、スタートから7年が経過した今、デュアルスクールの利用は新たなフェーズに入っていると言います。「当初はサテライトオフィスの方たちが、子どもを一緒に連れてくるために利用するケースが多かったです。いわば、親の都合ですね。ところが今は、子どもの教育的な意義を求めて利用する人が圧倒的に増えています」
短期山村留学のように、夏休みなどに都市部の子どもだけで地方を体験するのとは異なり、デュアルスクールは地域の学校に通いそのコミュニティの中で学ぶことになります。1学年数百人の学校からわずか数人の小さな学校へ。放課後はゲームではなく川遊びが当たり前。そんな日常に刺激を受け、子どもたちは一様に大きく変わっていくそうです。「初めて学校が楽しいと言った」「描く絵のタッチや色使いが変わった」「よくありがとうと言うようになった」など、子どもたちの目を見張る変化に、利用者は教育的な価値を見いだしているといいます。

稲刈りを体験する児童。元の学校とは、遊ぶ環境や遊び方、一学級の児童数などが違い、それまでにない経験ができるという
さらに、子どもたち同士にも関係性が生まれます。「友達にもう一度会いたいとリピートするケースも出てきて、翌年度にもう一度来る場合もあれば、同じ年度内に3回来た子もいます」と中野さん。「また、デュアルスクールとは全く別で、友達に会いに来た子もいました。徳島の友達からお祭りに誘われたので、親御さんをなんとか説得して来たそうです」
一方で、受け入れ校の子どもたちにも、改めて自分の町の良さを認識するという気付きが生まれます。都会からやって来る子どもに自分の学校や町を褒められて、それまで抱いていた田舎だというコンプレックスが誇りに変わる。自分の町を好きになってもらいたいと、積極的に良いところを探すようにもなります。
「新しく来る子のために、町の紹介を自分たちにやらせてほしいと先生に頼み込んで、子どもたちが自発的に町を案内したこともあります。それは観光スポットとは全く違った、大人が気づかないような本当に素敵な場所でした」
“帰る”からこその気づきは、送り出す学校の子どもとも共有
「デュアルスクールの良いところは、どちらにも居場所を持てると同時に、帰る場所があることです」と高畑さん。「自然の中の暮らしや少人数の学校の楽しさを知った上で、元の学校や都市生活の良さを改めて認識することもあるでしょう。そしてデュアルスクールに行った子が、戻って経験を伝えることが重要だと思います。それによって元の学校のクラスの子どもたちも刺激を受けて、コミュニティにも変化が生まれます」
実際、送り出した学校では、デュアルスクールに行った子どもがその経験をみんなの前で話す機会を設けることがあると言います。受け入れ校からも、その子が学校でどんな時間を過ごしたか、写真を添えて報告しているそうです。

滞在施設近くの農家で花を購入した、デュアルスクール利用者の親子。元の都会の学校の友達にこの地域の花をプレゼントしたいと立ち寄った時の様子
当初は地方創生を目的とした取り組みでしたが、親子で知らない土地に住んでみると感受性の豊かな子どもの方に大きな変化があり、教育的な価値が見えてきました。現在は長野県や山形県などでも導入が進んでおり、将来的には全国に普及させることを目指しています。大人たちのワークスタイルは多様化し、今やどこでも働けるようになりつつあります。同じように、子どもたちにもどこでも学べる選択肢を提供するべきだと、高畑さんは言います。
「デュアルスクールは多拠点居住に伴う選択肢の一つにとどまらず、移動することによって教育的価値が生まれる。だからこそ、誰もがどこでも、簡単に使えるよう整えていかなければなりません。そのために何を変えるべきかということを、自治体や教育機関はもちろん、国へも提言していきたいと思っています」
さらに、制度的な課題とは別に、経済的な課題もあると指摘します。移動先の滞在施設に関しては、地方創生の取り組みにより整備が進んでいたりもしますが、移動そのものの経費はどうしても全て自己負担になってしまうなど、デュアルスクールを利用できるのは、ある程度経済的な余裕のある家庭に限られます。そこで、多くの子どもたちが利用できるよう、「デュアルスクール基金」のようなものを作りたいと考えているそうです。
今後、より質の高い教育を求めて、さらに多くの人々が、教育的価値のあるデュアルスクールを利用するような日も来るかもしれません。基金のような形で、教育関連ではない営利企業が日本全体の教育の質向上に貢献する。そんな可能性を視野に入れておくことも求められるでしょう。
聞き手/松本阿礼 取材・文/初瀬川ひろみ 画像提供/株式会社あわえ
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.58掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年12月)のものです。
(1)unito 〜住み替えや「半一人暮らし」が気軽にできる仕組みで、住まいをもっと自由に〜
(2)リノア北赤羽 〜近隣住人も集える共用施設から暮らしの豊かさを創出するマンション〜
(3)デュアルスクール とくしま 〜まちを移動し環境を変えることが、子どもの教育的価値を生む〜








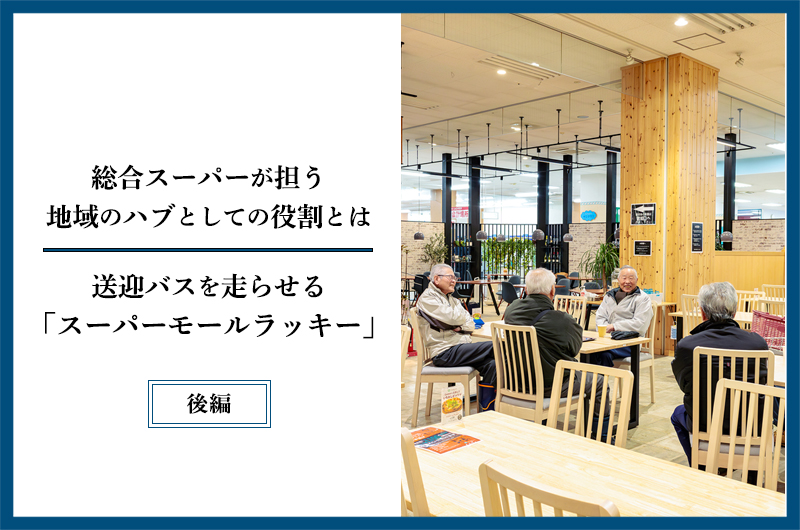
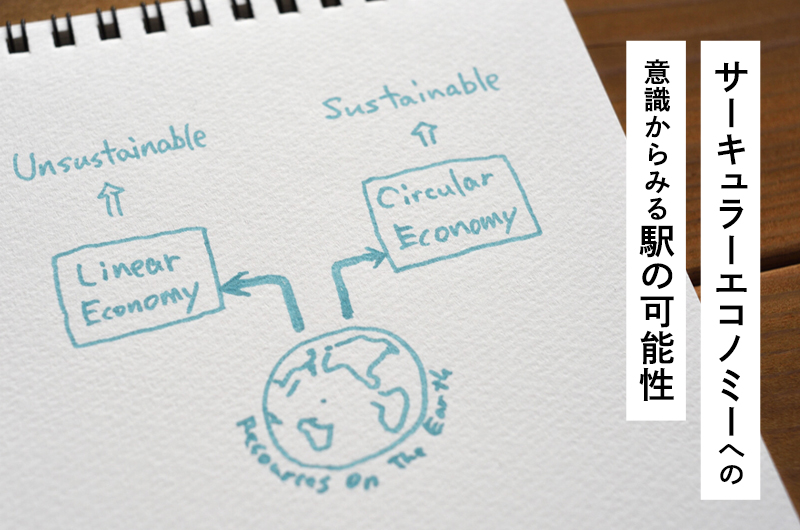





















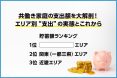












町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。