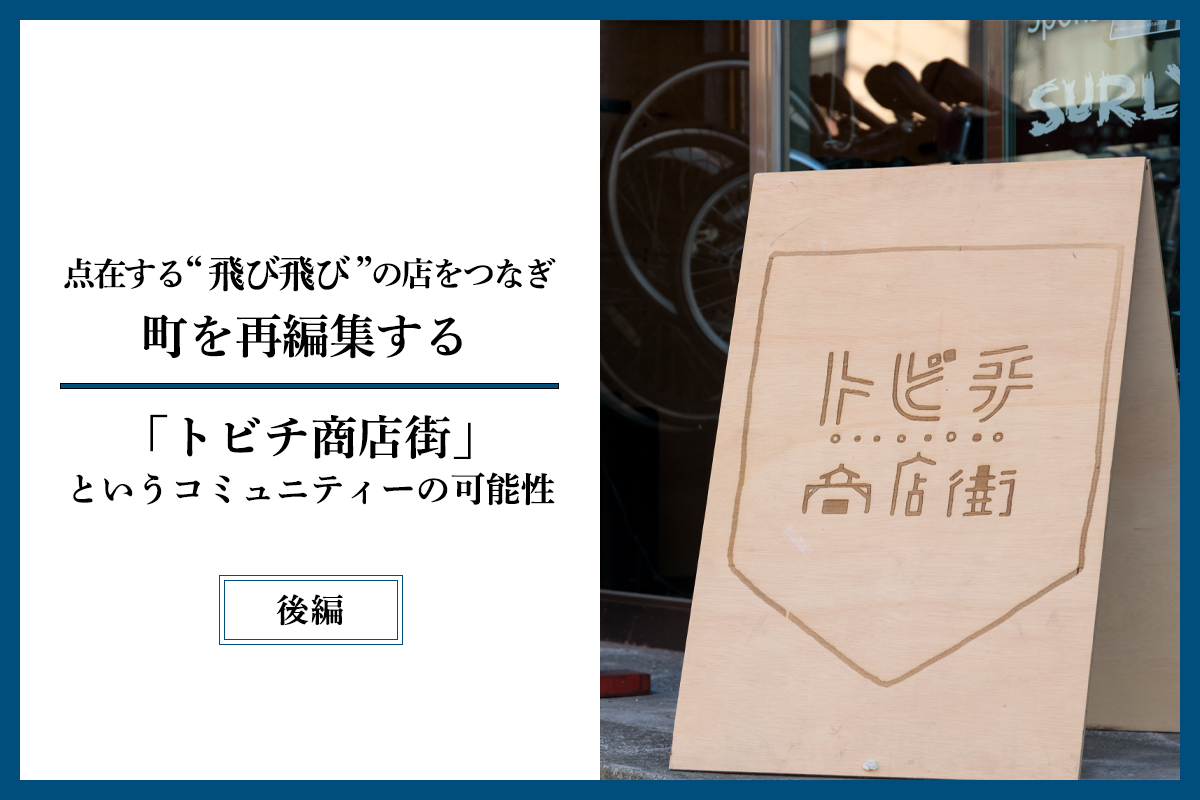

赤羽 孝太さん
一般社団法人○と編集社 代表理事
1981年長野県辰野町生まれ。首都圏で建築を学び、大学助手、大工、設計事務所を経て独立。2014年に発足した「辰野町移住定住促進協議会」に携わる。2016年には「集落支援員」として辰野町へ拠点を移し、2018年に○と編集社を立ち上げた。町の空き家バンク、シェアオフィスやサイクルステーションの運営から、不動産の管理や仲介、設計施工、ブランディングやデザインディレクションまで幅広く手掛け、企業や地域を再編集する。
素敵な店を出してくれる人に“えこひいき”して物件を紹介
トビチ商店街には、自家焙煎のコーヒースタンドをはじめ、居心地のいいバーやこだわりのセレクトショップ、古着屋さんなど、おしゃれで個性的なお店が多いですね。何か選択基準があるのですか。
赤羽:空き家バンクに登録している物件の中でも、とっておきのものはあえて非公開にしておいて、自分たちの暮らしが豊かになりそうな店を出してくれる人を選んで紹介します。ある種の“えこひいき”ですよね。僕らは行政ではなく、民間の不動産会社として関わっているわけです。
空き家対策もトビチ商店街も、町のためにやっているというより僕の趣味です。自分のお金と時間を使って、リアルな街づくりゲームをやっているみたいなもの。それでおいしいコーヒー屋さんができれば僕はハッピーだし、ついでに町の人もハッピーになってくれたら、なお良しです。
最近は、株式会社On-Coが運営する「さかさま不動産」と連携を始めました。物件情報が並ぶこれまでの不動産会社とは逆の発想で、借りたい人の夢や思いなどの情報が公開されていて、空き家のオーナーがこの人なら貸したいと思う相手にアプローチするというものです。空き家を素敵に使ってくれる人を見つけていくためにも、これからは人の情報が大事です。

Equinox STORE内のセレクトショップKaymakli(カイマクル)の大槻さんがDIYした店舗奥のギャラリースペース。この日は辰野町で活動する2008年生まれの画家、三村大悟さんの個展が行われていた。
トビチ商店街のスタートは、2019年12月7日に開催された「トビチmarket」というイベントだそうですね。どんなイベントだったのでしょうか。
赤羽:「10年後のトビチ商店街の1日を体験する」ことをコンセプトとして、地域の人たちにトビチ商店街のビジョンを共有してもらおうと企画しました。そのためトビチmarketの出店者は公募せず、僕たちが良いと思える全国のお店にこちらから声を掛けました。しかも、実店舗を持っているお店に限定しました。店舗を持っているお店は、その土地に思い入れがある。だから、僕たちの考えに共感できます。そういう人に参加して欲しかったのです。
地元のお店にこだわらず、全国のお店に声をかけた理由は何だったのでしょうか。どのような意図がありましたか。
赤羽:ローカル・オブ・ローカルの辰野町には、やっぱり人が少ない。人口2万人くらいのこの町の経済規模で、お店を成り立たせるのは難しい。でも、近隣には1時間ほどで行ける松本市があります。辰野町からも松本に遊びに行きます。だったら、逆に松本から人を呼ぶこともできるはずだと考えました。1時間で行ける範囲を商圏とすると、圏内の人口は一気に約60万人になるのです。僕はこれを「1時間商圏」と呼んでいます。そう考えると、可能性が広がります。地域が“ローカル”に落ち着いてしまったら、ずっと“ローカル”でしかない。松本の人たちにも行ってみたいと思ってもらえるような店を揃える。そういうイベントにしたかったのです。
結果的に、トビチmarketでは下辰野商店街の空き店舗と空き家に、県内外から飲食店や雑貨店、貸本店などワクワクするようなお店が54店舗出店し、1日で4,000人以上の人たちが来てくれました。
場所ではなく、誰が何をするかが大事な時代で、それが共感を生むのだと思います。
地域性よりも、純粋にみんなが行きたいと思えるワクワクしたお店をそろえたことが、成功のポイントだったのですね。
不動産を入口として店づくりのためのソフトをビジネスにする
○と編集社は、不動産ビジネス以外にもさまざまなプロジェクトや事業を行っていますね。そこには、どんな思いがあるのでしょうか。
赤羽:不動産ビジネスの仲介手数料は物件の値段で決まるので、一般的に安い物件は敬遠されます。しかし、行政目線の空き家バンクは、活性化や移住・定住を目的にしていますから、市場価値が低い空き家でも改修して誰かに住んでもらうことで、地域に人を増やしたい。そこにギャップがあるので、自治体の人が不動産業界の人に空き家バンク運営のアドバイスを求めても、なかなかうまくいかないのです。
○と編集社は、普通の不動産屋さんが扱わない不動産のみを扱っています。僕たちの場合は、入口として不動産屋をやっているので、不動産で数字を作る必要がありません。空き家を改修してお店をやりたいという人につないだら、お店のパンフレットを作ったり、デザインディレクションをしたり、ブランディングをするという形でビジネスをしていきます。
もちろん、不動産の仲介だけをやる物件もありますし、場合によっては設計や施工を依頼されることもあるなど、物件や顧客それぞれの事情でさまざまなやり方があります。今ちょうどDIYで改修を進めている建物は、旧旅館。物件を買った方から僕たちが建物を借りていて、改修後には宿泊機能付きのシェアハウスを運営することになっています。その運営は○と編集社ではなく、分社化して新たにつくった合同会社トビチカンパニーが担います。

この日のDIY改修イベントには、町の子どもから兵庫県在住の家族連れまで約15人が集まった。イベント参加者はペンキ塗りを担当し、基礎工事は契約する工務店のメンバーが行う。館内の古い案内はそのまま残す。
不動産を入口にして、ソフトの部分をビジネスにしているのですね。
赤羽:集落支援員としての3年の任期が終わるときに、行政の事業の受け皿となる団体として法人をやろうと決めていました。でも、行政の仕事だけのまちづくり法人では面白味がありませんから、民間としての仕事もやることにしました。僕は建築の出身ですが、空き家の活用はハードよりソフトの方が大事だと思っています。デザインやコミュニティーの要素が重要になってきますから、メンバーを集めるときもそういう意識でチーム作りをしています。
入口を不動産屋にしたのは、まちづくりをしていくときに場所をコントロールできるからです。鳥のような目線で町全体のストーリーを見ながら、この場所にカフェがあったら面白いなどと考えられます。その上で、先ほどお話ししたように、そこに素敵な人を引っ張ってくるわけです。
なるほど、そのようにしてトビチ商店街は着実に店舗を増やしているのですね。今後に向けての、思いや展望などがあれば教えてください。
赤羽:飛び飛びのトビチ商店街は、自転車ととても相性がいい。自転車を使えば少し離れた里山にあるこだわりの店にも行きやすいですから、自転車をレンタルできるサイクルステーションも整備しました。ただ、里山エリアまでは10kmほどあります。行きは自転車でサイクリングを楽しんで、帰りは電車で戻ってこられたら、もっと気軽に巡ることができます。車内に自転車を持ち込めるサイクルトレインの実施を、鉄道会社さんにぜひともお願いしたいです。
商店街と駅は切っても切れない関係です。駅があるから商店街が形成されますし、商店街が盛り上がれば鉄道の利用者も増えるでしょう。自転車も鉄道も垣根なく使えるようになれば、新たな客層が増えてWin-Winになるのではないかと思っています。

○と編集社が取り組む事業の一つ、サイクルステーションのgrav bicycle station(グラバイステーション)の入口。理事で、自転車で世界一周した長野県岡谷市出身の冒険家、小口良平さんが中心となって運営している。
聞き手 松本阿礼/聞き手・文 初瀬川ひろみ
写真 徳山喜行
〈完〉
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.55掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年3月)のものです。








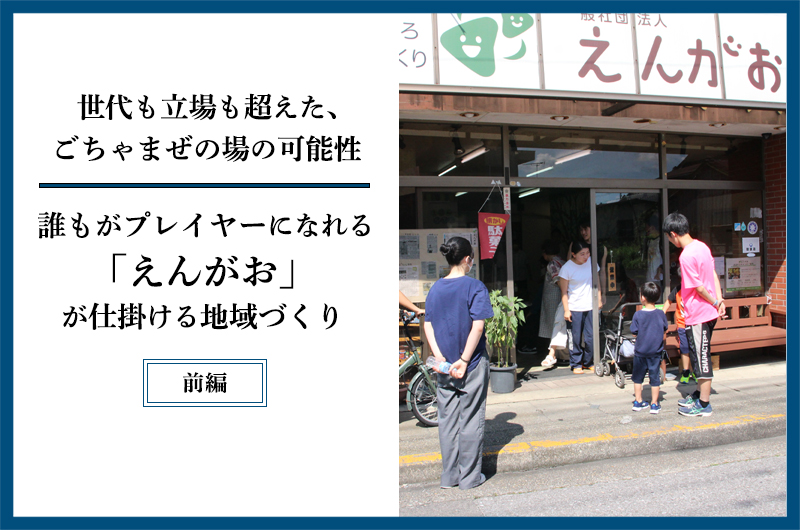

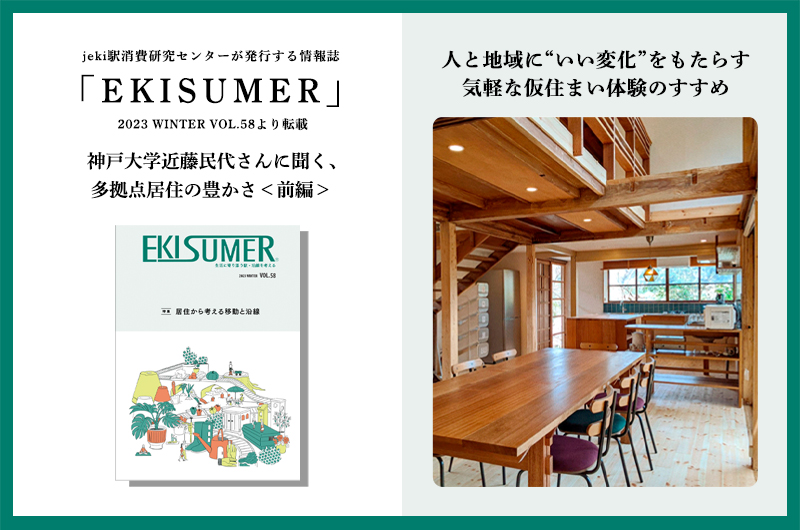

































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。