
写真左 ヤマザキビスケット マーケティング部 部長代理 飯島宏一郎氏 写真右 ジェイアール東日本企画 第一営業局 次長 兼 第二部長 今野史子
1970年の設立以来、海外大手ビスケットメーカーとブランド使用に関するライセンス契約を締結し、その製品を日本国内で製造・販売してきたヤマザキビスケット。長期に亘った契約が2016年8月末をもって終了し、社名も現在のものへと変更。同時に、46年間日本国内で圧倒的知名度を獲得していた既存ブランドも手放すこととなった。残された製造・販売の経験と知識を背景に、新ブランド「ルヴァン」「ルヴァンプライムスナック」「ノアール」を立ち上げ、国内で自分たちが育ててきた圧倒的知名度と実績を誇る既存ブランドに対し、新規参入者として挑戦しているヤマザキビスケットの飯島宏一郎氏に、jeki第一営業局の今野・鳥飼が話を聞いた。
消費者の方々に「後継品」であることをいかに理解してもらうか
鳥飼:2016年のライセンス契約終了については、ギリギリまで交渉が続いていたこともあり社名の変更や新ブランドへの移行を周知する時間もなかったのではないかと感じます。
飯島:ライセンスについては経営判断です。ブランドライセンスが使用できなくなっても、これまでの製造ラインとそこで培った技術まで手放すわけではありません。企業としては、その財産を活用しないわけにはいかないと同時に、今までご愛顧いただいた消費者のために製造を止めるわけにはいきません。後継となる新ブランドの誕生は必然でした。
ただ、ライセンス契約上の条件もあり、「ルヴァン」ブランドは16年に立ち上げましたが「ルヴァンプライムスナック」や「ノアール」ブランドは17年12月からのスタートになりました。
鳥飼:今回は、ライセンス契約で製造していた既存ブランドも国内市場に残り続けていますが、看板は同じでも生産背景などは全く違うものになっています。つまり、消費者が慣れ親しんでいた商品に近いものはヤマザキビスケットの新ブランドという珍しいケースだと思います。
新ブランドとして、既存品の後継品であることを想起してもらうのか、全くの新規ブランドとして訴求するのか、コミュニケーション設計はどのようにされたのでしょうか。
飯島:全く新しいものというよりは後継品という訴求です。ライセンス契約で製造していたブランドの後継品でありながら、より良くなったと感じてもらうことを目指しました。
既存ブランドは、今も消費者の方に「幼い頃から親しんだブランド」として選ばれています。そこではライセンス契約や生産背景の違いは意識されていません。これはブランドの力である一方、無意識に私たちの国内生産品ではなく海外生産品を買っていることになるとも考えられ、消費者の方にとっては選択の自由が制限されているという見方もできます。
「ルヴァン」や「ノアール」が生産背景的には既存ブランドの後継品にあたると理解したうえで、既存品を選ぶのは仕方がない。皆さんが昔から食べていたものが今どうなっているのかを、他社との比較という形ではなく、日本のヤマザキビスケットが作っているものとして伝えていくことをコミュニケーションの軸にしています。

今野:新ブランドへ移行したタイミングでは、特にウェブメディアを中心に既存ブランドと比較する記事が多く出ていました。食べ比べるのは特に消費者にもインパクトがあったと思います。
飯島:当時のメディアでの露出は、生産背景の相違や社名変更という話題性もあり、自然発生的に生まれたものです。なかには私たちが広告を通じて伝えきれないことに触れているものもありました。
食べ比べのようなものは私たち企業側からの発信になるとプロモーション感が出て逆効果になりかねません。ウェブメディア特有の動きだったからこそリアルに感じてもらえたと感じています。テレビの情報番組も含め、そこで情報に触れた人が友人・知人に話したくなるという側面もありました。
鳥飼:確かに「バズる施策」を企業から仕掛けると炎上などの一因となり、逆にブランド価値を傷つけてしまうリスクもあります。
メディアの記事に触れたり、人づてに話を聞いたりして、食べ比べた人が「ルヴァン」「ノアール」を選ぶ、戻ってくるという感覚は持っていたのでしょうか。
飯島:はい。実際に、販売実績(POSデータ、出荷データなど)を見てもシェアは伸びており、一時的に既存ブランドのシェアを逆転する場面もありました。
これまで既存ブランドを作っていたのが私たちで、生産背景的にその後継が「ルヴァン」であり「ノアール」だという情報を得てから食べた消費者は、その後も当社のブランドを選び続けている。こうしたブランドスイッチがシェア拡大につながったと考えています。とは言え、まだ完全に認知を獲得したわけではないため、まだまだ情報を発信していく必要性を感じているところです。
鳥飼:「ルヴァン」ブランドでは広告のキャラクターに前のブランドから継続して女優の沢口靖子さんを起用しています。その狙いについても教えてください。
飯島:私たちが一番大事にしなければならない、獲得すべき市場は、ライセンス契約で生産していた時代から私たちの製品を食べていた人たちです。今、その人たちが既存ブランドを食べているのなら、私たちのブランドについて正しく理解してもらい、選んでもらえるようにする必要があります。
そこで、社名変更以前からの取り組みを継続することで、社名やブランド名が変わっていることを知ってもらう狙いがあります。テレビCMの沢口靖子さんの起用については社内でも敵に塩をおくることにならないかという議論がありました。しかし、当時からの私たちのファンと、社名やブランド名が変わった今の私たちをつないでくれる存在としてあえて継続する選択をしました。
テレビCMについては、長く同じ番組に提供し続けていることも効果的です。特に私たちが提供しているのは長寿番組と呼ばれるものが多く、そのメリットはずっと同じ人が見ているので、CMの変化にも気づいてもらいやすいことです。スポットCMはキャンペーンなど、戦略的に使うことでリーチする狙いもあり重要ですが、同じ時間、同じ番組に流すことにも意味があります。
サッカー、Jリーグのカップ戦へのスポンサードも、2013年に「同一スポンサーによる世界最長のカップ戦」としてギネス世界記録に認定されています。サッカーファンにとって、私たちは非常に親近感を抱いてもらえる環境にあります。このスポンサードの継続も、2016年から名称を「ルヴァンカップ」と変更したことは、企業名の変更の認知度向上に非常に効果がありました。
一方で、流通の方からの反応は厳しいもので、私たちのテレビCMで既存品が売れるという声もきかれました。ただ、これは消費者の行動から考えると、たとえばビールのテレビCMを見てビールを買いに行くとしても、店頭にないという理由も含めて、お店にある違う銘柄のビールを買うこともあります。これは仕方がないことです。店頭までの時間でブランドへの意識が薄れ、違うブランドを選ぶこともあります。
また、ひとつの対策としてテレビCMのメッセージを見直しています。これまでは「パーティー」をキーワードにして、沢口靖子さんといえばパーティー、既存ブランドというイメージが定着していました。しかし、実際の消費者はパーティーをするからクラッカーを買うわけではありませんし、常に家に置いている、常備する人がメーカーから見ると理想的な消費者です。
パーティーをするから買うというのは年に一度あるかどうか。そうではなく、常備していればパーティーにも、おやつにも、防災の備蓄にもなる。そのような生活の一部にしてほしいという狙いで、テレビCMでも「家にルヴァンがあるからパーティーをしよう」という表現へ変えています。これによって、買い物へ行った際に店頭で見かけて買うという行動へ繋げることを目指しています。流通との戦略もこの方向性で進めようとしていますが、まだ実現できているとは言いがたい状況で、この点は課題となっています。
理解がなければ真のブランドスイッチは生まれない 先人たちが開拓し、築き上げたブランドに挑戦することの難しさ
鳥飼:シェア獲得において認知度や理解度など、どういった項目の数値と関連性が高い、あるいは評価しているのでしょうか。
飯島:私たちが一番重要視しているのは認知よりも理解です。ブランドの名前を聞いたことがある、ということよりももっと深く、「ルヴァン」がなぜ誕生したのか、なぜヤマザキビスケットという社名になっているのかを理解してもらわないと、真の意味でブランドスイッチを達成できないと考えています。
テレビCMはルヴァンカップの効果で社名もブランド名も多くの人の耳に入っていると思いますが、それがどんなものなのかを伝えることが大事で、同時に課題でもあります。
今野:やはり長い間既存品のパッケージや名前に親しんでいるからこそ、理解が必要ということですね。

飯島:理解を助ける取り組みのひとつとして、昨年末から「ルヴァンプライムスナック」は、パッケージの上部に記載する企業名を「YBC」だけだったものに「ヤマザキビスケット」を併記するように変更しています。テレビCMでも「ヤマザキビスケット」と表記するようにして、商品名と企業名を合わせて伝えて、関連した認知を獲得し、そこからより深く知ろうとする行動を喚起したいと考えています。
現在、既存品が獲得している認知度やロイヤリティは、当社設立以来の先人たちが40年以上かけて獲得したものです。消費者は既存ブランドに安心感を持っています。ブランド名を聞いただけでなんとなく「好き」と感じる。それくらい浸透しているので、どこで作られているかをあえて気にしないで買っている。優秀で熱意のある人たちが作り上げたいまの既存ブランドを超えようとするのは本当に大変です。
「ルヴァン」と「ノアール」がデジタルよりもテレビを中心とする4マスに重心を置いているのも、既存ブランドに親しんだ層への認知を狙っているからです。お菓子の主要購買層は30〜40代で、若い層はお菓子を買わない、そもそも少子高齢化で人口が減っていくという危機感もあります。自分自身がお菓子を買うときに選ぶものは何かというと、小さい頃から食べているものがやはり安心します。それは、自主的に買うというよりも、母親などが買って家にあったものです。
「ノアール」では女優の広瀬アリスさんを起用し、若者への訴求を意識していますが、同時に、主要購買層に確実に買ってもらい、いつも家にある状態にしたいと考えています。若者が自分で買わなくても、家にあるから自然に触れる、そうしていつか自分が買う側に回ったとき、私たちのブランドを手に取っていただく、そのサイクルを作っていくことが重要であると考えています。
お菓子は人と人をつなぐもので、単なる嗜好品ではないと思っています。今はお菓子も少量化や個包装になっていますが、「ルヴァンプライムスナック」はSサイズでも13枚入りが3パック入っています。ある種時代に逆行した内容量になっていますが、家族で「一緒に食べる」といった会話のきっかけになるためにはこの形態が必要になります。分けあって食べる、誰かにあげる喜び、もらって嬉しいというコミュニケーションは、お菓子のもつひとつの価値、家族や世代をつなぐものだと考えています。
鳥飼:今後についてはどのような展望をお持ちですか。近年は消費のスタイルも「モノ」から「コト」をより重視するようになっています。お菓子を食べる新しいシーンの提案という方向性もありますが、やはり理解度が重要でしょうか。
飯島:「ルヴァン」は一時的にシェアを逆転しましたが、もともとはほぼ市場を独占するほどのシェアを持っていたので、51%を獲得できたとしても満足することはできません。ここからが重要だと考えています。経緯を見ると異色ではありますが、私たちは新規参入者になります。引き続き、消費者の理解度を高めていくことが重要になります。
お菓子を食べるシーンについては、今は「コト」があふれているようにも感じています。そこであえて「パーティー」に絞るのもひとつの選択肢ですが、あふれる「コト」、さまざまなシチュエーションにお菓子を食べてもいいと感じてもらいたいと考えています。例えばクラッカーは、他のお菓子と比べて、罪悪感が少ないというのが特徴であり、朝食にも、スポーツをした後の小腹満たしとしても、健康意識が高まる現在だからこそ、クラッカーが担える役割は多様化していると考えています。
【取材を終えて】
「ルヴァン」・「ノアール」のシェア拡大戦略について、「生産背景的に後継商品であることを正しく理解してもらい、その上で消費者に選んでいただける形を目指した」と、決して押し付けではなく、丁寧に情報を伝えるという姿勢に感銘を受けました。
大企業の発する声が炎上に繋がることもある時代、消費者に応援されたのはこのような姿勢の賜物だと思います。
そして、「お菓子は世代を超えて繋がれていくもの。例えブランドが変わっても、安心できる味として存在し続けなくてはいけない」という言葉も伺い、自社や商品の存在意義と真摯に向き合うことの大切さをあらためて感じました。
「ルヴァン」・「ノアール」がこの先何世代にも愛されるブランドに育つことを心の底から願っております!(鳥飼)
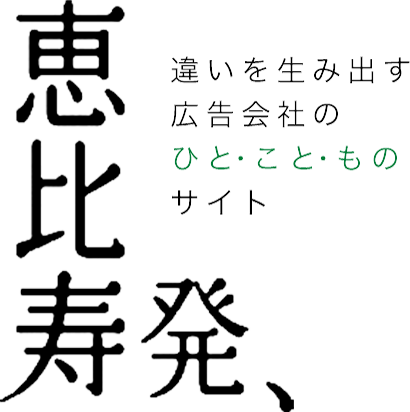
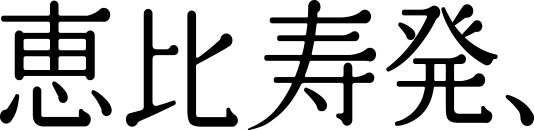






















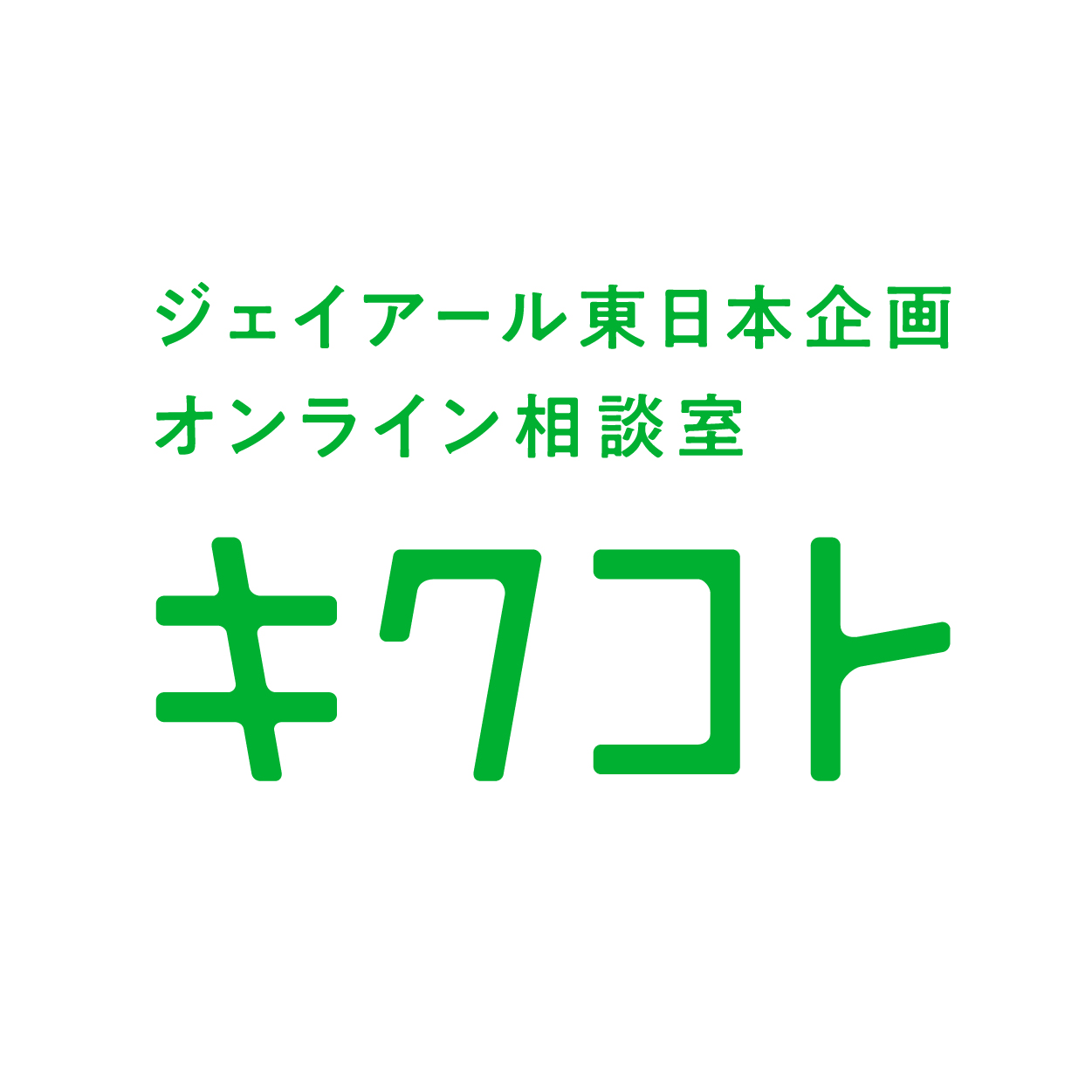


















今野 史子 第一営業局 次長 兼 第二部長
1992年jeki入社。以来、一貫して営業部門を歩む。 流通系クライアントを長く担当し、2011年部長、2013年より現職。