
写真右:ワークマン 専務取締役 土屋哲雄氏 写真左:ジェイアール東日本企画 上級執行役員 デジタル・ソリューション局長 萩原浩平
作業着、および作業関連用品を販売するチェーンストア「ワークマン」のフランチャイズを運営するワークマン。創業以来、建設現場などで働く作業員向けに事業を展開してきた。近年は作業現場の過酷な環境でも通用する防風性や防水性を持つ高機能・低価格なプライベートブランド(PB)が注目され、一般消費者からの支持も集めている。こうした流れを受け、扱っているのは作業着と同じPB商品ながら、一般消費者を意識した店舗設計の「ワークマンプラス」を2018年にオープン。以降「ワークマンプラス」業態での出店も拡大させている。機能を訴求するための「過酷ファッションショー」や、2020年3月には時間帯によって看板を「ワークマン」から「ワークマンプラス」へ掛け替えて変身する実験店舗をオープンする予定だという同社専務取締役の土屋哲雄氏に、jekiデジタル・ソリューション局長の萩原浩平が話を聞いた。
商品はそのままに店舗の「空間戦略」を変えた「ワークマンプラス」誕生
萩原:土屋さんは三井物産のご出身で、アパレル業界の経験もないというユニークなプロフィールをお持ちですね。
土屋:三井物産では、35歳から約10年間社内ベンチャーを立ち上げ、秋葉原でレーザープリンターの制御装置やボウリングの自動採点装置などの開発をしていました。
その後復帰し、経営企画を担当したのちに三井物産を退社。IT企業を2社挟み、創業者(元会長)から声をかけていただいて、2012年にCIOとしてワークマンに入りました。
萩原:一般消費者向けの店舗形態「ワークマンプラス」を立ち上げるために入ったわけではないのですね。今の動きにつながるようなきっかけは何かあったのでしょうか。
土屋:当初は企業ガバナンスを見てほしいということだったのですが、1年くらい経った頃に社内にただよう逼迫感に気づきました。CIOとして入っていたので、3年、5年先を見たときに組織として店舗数が3桁なのか4桁なのか、ということは非常に重要な視点になります。多方面から分析してみると既存の事業には「取り尽し」感があった。社内のヒアリングでも、事実そうだということがわかりました。
入社当初のジョブアサインはCIOだったので事業の変革については考えていませんでしたが、事業をさらに発展させるポテンシャルのある会社だとは感じていました。そこに社内の天井感に気づき、当初の役割からジョブを増やして新規事業もやってみようと考えました。
アパレル事業の経験はなかったものの、ベンチャー時代に海外のパソコンメーカーの販売代理店として通販をしていたことと、秋葉原でパソコンショップもやっていたので多少小売の知見はありました。
商社時代に新規事業をやったときに、売上100億円、利益10億円規模までは企画力ですぐに成長させることができましたが、1000億、2000億円規模へ成長させるには突出したオペレーション能力がないと難しいことに気づいていました。そこで、自分が企画し、オペレーション能力の高い企業と組むことが最適な組み合わせなのではないかと考えていました。
2014年に中期業態変革ビジョンを策定しました。従来の作業着、作業道具の専門店から、一般消費者向けの衣料品販売への参入も含む、市場を拡大し売り上げ、店舗数を拡大するための改革をスタートさせました。もともと、ニッチな市場のナンバーワンで2位の企業とも大きく売上、店舗数ともに差があるので競争はないに等しい。そのため「変革」といっても期限はありません。そのかわり、やると決めたらできるまでやる。改革を実行するための組織へと移行するための準備として、社内文化についても、変えるべきもの、守ることを取捨選択しましたが、6割近くは変える必要はありませんでした。
社員に対しては、事業内容の変革にともなって、改革で価値観や業績評価も変わることになるので5年間で100万円のベースアップをすると宣言しました。成果報酬を先に出して会社としての決意を表現し、変革の機運を高めました。

萩原:ワークマンプラスは、それまでのワークマンの吉幾三さんのテレビCMや作業着のイメージから大きく変化しました。
土屋:テレビCMを変えたのは2014年です。リーマンショックをきっかけに、企業が作業着を支給することが減って、個人で買うことが増えました。これにともない、作業着にもファッション性が求められるようになりました。業界全体にスタイリッシュ化の波が来ていたにも関わらず、ワークマンの作業着は「ダサい」「許せる」「カッコいい」で分類すると8割の商品が「ダサい」というものでした。こうした状況も社内の危機感につながっていた理由のひとつです。
当社は製品よりもオペレーションの会社で、PBの在庫をキャリーして翌年も売るという今のやり方は発想にありませんでした。商品在庫を持たないなど、創業者が作り上げた方針を39年守り続けて、成功した会社です。そこから意識を変えて、在庫をかまえても売れ続けるような商品力を身につけることは改革の第一歩でした。
ただ、作業着がスタイリッシュ化し、そこに一般消費者が先に目をつけていると気づくまでには1〜2年かかりました。店舗で派手な色が売れていることがわかり、購入者の属性を調査したところオートバイのライダーや釣りをする人が多かった。「ワークマン」のPBは作業員だけではなく、一般の消費者にもニーズがあった。
これが一般消費者向けの店舗設計を意識した「ワークマンプラス」誕生や、現在取り組んでいる「アンバサダー」と呼ぶさまざまなジャンルの愛好家の意見を聞いて進める商品開発にもつながっています。
ファンをアンバサダーとして商品開発に活用
萩原:ワークマンプラスの商品開発は、売れているものの傾向を分析して、そこからニーズを見つけたということですね。
土屋:最後に市場調査的なことをしたのは売り方を変えたとき、「ワークマンプラス」を立ち上げる前のことです。PBの製品を一般消費者にも使いやすいものにしたにもかかわらず、売り上げは4〜5年前から3〜5%しか伸びなかった。商品は良いので、問題は売り方ではないかと考えた。当社で「空間戦略」と呼んでいる出店場所や店舗内の設計などを180度転換しました。
従来のワークマンらしくない場所へ出店し、見せ方と顧客体験(UX)を変えることで消費者の意識を変えようとした。それがショッピングモールへの「ワークマンプラス」の出店です。路面店の建設費と同じくらい内装にも予算を投じ、既存店の「らしさ」をなくした店舗にしました。販売する商品は、従来の「ワークマン」と同じものです。
このモールの店舗が好評だったので、「ワークマンプラス」の2号店は路面に100坪の店舗を出しました。特に戦略があったわけではなく、仮に売れなくても通常のワークマンに戻せば良いという考えでした。通常アパレルの路面店は150坪から200坪くらい必要で100坪は絶対ダメだと言われていたのですが、2号店はショッピングモールの店舗より売れました。
「ワークマンプラス」の路面店の成功は、既存店舗の改善のヒントになりました。これまでワークマンは路面店でも一般消費者をカバーしてきましたが、そのうちの数店舗に「ワークマンプラス」の雰囲気を取り入れる“ミニ改装”を行うことで、さらに一般消費者も入りやすくしました。最近は、この「ワークマンプラス」仕様の店舗が増えていて、朝晩はプロ顧客、昼間と土日は一般消費者と回転率が2倍になる、二毛作的な店舗になっています。この店舗形態を今後の標準にする方針です。
2020年にはワークマンからワークマンプラスに看板が変わるコンセプトストアを出したいと考えています。今は、ワークマンプラスでないとアウトドアウェアは置いていないと思う消費者もいるので、この変身する店舗で商品が同じであることの認知を獲得したい。
萩原:ワークマンの商品は高機能でありながら低価格。これは他社に真似できないポイントです。そこにはどのような秘密があるのでしょうか。

土屋:まず生産量が違います。私たちはパンツでも20万〜30万本つくっていますし、新商品でも初年度のサンプルでも5万から10万着作るので1型あたりの生産量が多い。日本のアパレルは万単位で商品を生産することは少ないです。さらに、縫製を工場の閑散期に行うことで工賃をおさえることができています。
また、これはイノベーションと言っていいと思うのですが、どんな商品でも毎年色と柄だけを変えて最低5年は売り続けます。売り続けることで他社は価格も機能も勝負できなくなる。私たちのマーケット戦略の第一は「お客さんが値札を見ないで買えること」です。値札を見るということは不信感があるからです。作業着でも一般消費者向けでも、値札を見ないで買ってもらう、そのためには機能も価格もダントツになっていないといけない。
原価率は、通常のアパレルが20%くらいと言われているところを、私たちは64%と高い。その代わりセールはしません。在庫リスクは主に本部で、利益は加盟店と本部で分け合うオペレーションを磨き上げることで、参入障壁を高くしています。
この手法で作業着はもちろん一般消費者向けの低価格アウトドアウェアも30〜40年かけて市場を独占していくことを考えています。新業態「ワークマンプラス」をはじめて約1年経ち、今のところ追随する企業は出てきていないので、もしかするとすでにその狙いは果たせているのかもしれません。
萩原:「過酷ファッションショー」は非常にユニークでした。機能を表現するには最適な方法ですが、実際にやる人はいなかった。社内に反対はありませんでしたか。
土屋:雨雪風への強さで食っている会社なので、反対はなかったです。普通のファッションショーをしてもウケないと考えたので、「ワークマンらしさ」を追求しました。次の秋冬は、ソーシャルとの連携をアピールしたいと考えています。場所も外でやるよりも店舗の方が話題性も高まりますし、商品発表会をした店舗の売り上げも上がるのではないかと期待しています。
萩原:アンバサダーと呼ばれる消費者の意見を商品開発に活用されているそうですね。
土屋:みなさんワークマンのファンで、ヘビーユーザーとして知られている人たちです。私たちが声をかける以前からブログやYouTube、ソーシャルメディアでキャンプや釣り、ツーリングなどで使用したときの感想を発信していました。そうした人たちの意見を聞き、商品開発に生かすことで、より消費者のニーズに近い商品展開ができると考えています。
ただ、私たちはアンバサダーの意見を参考にしていますが、それに対して対価はお支払いしていません。ひとりのユーザーとして意見をもらい、それが反映された商品にいち早く触れ、自分たちのメディアで紹介する。店舗では商品説明をしないので、その補完としてマネキンにQRコードをつけています。そこから開発に携わったアンバサダーの方が商品を紹介しているブログに飛んでもらう。テレビや雑誌の取材も、店舗ではなくアンバサダーの方を対象にしてもらうようにしています。そうして閲覧数やフォロワーが増えることがメリット。それは収入にもつながっているはずだと考えています。
萩原:広告業界でもインフルエンサーの活用は求められていますが、どうしても良く書いてほしいという気持ちになりがちで、ステルスマーケティングの危険性と紙一重です。アンバサダーの方の記事に注文をつけることはないのですか。
土屋:アンバサダーの方のブログや動画をPRとして扱い、対価を払ってしまうと、そのレビューを見た人の印象が変化してしまう。アンバサダーにもより本音で語ってもらうためにそうしています。アンバサダーの方には自由に意見を言ってもらいたい。批判が6割くらいある方が信頼性は高まると思っています。そこはユーザーに委ねています。
今は女性が発信の中心ですし、女性のアンバサダーを増やしています。メディアとしてはインスタグラムに注力していて店舗でもインスタ映えするような場所を作れないか考えているところです。
萩原:店舗数はまだ増やせると考えていますか。ユニクロやデカトロンの存在は意識しているのでしょうか。
土屋:店舗数は今857ですが、2000くらいまでは伸ばせるのではないかと考えています。既存のフランチャイズ店から「忙しすぎるので近くに出店を」と言われるケースも出てきています。各店の売上高は1億5000万円くらいがオーナーの幸福度が高い。それを超えると、入荷量も増えるので品出しも大変です。最終的にはオムニチャネルにも取り組む予定なので、1500〜2000店になったとしてもその一部は受け取り専用という可能性はあります。
ユニクロはベーシックな商品が多く、原価率も違うので、向こうの方が私たちを競合ととらえていないのではないでしょうか。アパレル市場はこれまで有名ブランドしかなかったので、参入にはブランド化が必要だと言われていました。私たちもそのつもりで「ワークマンプラス」を立ち上げ、そのブランドを確立させるまでに時間がかかると思っていました。実際は、高機能・低価格という4000億円規模の空白市場がありました。これはチャレンジして初めてわかったことで、私たちにとっても驚きでした。この市場で25%、1000億円を獲得することを目指しています。
【対談を終えて】
「2019年日経トレンディ ヒット商品ランキング1位」「対前年売上60%アップ」「ユニクロの店舗数を抜く」「同じ商品を見せ方を変えて別ブランドとして売る」。数々のニュースで紹介された『ワークマン』のユニークな勲章に、かねてから興味を持っていました。作業着店からアウトドア・ショップへ。”机上のマーケティング“だけではなく、”顧客志向のリアルなマーケティング“の強さ。ステルスマーケティングとトライブ・マーケティングの狭間の中で、アンバサダープロジェクトなど、SNSをも巧みに使いこなすワークマンは、成長企業の重要要素である「スピード経営」と「変化への対応力」を兼ね備えた組織であるということを、今回の取材を通じて改めて感じました。
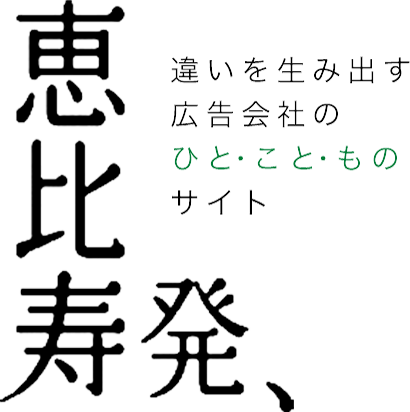
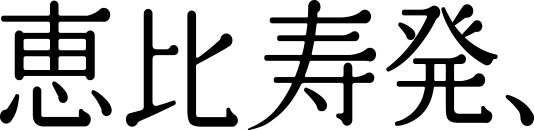








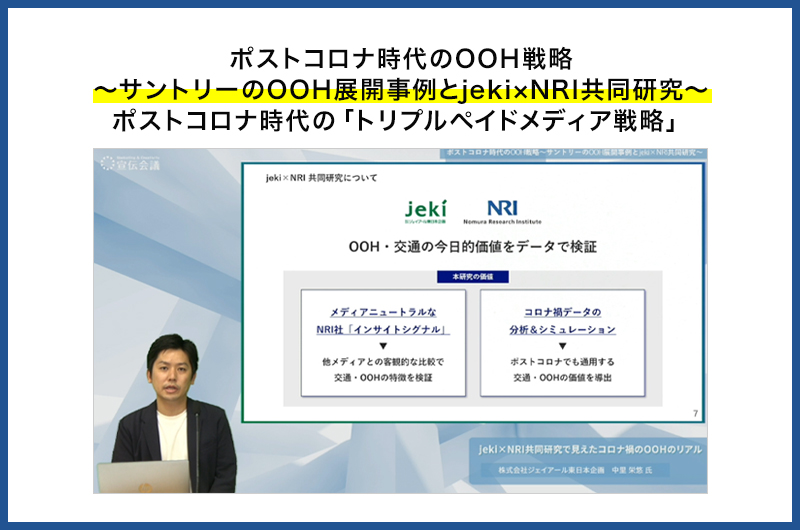















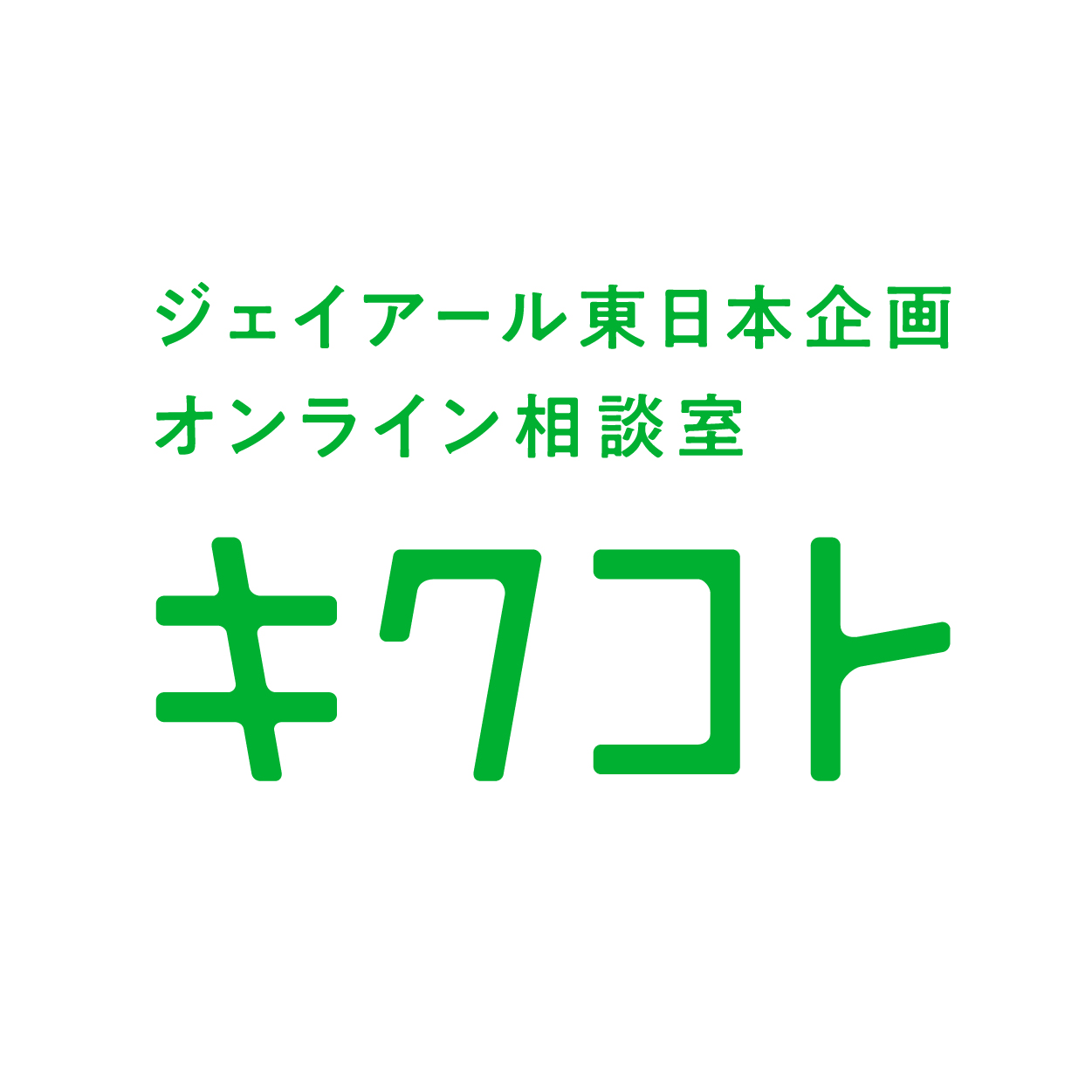


















萩原 浩平 上級執行役員 デジタル・ソリューション局長
上級執行役員 デジタル・ソリューション局長 1998年 jeki入社 マーケティングからデジタル領域全般を担当。幅広い人脈を持ち、メディア・コンテンツ開発や、新規事業開発、データ活用ビジネスなど様々な分野に対応する。現在は㈱JIC、㈱MMSマーケティングの取締役、㈱JDDLの代表取締役を務める。