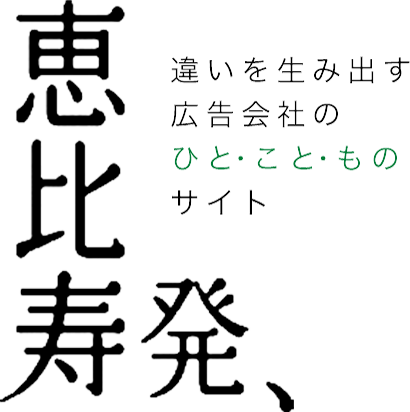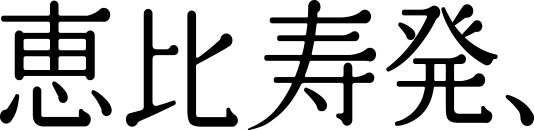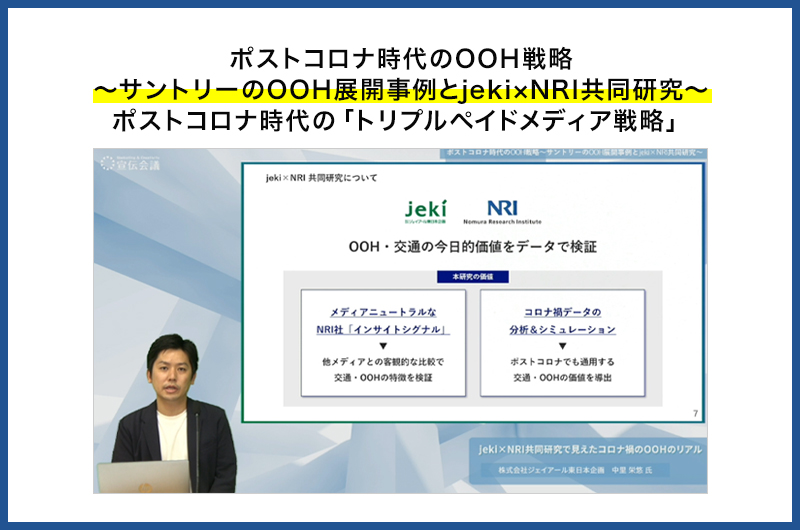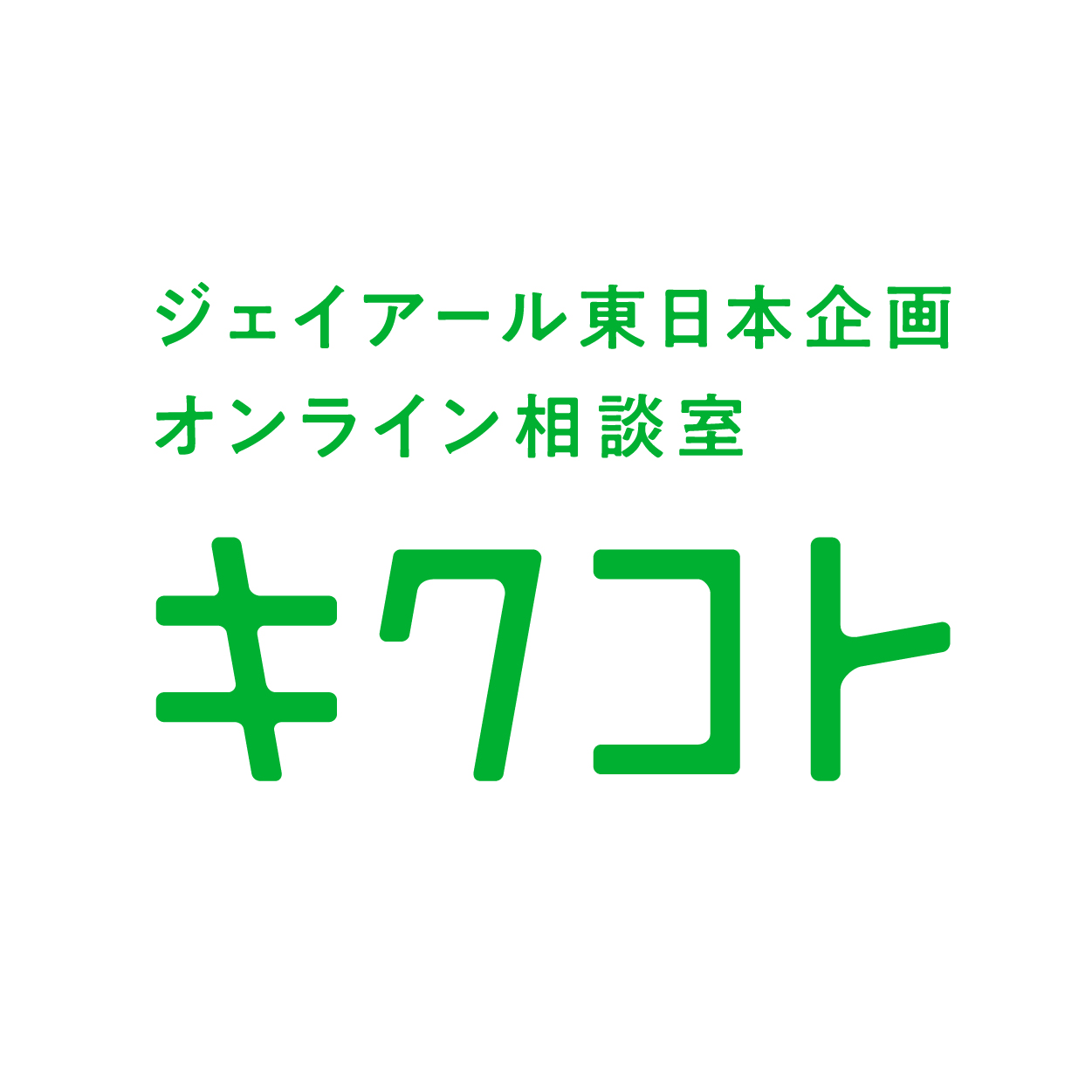写真左より
宣伝会議 マーケティング研究室 谷口優(聞き手)
アウトブレイン ジャパン株式会社 顧問/アビームコンサルティング株式会社 顧問 本間 充氏
株式会社ジェイアール東日本企画 CDO 高橋敦司
株式会社小霜オフィス/no problem LLC.代表 小霜 和也氏
ハウスエージェンシー、媒体社、総合広告会社の3つの側面を持つジェイアール東日本企画(jeki)。jekiは急速に進むデジタルシフトへの対応を目指し、常務取締役である高橋敦司のCDO就任と、小霜和也氏のデジタルアドバイザー就任を発表した。jekiが考える「デジタルシフト」とは一体どんなものなのか。そして、そこから見えてくる広告会社の未来とは。小霜氏、高橋と、広告主側の立場でも広告会社を見てきた経験のある本間充氏の3名に共同取材を進める宣伝会議マーケティング研究室が聞いた。
※所属・役職は取材当時のものです。
「デジタル化」は広告の世界に何をもたらしたのか?
――小霜さんはクリエイターとして、本間さんと高橋さんは事業者側も経験されたお立場と、同じ広告・マーケティングに携わりながら、立ち位置が異なると思います。まずはお三方に今日のテーマである、「デジタル化」についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。そもそも、マーケティングのデジタル化とは何を意味するものでしょうか。

本間 充 氏
本間:今は、私たちが思っている以上に生活者の方がデジタル化していると言えます。広告の出し方も、同じ時間、同じ場所で、全ての人に同じものを見せるワンメッセージの時代から、お客さま一人ひとりに合わせてパーソナライズできる時代になっている。そういう意味からも、広告メディアがデジタル化しているだけではなく、広告コミュニケーション全体がデジタル化していると考えています。
小霜:僕は自分の仕事をクライアントの課題を解決することだと考えてきました。ですからデジタル化したことによって、課題解決のための武器が増えた、よりいろんな課題に適した提案がしやすくなったと感じています。 広告業界はテレビCMとデジタル広告を区別して捉えがちですが、それは生活者にとってはまったく関係のないことで。クライアントの課題解決のためには、本来はすべてのメディアをシームレスに捉える必要があると考えています。
高橋:広告主側でマーケターをしていた経験からすると、デジタル化によって、コミュニケーションの「上流」「下流」という意識や順序を自由に変えることができるし、もし、問題があってもすぐやり直しができるようになったと捉えています。
広告会社の取締役という、現在の立場で見れば、デジタル化によって、あらゆる面でローコスト化が進み、アジャイルな対応が求められ、複数のクリエイティブも瞬時に制作・変更できる可能性が生まれたことを認識しなければならない。そうした環境下でマーケティングからコミュニケーションまでの流れを考えていくことが「デジタルシフト」だと考えています。
――広告会社である一方で媒体社でもあるjekiで働く社員は、この「デジタル化」にどう対応していけばよいでしょうか。

高橋 敦司
高橋:私たちの事業はJR東日本グループのハウスエージェンシー、媒体社、そして現在では売上の4割を占める中核事業とも言える、一般広告会社の3つのボックスから構成されます。しかし、自分たちでただ、その「3ボックス」のラベリングをあまりにも硬直化して捉え、ミックスアップする意識を持たないのは危険。デジタル化はそうした定義をも無効化してしまう可能性を持っています。
今後は、クライアントが自ら課題を見つけだし、広告会社はそれに対するソリューションをクライアントが認識している課題の範囲内で提案する、という従来型の仕事の進め方では立ちゆかなくなります。クライアントから見て「jekiにしかできない仕事」をデジタル領域で考えれば、おのずとよりマーケティングの上流の、課題発見のところからプレイすることを望まれるはずです。だからこそ、jekiのデジタルビジネスモデルはまったく新しいものだという意識が必要です。
本間:jekiさんの一番のメリットは交通広告という媒体を持っていること。さらに、JR東日本管内という非常に乗降客数の多い場所や、そこに有効な広告を掲出できる場所を持っています。そうした「他にはない強みは何か?」を理解し、そこにデジタルの要素を加えることで何ができるのか、それはどうすればマネタイズできるのかを考えたときに今までできなかったことができるようになるチャンスがありますよね。今、自分たちが持っているものを要素ごとに分解して、そこにデジタルを掛け合わせることで何が起こるのか考え、実行していくことが大事になると思います。
――デジタル化が進むと「広告」の定義や広告会社の役割は変わっていくのでしょうか。

小霜 和也 氏
小霜:テレビCMは、必要のない商品情報に「付き合わされるもの」でもありました。ですから、誰が見ても受け容れられる、最大公約数的に面白いものがクリエイティブとして優れているとされてきました。一方でWebはターゲティングが可能です。その精度が高くなればなるほど、エンタテインメント性はむしろ余計で、必要な情報だけで良いということになって来る。そして、僕の経験から言えばその方が売上に貢献する傾向があります。
これはターゲティングが緻密にできているからエンタテインメントはなくても良い、これはターゲティングが大ざっぱだからマス的エンタテインメントが必要、などとケースバイケースでクリエイティブを決めていく、そこまで俯瞰する能力がこれからのクリエイティブディレクターに求められると思っています。
本間:広告は「広く告げるもの」なので、特に80年代から90年代の日本経済はマス広告が刺さった。近年は、あらゆる面でコモディティ化が進み、「私に一番ふさわしいものを教えて欲しい」と感じる人が増えています。
小霜さんがおっしゃる通り、エンタテインメント性はいらないという人もいれば、深く考えずに一番面白いものが欲しいという人もいるでしょう。ですが、生活者の情報の受け取り方を判断し、ふさわしい情報を伝え、広告主をサポートするという本質は変わらない。ただクリエイティブの手法も媒体も変わっているので、そこに対応する柔軟さは必要です。
自分が何者なのかを問い直し、役割をデザインすることで強みを最大化する
――デジタル化が広告、メディア界のビジネスモデルも変えてしまうと思いますか。
本間:今、テレビ局やラジオ局も広告収入だけに依存するビジネスからの脱却を考えています。近年はテレビ局もネット配信によるPPV(ペイ・パー・ビュー)やコンテンツライセンス事業などに着手しはじめ、自分たちが何者なのかを再定義する段階に突入しています。今、テレビ局は、電波塔か、放送編成か、その先にいる制作会社か、何がその企業の強みなのか再確認している。jekiも同様に、鏡を見て自分が何者なのか、箇条書きにして再定義する時期にさしかかっているのではないでしょうか。
小霜:自分は日テレのアドバイザーも務めていますが、TV局はテレビとデジタルを分けるという発想ではなく、どうすればシームレスなビジネスモデルにできるかを考え始めています。それは広告コミュニケーションでも同じで、シームレス化の過程でいろいろなレイヤーで課題があり、今はそれを探っている状況にあると思っています。
高橋:とはいえ、ナショナルブランドを持つ大企業の多くは今後もテレビに広告を出し続けるでしょう。その一方で、デジタル化によって多種多様な方法で生活者にリーチできるようになり、今まで「とてもマス広告なんて」と思っていた企業がメディアに向き合うチャンスにもなっています。
単に既存メディアが衰退し、Webメディアにシフトするという発想ではなく、広告主ととらえられるゾーンが広がっているのだと感じています。デジタル広告への理解が深くない広告主もまだ多く、そうした企業にとって、マーケティングツールとしてのデジタルサイネージやそれと連動したSPなどは初めてのコミュケーション手段になりうると感じています。そういう点で、交通広告の雄たるjekiだからこそできるデジタルコミュニケーションがあるのではないか、と思っています。
本間:広告主の中には、今までコミュケーションの場としてはあまり考えていなかった「移動時間」に目をつけはじめた企業が出はじめています。デジタルサイネージに関しては、手法や開発に余地があり進化させられるタイミングでもある。jekiさんがその可能性を明らかにできれば、それだけで自社の価値を示すことにつながると思います。
小霜:今回、僕がjekiのアドバイザーに就任して、やりたいことのひとつがデジタルサイネージの可能性を開くことです。
流通業には「ラストワンマイル」という言葉がありますが、広告業界にも最終的にどうやってターゲットを店舗に送客するかという、同様の概念が入って来ています。デジタルサイネージには送客メディアとしての可能性があると僕は思っていて、それには相応のクリエイティブがあると考えています。これからは、コミュニケーションの全体を俯瞰して見ることができないとクリエイティブの仕事ができないという時代になっていく。その流れのなかでjekiは、マス広告やウェブ広告に強みを持つエージェンシーとは一線を画した、オフライン店舗への送客に強い、売りの現場に強いエージェンシーであるということにまず軸足を置いて、そこでのクリエイティブでは絶対に負けない、というところから得意領域を拡げていくべきじゃないかと思っています。
高橋:30年前にjekiをつくった人たちは先見性がありました。それは会社の英文名を「East Japan Marketing & Communcations」と名付けたことです。まずはマーケティングがあり、コミュニケーションがある。大阪や名古屋、海外の仕事も増えて「東日本」ではなくなりましたが。
私たちのコア・コンピテンシーの定義の仕方次第で、上流から下流までの全てを担う独自のモデルを作ることができると思っています。そこで、ハウスエージェンシーであり媒体社であるという既存の強みを消す必要はなくて、本間さん、小霜さんのおっしゃる通り、1日に1750万人が利用する生活者を抱える駅や電車のサイネージに、広告媒体としてだけではない何かを見いだすことができれば、商品開発やマーケティング、ブランディングのベースに化ける可能性があります。
近年、広告の世界にはコンサルティングやマーケティングファームというライバルが参入しています。しかし、「ラストワンマイル」の部分で生活者との接点を持ち、コミュニケーションの手法と手段を持っているわれわれには一日の長があるはずです。そのアドバンテージを生かすためにも、今、広告会社としてのjekiの役割をデザインする必要があると感じています。

小霜 和也
株式会社小霜オフィス/no problem LLC.代表
1962年兵庫県西宮市生まれ。1986年東京大学法学部卒業、同年博報堂入社。1998年退社。2018年現在(株)小霜オフィス/no problem LLC.代表。内閣府政府広報アドバイザー。クリエイティブディレクター、コピーライターとしてマス・Webを統合する広告キャンペーンに携わる一方、幅広い企業のクリエイティブ・コンサルティングにも従事。広告賞受賞多数。

本間 充
アウトブレイン ジャパン株式会社 顧問/アビームコンサルティング株式会社 顧問
1992年、花王に入社。1996年まで、研究員として、スーパー・コンピューターを使って、数値シミュレーションを行う。社内での最初のWebサーバーを自ら立ち上げ、以後本格的にWebを業務として取り組み、1999年にWeb専業の部署を設立。2015年10月に、アビームコンサルティング株式会社に入社。現在は、その他、アウトブレイン ジャパン株式会社 顧問や、ビジネスブレークスルー大学講師、東京大学大学院数理科学研究科 客員教授(数学)を務めている。