日本酒づくりに欠かせない杜氏に頼らず一年を通じて醸造するという、業界の常識を破りながらも、多くの消費者に支持されるブランドとして成長してきた「獺祭(だっさい)」の製造・販売を行う旭酒造。“味わうため”の酒づくりにこだわってきた同社は、昨年末「お願いです。高く買わないでください。」という新聞広告で話題を集めることとなった。2016年、社長職を引き継いだ桜井一宏氏に「獺祭」ブランドが目指す未来について、ジェイアール東日本企画 営業本部 第三営業局長の大熊仁が聞いた。

旭酒造 代表取締役社長 桜井一宏氏(右)
ジェイアール東日本企画 営業本部 第三営業局長 大熊仁(左)
本当に届けたい人に思いを伝えるための「買わないでください。」という強いコピー
大熊
昨年末の旭酒造さんの「お願いです。高く買わないでください。」というコピーの新聞広告は、大変話題になりました。広告会社で働く私としては、「買わないでください。」という強い言葉を使ったときの反応が気になります。社内外で、どのような反応があったのでしょうか。
桜井
いつも依頼しているデザイン会社も、また出稿先の新聞社からも抵抗はあったようですが、私たちの思いをはっきり伝えなければ広告を出す意味はないので、今回はシンプルな言葉を選びました。
反応はまさに賛否両論です。具体的には「炎上マーケティングではないか」、「資本主義を否定するのか」「出荷量が増やせない私たちが悪い」という意見もありました。
しかし、本当に伝えたかったのは、インターネットもソーシャルメディアも使わないようなお客さまに「町の酒屋(正規販売店)のほうが、良い状態の『獺祭』を適切な価格で買えるんですよ」ということです。
その点では、ファックスや手紙で「今まで買っていた『獺祭』は高かったのだということがわかった」「買いに行ったら高かったのでやめた」というお声をいただいて、期待した効果は得られたと思っています。
今回、ソーシャルメディアで拡散し話題が大きくなったのは想定外でしたが、結果的に注目が集まり、多くの人に私たちの思いを届けられたと感じています。
「飲んでもらうこと」、それ自体がマーケティングである
大熊
旭酒造では、広告やマーケティングに対してどのような考え方を持っていますか。
桜井
すべては「飲んでもらってこそ」だと考えているので、イベントに商品を提供する場合でも、ロゴを出すことよりも、温度や器、輸送中や現場での管理・保存などをしっかりとすることに最大限の配慮をします。そこで美味しく感じてもらえれば認知につながる。飲んでもらうこと自体がマーケティングなのかもしれません。

大熊
正しい状態で飲んでもらうことがマーケティングというお話は興味深いです。
新たなファンを増やす一方で、既存のファンを満足させることも大切です。そのバランスについてはどうお考えですか。
桜井
その点は、あまり気にしていません。私たちは、山口県ではほとんど売れず、東京の市場で受け入れられたことで広まりました。品質重視型のブランドへシフトできたのも東京を起点に受け入れられたからで、古くから特定のエリアや層の根強い支持があったわけではありません。
日々少しでも美味しいお酒をつくることこそが、私たちがすべきこと。その軸さえぶれなければ、新しいお客さまとの接点も生まれ、また既存のファンの方々にも満足いただけると考えています。
ブランドとして、より良いものづくりを目指していかなければ消費者の満足は得られませんし、特定の地域や既存の顧客だけを対象にしていては行き詰まってしまうのではないでしょうか。
気にするのは「獺祭」を飲んでくださる、お客さまの反応だけ
大熊
お話を伺っていると獺祭は「日本酒」というカテゴリーではない市場を見ているように感じます。「獺祭」にとってのライバルや競合についてはどう考えていますか。
桜井
日本酒業界や特定の酒蔵をライバルだとは考えていません。例えば、この「獺祭ストア」がある銀座エリアの飲食店で考えてみても、日本酒しか置いていないという飲食店はない。お寿司屋さんにもワインは置いていますし、ビールにいたっては置いていない飲食店を探すほうが難しい。
つまりは「日本酒」という市場で争うことに意味はないのです。これは業界全体で意識を変えていかないといけないのかもしれませんが、私たちはすべてのアルコール飲料と競いながら、選ばれるようなものづくりを考えています。
スポーツ選手も「俺は地元を愛しているから地元でしか試合をしない」では、絶対にオリンピックで金メダルは取れません。強い相手と試合をして、地元や日本を背負って挑戦することに価値がある。
私たちも地元や日本を背負って「ドン・ペリニヨン」や「オーパス・ワン」、「クリュグ」や「山崎」といった名だたるブランドやビール、ウイスキーなどと競い合いながら、価値を提供していくことのほうが大事だと思っています。それが結果として「獺祭」であり、日本酒だったと、そういう方向へ進んでいきたい。

大熊
世界で価値を提供していくときに、「日本酒の『獺祭』です」と呼びかけることと「『獺祭』は日本酒です」という表現ではPRの仕方も変わってくるのではないかと思います。
桜井
海外で日本酒を広めようとするときには、伝統や文化的背景とともに「“日本酒”は美味しいものです」とすべてを同質化してしまいがちです。ですが、現実的には酒蔵やつくり手によって味は違います。
私たちのスタンスは、ワインも美味しく感じるものとそうでないものがあるように、日本酒にもいろいろあるけれど、私たちは美味しい日本酒をつくっていますというもの。そういう意味では後者です。
護送船団方式で日本酒を世界に売り込むよりも、まずは「獺祭」の味を知っていただき、気に入っていただきたい。そして、後から「獺祭は日本酒です」ということを伝えればいい。リスクも手間もあるかもしれませんが、私たちはそれをやっていく覚悟があるんです。
今はまだ、海外では「獺祭」は東洋のエキゾチックなお酒として、少々高くても仕方ないものという認識で味わっていただいていますが、海外でも最高の状態の「獺祭」を、適正な価格で飲んでいただくことができる状態にしていきたいと考えています。
先代が山口県から東京へと進出してきたように、今度は私が日本から世界へと広めていきたい。これは2016年に会社を引き継いだ私の役目のひとつだと考えています。

大熊
自分たちの歩む道をしっかりと確実に進むことが、結果的にブランドやそれを含む業界のためにもなるということですね。今後も国内外で競い合っていくなかで、気にすべきことは何でしょう。
桜井
気にするのは、「獺祭」を飲んでくださっているお客さまのことだけです。これは東京へ進出してきた頃から変わらず、美味しければ認められるというシンプルな原理で成長してきました。
自分たちで飲んで、お店で隣の席の人が飲んでいる表情や態度を見て、美味しそうかどうか、そこが大事だと思っています。
味が落ちていると誰かが気づけば、すぐに社内で情報が回ります。どこに問題があるのか、原因を追求し、改善する体制はここ数年でできてきました。これは「獺祭」が年間を通じて製造していることの強みでもあります。
最近は、美味しいから飲むという人に加えて、「かっこいいから」という人も増えているように感じます。
そうした消費者にも受け入れてもらえるよう、「きちんとつくった良いものを飲むことはかっこいい」というシーンをつくることも大切だと思っています。
【 対談を終えて 】
徹底した数値管理で年間を通じ、杜氏がいなくても実現する、高品質の酒づくりで世界的な評価を受けてきた旭酒造さん。桜井社長も「モノづくり」のプロフェッショナルな方であろうと思いお話を伺いましたが、それだけでなく「コトづくり」のプロでもあることにとても感銘を受けました。我々、広告会社も「コトづくり」のプロであるべきですから、桜井社長に負けぬよう、さらに精進しなければならないと感じました。
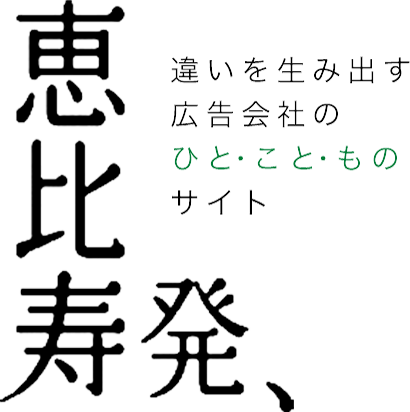
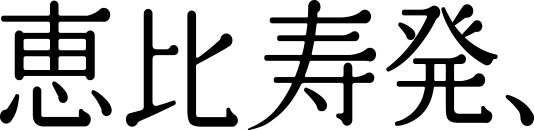









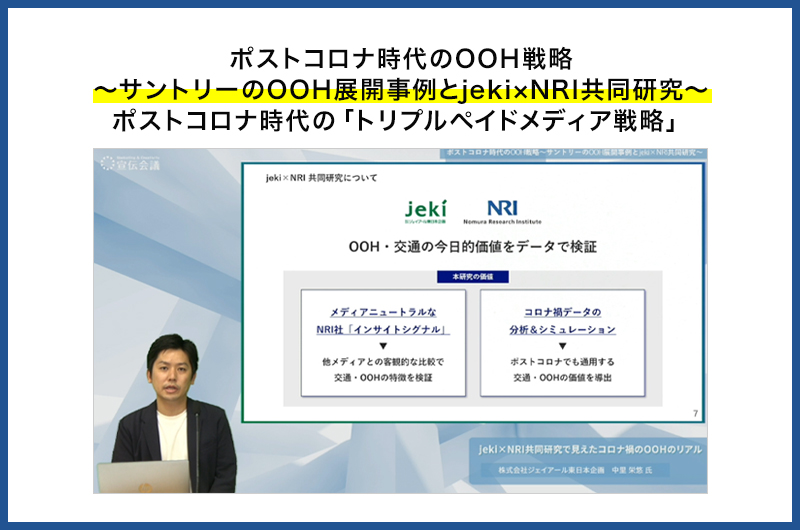












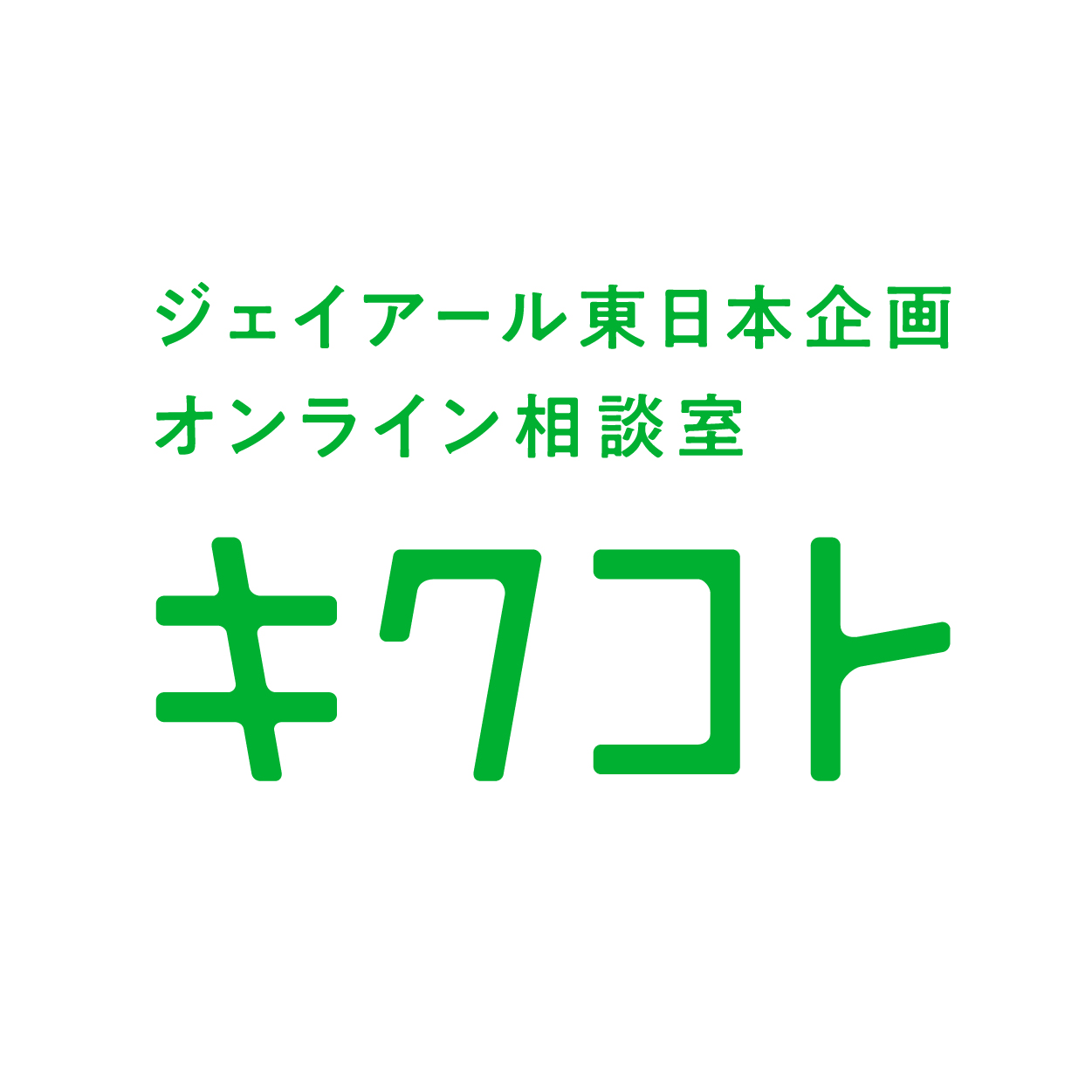


















大熊 仁 第三営業局長
1992年jeki入社。入社以来25年間、一貫して営業部門を歩む。 人材系クライアントを長く担当し、2006年営業部長、2016年12月より現職。