
近年のコーヒーブームが続く中、街でよく見かけるようになったコーヒースタンド。こだわりの一杯を提供しようと各店がドリップの腕を競うなか、「silo coffee stand(シロコーヒースタンド)」が最も大事にしているのは、お客さまとの3分間のコミュニケーションです。そして注目すべきポイントは、店主のヤベケンタさんが現役の美容師であること。美容師のヤベさんがコーヒースタンドに新たに求めたコミュニケーションのあり方や、街における店の役割について伺いました。

ヤベケンタさん
silo coffee stand 店主
1981年埼玉県生まれ。15年以上の経験を持つ美容師で、東京都中野区の美容室「silo」や「silo coffee stand」などを経営。毎週木曜の午前中はバリスタとして店頭に立ちながら、美容師の仕事を続ける。2022年に新たにオープンさせた美容室「nilo」は飲食店登録済みで、カット中に本格コーヒーを提供している。
「実家のような街」で気軽にあいさつがしたかった
なぜ美容師のヤベさんがコーヒースタンドを始めたのでしょうか?
ヤベ:美容師として長年過ごし、実家のように感じている中野区(東京都)で、街の人と毎日気軽にあいさつができる場所を作りたかったんです。僕は生活に特化し、地域に根差す仕事をしたかったのですが、美容室はしょっちゅう立ち寄る場所ではありません。そこで思い浮かんだのが、そのとき通っていたコーヒースタンドでした。カフェよりも店員とお客さまとの間に会話が生まれやすく、コーヒーを淹れ手渡すまでの3分間という、ちょうどいい距離感のコミュニケーションが理想的でした。
実は美容室のオープン当時から、商店街を活性化させたい、他業種の展開もしてみたいという思いがあったんです。商店街の活性化を目的にした、東京都中小企業振興公社の助成金を活用して、2020年、美容室のある商店街にsilo coffee standを出店しました。
silo coffee standの特徴を教えてください。
ヤベ:僕を含むバリスタが毎日交代で店に立ち、1人で接客しています。1時間の休憩をはさむ二部営業とし、出勤表はSNSで公開しています。コーヒーショップでは店の味がぶれないことが常識とされていますが、うちではバリスタによって味が変わってもOK。バリスタごとに異なるコーヒーの味わいや会話、空気感を目当てに、日によって違うお客さまが訪れています。
内装はデザイナーを入れず自分で設計し、寸法を計算しました。店の面積は3×3mの正方形なのですが、カウンター越しの対面距離を、近すぎず遠すぎない90㎝に設定しています。独自のカフェ文化が根付くオーストラリアのメルボルンに行き、コーヒー店のカウンターを実際に測って参考にしました。茶室の距離感とも似ていると、よく言われます。

近くのプールに通うついでによく寄るという常連客とヤベさん。ヤベさんは、店員と客が話す機会の少ないカフェではなく、ちょっとした会話を楽しめるコーヒースタンドを選んだと話す
美容室とコーヒースタンドのコミュニケーションには、どんな違いがありますか?
ヤベ:美容室で過ごす時間は1、2時間ですし、どんな方なのか顧客情報を把握しているのに対し、コーヒースタンドでの接客はおよそ3分で職業も年齢も聞きません。かなり対照的ですが、実際にやってみるとコーヒースタンドでもコミュニケーションが成立することが分かりました。カウンターで横並びに座った人同士が自然発生的に会話をしたり、バリスタがお客さま同士をつなげたりして、そこから友達になる人たちも。
コーヒースタンドに来れば悩んでいることが解決する、そんなコミュニティーに育ちつつあります。ホームや拠点となるベースを作っているような感覚でしょうか。この場所に人が集まって新しいコミュニティーを生み、さらにコミュニティーが縁をつないで新しいきっかけを作る。その循環が、街や人、店には必要ですし、長く愛される店になるための要素だと思っています。

看板商品のラテと、スタッフの友人のパティシエに特別に作ってもらっているスイーツ
カフェの本場メルボルンから取り入れたのは、コミュニケーションが図れる「人材」
silo coffee standをオープンさせる時、どのようなことを重視しましたか。
ヤベ:「地域にフィットする」ことを大事にしました。ただ、それには街の人を知らないと始まりません。美容室だけではどこにどんな人がいて何をしているのか分からなかったので、コーヒースタンドを始めてから徐々にフィットさせていった感じです。実際にコーヒースタンドを始めると、圧倒的に情報が入ってきました。自分のことも街に知ってもらえるようになり、互いにあいさつを交わす間柄になることができました。
中野の街を知ると、どんどん変化していることが分かります。アニメなど、サブカルチャーの街として知られていますが、地元の店では世代交代も始まって、次世代がおしゃれで新しいことを仕掛ける「足し算」が生まれていると感じます。
中野は転出・転入する人も多い街。引っ越してきたコーヒー好きの人が、どんな店かと来店してコミュニティーに加わり、中野から離れても通い続けてくれる。循環があるんです。再開発によって中野は変貌していますが、店もそれに合わせつつ、何ができるかを主体的に考えていく必要があると思っています。

歩道と境目のないオープンスペースは、お客さん同士のコミュニケーションの場
カフェ文化の実地調査にメルボルンまで行ったとおっしゃっていましたが、お店の運営に取り入れたことは何かありますか?
ヤベ:お客様とコミュニケーションが図れる「人材」ですね。メルボルンではとにかく、スタッフとお客さんがおしゃべりを楽しんでいたんです。silo coffee standでは僕ではなくバリスタが主役だと考えています。なのでスタッフの採用基準は、コミュニケーションをしっかり取るという接客に対する価値観の確認と、僕がその人の夢を応援してあげたいと思えるかどうかという2点だけ。
履歴書には独自のフォーマットを使っていて、1年後、3年後、5年後の夢を書いてもらいます。別にコーヒーのことでなくてもいいんです。店では服飾など異業種とのポップアップイベントや、バリスタ同士の連携イベントなど、好きなことをやってもらいたいですね。僕はスタッフたちを後押しする役割でいたいと思っています。
スタッフの夢を応援したり、地域に根差したコミュニティーづくりを意識したりしていらっしゃるのは、どのような思いからでしょうか?
ヤベ:地域の活性化や、人と人が関わって楽しいことが生まれる場になってほしいという思いが前提にありますが、自分がやりたいことをするにはいろいろな人の力が必要だからです。助けてもらうだけでなく、自分も誰かを助けてあげたい。人をどれだけ応援していけるかということを目標にしています。でも僕の中ではまだゴールは決めておらず、今は完成図が分からないままパズルのピースを埋めている最中という感覚です。
ただ、コーヒースタンドを開いた3年前とは僕のコミュニティーは明らかに変わりました。silo coffee standのインスタグラムは、僕がフォローしてきた人数がそのまま関わってきた人の数を表しています。まだ道の途中で、共感、共鳴、応援してくれる人を増やしていきたいです。現在フォローしている人数は5千人ほどですが、まずは1万人を目指したいですね。数が増えていくと、また面白い展開が待っていると思うんです。
聞き手 松本阿礼/聞き手・文 中村さやか/写真:徳山喜行
〈完〉
※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.56掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年6月)のものです。









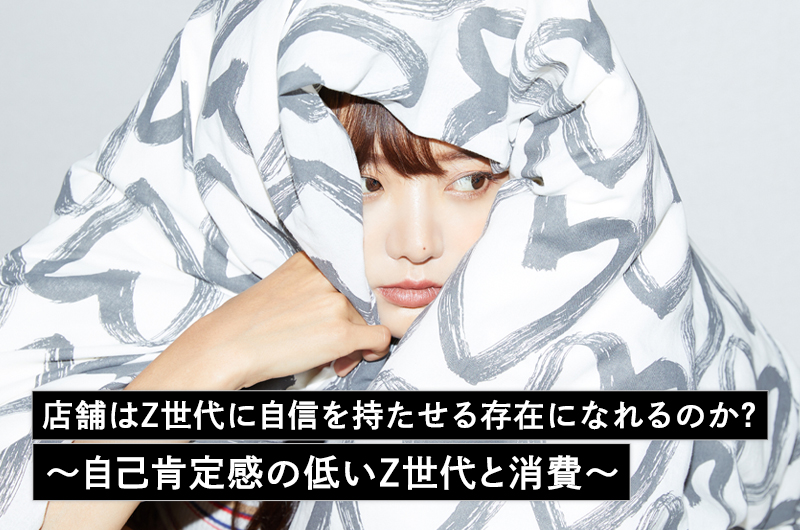
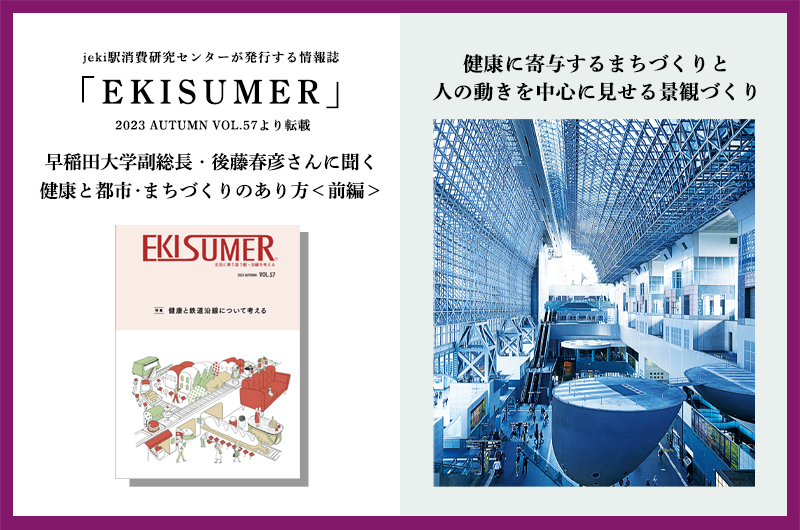

































町野 公彦 駅消費研究センター センター長
1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。