
令和3年6月の育児・介護休業法の改正で、「産後パパ育休制度」が創設され、令和4年10月に施行となります。男性の育児参加が注目される今、イマドキファミリー研究所では、まだ子供のいない共働き夫婦世帯に調査を行い、今後の子育てに関する意向などを聴取しました。今回は、将来子供を持つ可能性のある「共働きパパ予備軍」に着目した調査結果をご紹介します。
※文中で使用される「共働き」「パパ予備軍・ママ予備軍」「パパ・ママ」の定義は以下の通りです。
・「共働き」…自身および配偶者がフルタイム勤務
・「パパ予備軍・ママ予備軍」…将来子供を持つ可能性ありと回答した男女
・「パパ・ママ」…2021年度「子育て家族に関する調査」の調査対象者(末子小学校3年生以下を持つ男女)
共働きパパ予備軍の「育休を取得したい意識」は8割超!
下記グラフAは、2021年度実施の「共働き夫婦に関する調査」より、パパ予備軍の育休取得に対する意識を聴取したものです。共働きパパ予備軍の「育休を取得したい計」は83.2%と非常に高く、なかでも「取得すると思う」は51.0%と半数を超えています。また、共働きパパ予備軍より10ポイント以上低いものの、妻専業主婦パパ予備軍でも「育休を取得したい計」は7割を超えるという結果でした。
2021年度実施の「子育て家族に関する調査」より、共働きパパの育休取得実態(グラフB)を見ると、育休を「取得した」人は約2割と低く、育休の「取得・検討計」でも、共働きパパ予備軍の「育休を取得したい計」の半分にあたる4割に留まります。共働きパパ予備軍は、パパになる前から育休取得に特に高い関心を寄せていることがうかがえます。


一方で見逃せないのが、グラフAの青点線で囲んだ「取得したいが取得できないと思う」という、育休取得を諦めている共働きパパ予備軍が32.2%、妻専業主婦パパ予備軍では30.0%とそれぞれ約3割を占めていることです。職場環境や業務内容など、育休を取りたくても取れない状況下であることも浮き彫りとなりました。
夫婦で支え合う意識が高い、未来の共働きパパ・ママ
2021年度実施の「共働き夫婦に関する調査」より、育休取得の意識が高い共働きパパ予備軍の育児関与意識について見てみたのがグラフCです。共働きパパ・ママ予備軍はどちらも、「夫婦は同じくらい育児に関与すべきだと思う」という意識が「あてはまる」「ややあてはまる」を合わせて8割を超え、妻専業主婦パパ予備軍よりも高い結果となりました。共働きパパ・ママ予備軍は、育児を夫婦でシェアしていく意識が特に高いことがうかがえます。

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月に産後パパ育休制度が施行となります。法の改正により、職場の環境改善が進むことで、育休取得を諦めていた男性も取得しやすい環境に変わり、夫婦ともに仕事と家庭のバランスを取りながら、より子育てしやすい社会となっていくことが期待されます。
2021年度研究「共働き夫婦に関する調査」
“共働きパパ予備軍”の「育休を取得したい意識」は8割超!
夫婦で支え合う意識が高い、未来の共働きパパ・ママ
2021年度「共働き夫婦に関する調査」
- 調査地域 : ●首都40km圏(東京駅を中心とする40km圏内の東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
●中京圏(愛知県、岐阜県、三重県)
●関西圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)
※今回の記事においては首都40km圏のみのデータを使用しています。 - 調査方法 : インターネット調査(調査会社のパネルを使用)
- 調査対象 : 25~39歳の既婚男女で子供がいない方 計1600ss
夫婦同居であること。親同居者は除外
(女性側の勤務形態、居住地域で割付) - 調査期間 : 2021年11月26日(金)〜12月7日(火)
※比較した子育てパパ・ママ層は2021年度「共働き家族に関する調査」のデータを使用しています。
2021年度「子育て家族に関する調査」
- 調査地域 : 首都40km圏(東京駅を中心とする40km圏内の東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
- 調査方法 : インターネット調査(調査会社のパネルを使用)
- 調査対象 : 末子小学校3年生以下の25~49歳の既婚男性・女性 計1800ss
夫婦同居であること。親同居者は除外
(女性側の勤務形態、子供の学齢で割付) - 調査期間 : 2021年8月31日(火)~9月13日(月)










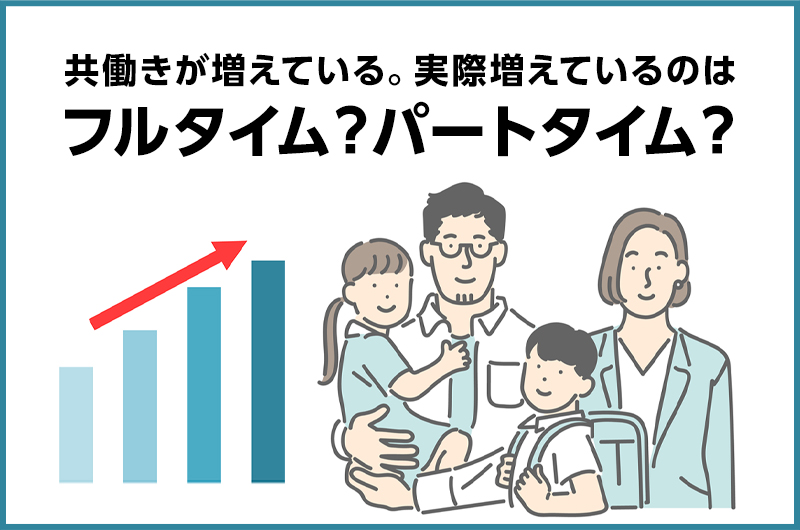

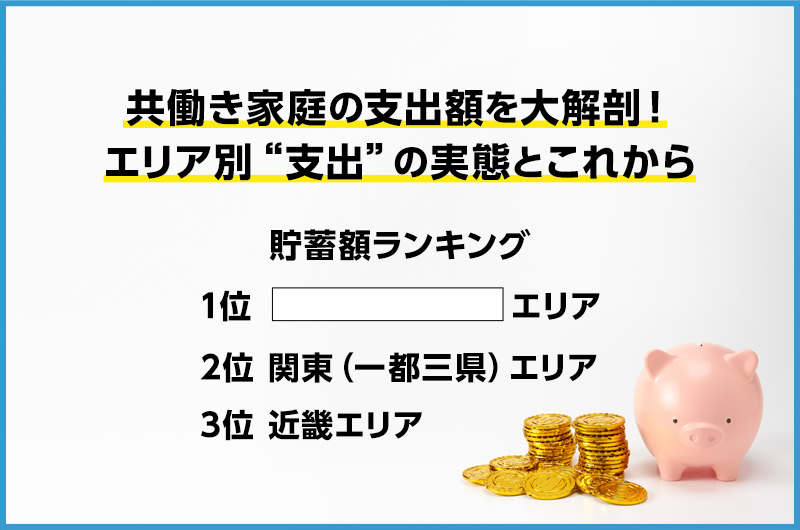





































高野 裕美 イマドキファミリー研究所リーダー/エグゼクティブ ストラテジック ディレクター
調査会社やインターネットビジネス企業でのマーケティング業務を経て、2008年jeki入社。JRのエキナカや商品などのコンセプト開発等に従事した後、2016年より現職。現在は商業施設の顧客データ分析や戦略立案などを中心に、食品メーカーや、子育て家族をターゲットとする企業のプランニング業務に取り組む。イマドキファミリー研究プロジェクト プロジェクトリーダー。